年間1mSv以上は国費で除染
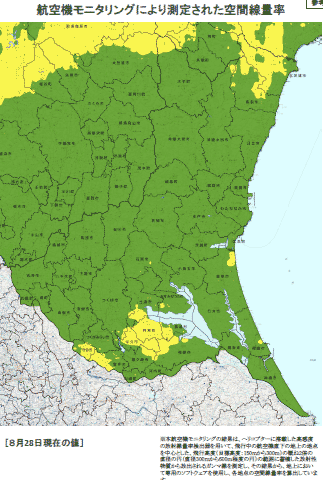 10月5日、環境省と原子力災害対策本部による放射性物質で汚染された土壌の除染の進め方や国の支援の考え方などについての説明会が行われました。
10月5日、環境省と原子力災害対策本部による放射性物質で汚染された土壌の除染の進め方や国の支援の考え方などについての説明会が行われました。
この説明会は今年8月に国が除染の基本方針を示したことを受けて開かれたもので、全国では福島県に続き2回目の開催となりました。県庁関係部局や県内39市町村の担当者、約200名が、放射性物質汚染対処特措法の趣旨や内容、除染活動の費用負担基準などが説明されました。
- 市町村が放射性物質汚染対処特措法に基づき地域指定(年間1mSv以上の地域)を受けて、除染実施計画を策定し、実施した除染に関しては、国の財政措置の対象となる。
- 年間1mSvを超える地域の基準としては、1時間当たり線量率は
0.25μSv0.23μSvとする。 - 国は、地域指定に当たっては、市町村の意向を踏まえて対応する。
- 中間貯蔵施設については、福島県以外では想定していない。
などとの具体的な説明がありました。
さらに、年間1mSv以上の地域として、文科省が行った空中からの放射線量測定調査から計算した結果を基に、例示した史料も配布されました。
なお、年間1mSvを超える地域の基準が、1時間当たり線量率は0.25μSvとなるかについては、再度、県から説明を受けたいと思います。1日の生活パターンを外で8時間、室内で16時間と仮定し、室内の線量率は外の20%として計算したものと推計されます。
(0.25μSv×8時間+0.25μSv×16時間×0.2)×365日=1022μSv

(2011/10/6更新)
5日開催された国の除染説明会で、「年間1mSvは、1時間当たり0.25μSvに換算」との説明について、5日夜、県に訂正のメールが国より入りました。
正しくは0.23μSv/h。これは、国の「第2回環境回復検討会」で示された内容と同じです。
その考え方は、追加被ばく線量年間1mSvを、1時間当たりに換算すると、毎時0.19μSvと考えられる。(1日のうち屋外に8時間、屋内(遮へい効果(0.4 倍)のある木造家屋)に16時間滞在するという生活パターンを仮定)。
※毎時0.19μSv×(8時間 +0.4×16時間)×365日=年間1mSv
この数値に、大地から元々発せられる放射線量1時間当たり0.04μSvを加えて、1時間当たり0.23μSvが算出されました。
詳しくは環境省のページに資料が掲載されています。「第2回環境回復検討会」の別添資料2:追加被ばく線量年間1ミリシーベルト、5ミリシーベルトの考え方
政府、年5mSv基準撤回 除染計画の市町村支援へ
茨城新聞(2011/10/6)
福島第1原発事故に伴う除染について、政府の原子力災害対策本部と環境省は5日、県庁で県内市町村職員を対象に説明会を開き、先月28日に福島県の説明会で示した「追加被ばく線量が年間5ミリシーベルト未満は財政支援の対象外」との方針を撤回し、除染計画を立てた市町村には原則として財政支援を行うとの考えを示した。ただ、具体的な除染計画の策定方法や財政支援の対象範囲などは示されず、出席者からは「早く指針を示してほしい」との不満の声が相次いだ。
除染に関する国の説明会は、福島県に続いて2回目で、県と市町村の担当職員約200人が参加。国の担当者2人が「除染に関する緊急実施基本方針」と来年1月1日に施行予定の「放射性物質汚染対処特別措置法」について説明した。
同省大気環境生活室の大村卓室長は「福島県の説明会で、年間5ミリシーベルトを境に除染のやり方が違うとしたのは不適切な説明だった」とし、「国はどこで(財政支援の)区切りをつけるか今は考えていない」と説明。「市町村の要望を聞き、必要なところで除染を進めていく」と述べた。
その後の非公開の説明では、国が除染の前提としていない年間1ミリシーベルト未満の地域でも除線の必要があるかについて個別に状況を見るとの考えが示された。
ただ、今回は基本方針や概要についての説明のみで、出席者からは除染計画の策定手順や今後のスケジュール、除去した土の処分方法など具体的な対応策を求める質問が相次いだという。それに対し、国の担当者は「決まっていない」「検討している」との回答に終始し、会場からは「説明会を開くなら、もう少し詳細が決まってからにしてほしい」との不満が漏れた。
説明会終了後、北茨城市の担当者は「(除染は)初めての経験で分からないことだらけ。早く具体的な指針を示してほしい」と求めた。守谷市の山中毅生活環境課長は「市で先行実施した除染に対してもしっかり財政支援してほしい」と訴えた。
また、橋本昌知事は同日の定例会見で、除染をめぐる国の方針の相次ぐ修正について、「きちんと詰めた後で言えばいいと思う」と苦言を呈した。



