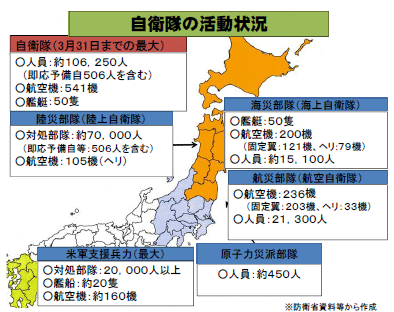
迅速な初動対応で人命救助にも貢献
東日本大震災では、自衛隊、警察、消防など国民生活を守る公務員の活動が目立ちました。中でも自衛隊は、その機動力や組織力を活かし、被災地の住民から高い評価を得ました。
地震発生の3月11日、自衛隊は大規模震災災害派遣と原子力災害派遣の命令を受け、即日約8400人を動員、18日には10万人態勢を整えました。派遣終了までに最大約10万7000人、延べ1000万人を超える隊員が自衛隊史上最大規模の活動を展開しました。
 震災と原発災害という複合事態に対し、放射能除染の部隊を投入するなど自衛隊は多様な能力を発揮しました。特に今回は、迅速な初動対応を実現し、全救助者の約70%に当たる約1万9000人の被災者を救出しています。
震災と原発災害という複合事態に対し、放射能除染の部隊を投入するなど自衛隊は多様な能力を発揮しました。特に今回は、迅速な初動対応を実現し、全救助者の約70%に当たる約1万9000人の被災者を救出しています。
その一方で官邸の「司令塔」が十分に機能せず、「派遣部隊が遊兵化し、その能力が発揮されない状況が生じた」(軍事アナリスト・小川和久氏)との厳しい批判もあります。
行方不明者の捜索活動では、岩手、宮城、福島の被災3県の沿岸・河口部で集中捜索を行い、全収容者の約60%に当たる約9500人の遺体をご家族の元に帰しました。
また、被災地で自治体の機能が失われ、支援物資の輸送が困難な中、自衛隊は3月15日、「物資輸送の一元的管理」の指示を受け、翌日、輸送体制を構築。都道府県で受け付けた救援物資を全国の駐屯地に集め、それを自衛隊機で輸送していきました。自衛隊は、被災自治体の一部機能を補うことになったのです。
予備自衛官を招集、訓練外で初の動員
政府は3月16日、元自衛官の志願者で構成される予備自衛官と即応予備自衛官の招集を閣議決定しました。訓練以外では初の招集で、北沢防衛相(当時)は「おおむね1万人規模で調整する」と述べました。
予備自衛官は有事の際、後方の基地警備などに就き、即応予備自衛官は第一線部隊で任務に就くことになります。平時は社会人として仕事をし、招集時は休暇をとって駆け付けます。今回、予備自衛官、即応予備自衛官ともに、招集の打診に対して約70%がそれに応じました。
陸自の場合、予備自衛官はトモダチ作戦で救援活動を支援する米軍との間の通訳や、医療技術の分野に従事、即応予備自衛官は災害派遣部隊の一員として被災3県の沿岸部に派遣され、捜索活動や給水活動など被災者の生活支援に従事しました。
予備自衛官、即応予備自衛官の初招集について防衛省は、「東日本大震災への対応に関する教訓事項について(中間取りまとめ)」(8月公表)の中で、「長年の会社等での勤務により向上したスキル(語学、医療、重機操作など)を駆使して活躍」したと報告、予備制度が「全体として円滑に実施」されたと評価しています。また、今回は1~2週間の招集であったが、雇用企業への影響もあり、招集期間の在り方について検討が必要だともしています。
統合運用の効果
政府は、前の「防衛計画の大綱」(2004年12月閣議決定)で、陸海空3自衛隊を個別に運用する体制から、3自衛隊の「統合運用を基本」とする体制への移行を決定、現大綱(10年12月閣議決定)もその強化を掲げました。06年から統合運用に移行し、3自衛隊を一体的に動かすための組織構築や指揮官の訓練などが進められてきた経緯があります。
今回の災害派遣に際し、自衛隊は初めて統合任務部隊を編成しましたが、防衛省は中間取りまとめで「各自衛隊の部隊が総合的に活動し、全般的に円滑な統合運用を実施」できたと評価しています。確かに、一気に10万人が派遣され、航空機による偵察や輸送、陸自部隊の海上輸送など迅速な活動が展開されました。統合運用への体制移行が今回の災害派遣で生かされたとことは評価できます。
この「災統合任務部隊」(統合部隊)は地震発生4日後の3月14日に編成され、陸自の東北方面総監を指揮官とし、その下に、航空総隊を基幹とする空自、自衛艦隊の一部を含む海自が参加するなど、3自衛隊の主要部隊が大規模震災災害派遣を担当しました。
原発事故、官邸や各省との連携に課題も残す
一方、東電福島第1原発の原子力災害派遣に対しては、陸自の中央即応集団を基幹とする部隊が対応しました。この中央即応集団は、大規模テロや特殊部隊からの攻撃などに対して機動的に対処する部隊であり、前大綱下で整備されました。放射能に汚染された地域の除染を行う部隊も含まれています。
しかし、3号炉の原子炉建屋爆発で給水作業中の隊員数人が負傷したこともあり、防衛省は「官邸、防衛省・自衛隊、関係省庁との間で情報共有が万全に行えたとは言えない状況」だったと総括しています。
(写真は、百里基地からの原発施設への災害派遣の模様)



