3月12日、厚生労働省は食品に含まれる放射性物質の新たな検査指針を決定しました。
今回の新基準の考え方と茨城県の対応についてまとめてみました。
新基準は数値を厳格化、分類は「5」から「4」に
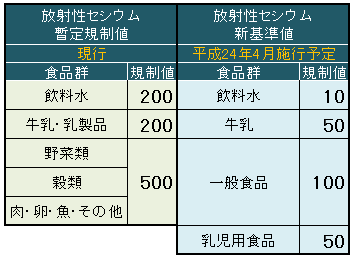 食品の区分が現行の5分類から、「一般食品」「牛乳」「乳児用食品」「飲料水」の4分類になり、数値は暫定規制値に比べてかなり厳しくなりました。
食品の区分が現行の5分類から、「一般食品」「牛乳」「乳児用食品」「飲料水」の4分類になり、数値は暫定規制値に比べてかなり厳しくなりました。
例えば一般食品の1キログラム当たり100ベクレルと新基準値は、欧州連合(EU)の規制値(1250ベクレル)や、食品の国際規格を策定する「コーデックス委員会」のガイドライン(1000ベクレル)の10分の1以下に設定されました。食品衛生法に基づき、基準値を超えた食品は出荷停止になります。
新基準の根拠となるセシウムの被ばく線量の許容上限値は、現行の暫定規制値では年間5ミリシーベルトでしたが、新基準値は年1ミリシーベルトです。厚生労働省は、コーデックス委員会のガイドラインを参考にしたと説明しています。
その上で、日本の基準は流通食品の汚染割合が国際基準より高いと想定し、高い基準を設定しました。コーデックス委員会は流通食品の1割がセシウムで汚染されていると想定していますが、日本は汚染の割合を5割としました。さらに、「牛乳」「乳児用食品」は子ども、乳児の感受性が高いことに加え、汚染割合を100%と設定し、より厳しい基準としています。
福島原発に近いか遠いかという地域差は考慮せずに、基準値は全国一律となっています。
文部科学省の放射線審議会は「汚染割合の設定が(高すぎて)現実的でない」などと修正を求めましたが、厚労省は「国民の安心確保のため、より安全側に配慮したい」と主張した経緯があります。
具体的な食品がどの分類に入るかを具体的に見てみたいと思います。
コーヒー牛乳や低脂肪乳など、加工された乳飲料は牛乳と同じ扱いです。牛乳から加工されるチーズ、ヨーグルト、乳酸菌飲料は一般食品の扱いです。
水は命にかかわるため、世界保健機関(WHO)のガイドラインが参考にされ、10ベクレルと特に厳しく設定されました。容器入り飲料茶やミネラルウオーターは、飲料水と同じ扱いです。ただし缶コーヒーや缶紅茶、缶ジュースは一般食品扱いです。
一方、家庭で飲む緑茶は湯で煎じた状態で10ベクレル以下なら、茶葉(4月以降収穫)が500ベクレルを超えても、基準値以下とみなされます。最終的に人間の口に入る状態でどの程度の放射性物質の量なのかが問題になります。
干しシイタケなど乾燥させた食品は、原材料の状態(乾燥前の生シイタケ)と、食べる状態(水で戻したもの)の両方で判断します。どちらかでも100ベクレルを超えたら流通できません。乾燥ワカメや乾燥野菜も同様です。
また、主食である米や牛肉、大豆などは経過措置が取られます。 米と牛肉は9月末まで、大豆は12月末まで、暫定規制値が適用されます。米と大豆は年1回の収穫であり、牛肉は冷凍保存で流通するので、すぐに新しい基準値を適用できないためとされています。摂取量が多い品目ですが、現行の暫定規制値でも安全性が確保されていると厚労省は考えています。
さて、こうした新基準値の導入で、茨城県が最も影響を受けるのは農林水産業の現場です。
茨城県漁政課によると、今年に入って検査をした75種類の魚類のうち、新基準の100ベクレルを超えた事例は、スズキ、ババガレイ、ヒラメ、ヤマメなど13魚種もありました。
全頭検査を実施している県産牛は、昨年8月からこれまで約1万2800頭を検査した結果、17頭で1キロ当たり100ベクレルを超える放射性セシウムが検出されています。
茨城県の漁業者、50ベクレルので出荷を自主規制
 3月14日、こうした状況を踏まえ、茨城県と茨城沿岸の漁協とは、4月以降の検査で、国の新たな基準値の半分にあたる50ベクレルを超えた魚の水揚げを自粛する独自の規制を導入することを決定しました。茨城沿岸の海域を北部、県央部、南部の3つに分けた上で、3月27日以降の県のサンプル検査で、1キログラムあたり50ベクレルを超える放射性物質が検出された魚があれば、その海域の同じ種類の魚の水揚げを自粛するというものです。また、同じサンプル検査で100ベクレルを超えた魚については、すべての海域で、出荷と販売を自粛します。
3月14日、こうした状況を踏まえ、茨城県と茨城沿岸の漁協とは、4月以降の検査で、国の新たな基準値の半分にあたる50ベクレルを超えた魚の水揚げを自粛する独自の規制を導入することを決定しました。茨城沿岸の海域を北部、県央部、南部の3つに分けた上で、3月27日以降の県のサンプル検査で、1キログラムあたり50ベクレルを超える放射性物質が検出された魚があれば、その海域の同じ種類の魚の水揚げを自粛するというものです。また、同じサンプル検査で100ベクレルを超えた魚については、すべての海域で、出荷と販売を自粛します。
県と漁協は、新たな基準の2分の1という厳しい水準を設けることで、茨城県産の魚の安全性を消費者にアピールしたい考えです。
自主規制を発表した漁連の小野勲会長は、「厳しい数値だが、安心で安全な物を消費者に送るのが使命。茨城の魚は安全だと胸を張って訴えられる」と、記者会見で語りました。
茨城沿海地区漁業協同組合連合会
海産魚介類における放射性物質の新基準値への対応について、昨日、下記のとおり県と沿海地区漁連で対応方針が決まりましたのでお知らせします。
1.方針
消費者が信頼・安心して本県の海産魚介類を購入できるよう4月以降市場に基準値(100Bq/㎏)超えの魚介類を流通させない体制を構築する。
2.4月に向けての対応方針
(1)100Bq/㎏を超過した魚種
・3月以降基準値を超えた魚種は県の自粛要請に基づき出荷・販売を自粛する。
・自粛区域は県内全域とする。
(2)50Bq/㎏超100Bq/㎏以下の魚種
・3月以降基準値を超える危険性のある魚種は自主的に生産を自粛する。
・自粛区域は、北部(日立市以北)・県央部(東海村~大洗町)・南部(鉾田市以南)の各海域ごととする。
(3)50Bq/㎏以下の場合
通常どおり出荷・販売をする。
(4)解除に向けた対応
検査期間:1ヶ月
検査回数:各海域毎に3カ所以上
解 除:各海域毎に解除
3.施行期日
(1)県での対応
・3月以降の検査結果を踏まえ100Bq/kgを超過した魚種について4月1日付けで出荷自粛を要請する。
(2)漁連・漁協での対応
・3月以降100Bq/kgを超過した魚種について出荷実務を考慮して3月27日から出荷を自粛する。
・3月以降50Bq/kg超100Bq/㎏以下の魚種について出荷実務を考慮して3月27日から海域毎に自主的に生産を自粛する。



