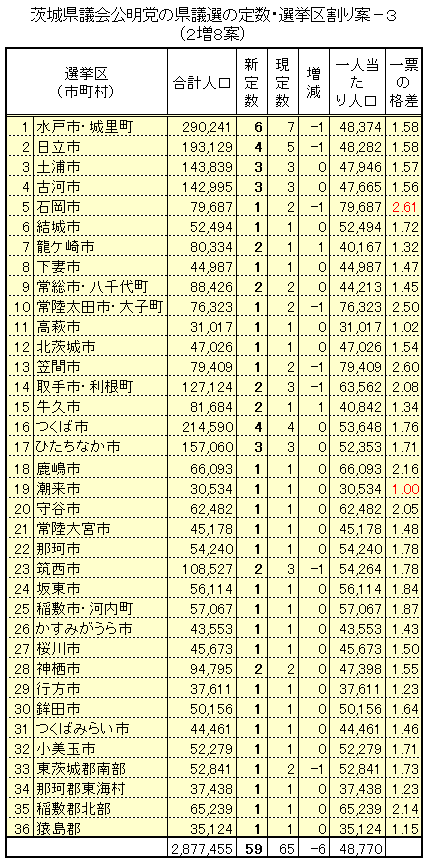5月28日、井手よしひろ県議ら県議会公明党は、県議会定数と選挙区割りの案に関して、記者会見を行ないました。
現在、茨城県議会では今年12月議会での決着を目指して、県議会議員の定数と選挙区割りの見直しを行っています。
現在の議員定数は65人です。次期の県議選の基礎となる人口である平成22年の国勢調査人口によると、議員1人当たりの人口は45,689人(平成17年国調時45,772人)になります。これは、全国でも11番目に多く、政令市のある都道府県を除きますと全国1位の人口となります。全国最少の鳥取県(16,819人)と比較いたしますと、約3倍の人口に相当します。
反面、市町村長や議会関係者からは、「市町村に比べて県議会の定数削減は進んでいない」との強い批判が寄せられています。一般県民からも、県の厳しい財政状況や県議会議員の活動の姿が見えづらいことを考えると、定数を見直すことが必要であるとの声が出ています。
こうした状況を踏まえ、次期の県議選の議員定数について、県議会改革検討会では、5月25日までに各会派の定数に関する意見を座長まで提出することを求めていました。
公明党としては、県議会の定数の意見照会に関して、以下のように回答しました。
1 現状の議員定数65人のままでよい。
◎ 2 減らした方がよい。
→その場合,議員定数は何人がよいと考えますか。
(1)64人
(2)63人
(3)62人
(4)61人
(5)60人
◎(6)59人以下(具体的な人数を記入願います。59人)
問Ⅱ 問Ⅰの設問で「2」に○をつけた理由・根拠について,具体的に記入願います。
- 各都道府県議会の現状を見ると茨城県の65の議員定数は適正なものと判断します。
- ただし、多額な県債残高をもつ茨城県が、行政改革の歩みを進める上で議会が強い意志を示す必要はあり、定数の削減という決断も重要だと判断します。
- さらに、情報化や交通網の整備により、一定の定数の削減を行なっても、県民の意思を県政に反映させることは可能です。
- 人口と議員定数との関連では、人口5万人あたり1人の議員が妥当ではないかと考えます。
- 県民ならびに有識者の意見を伺う中でも、50人台の定数を妥当と考える方のご意見が多いと認識しています。
- 公明党は、議員定数と選挙区割りは一体不可分である、という考え方から、定数59人に対する、選挙区割り案を3案提出いたします。
茨城県議会公明党が、定数案と同時に提出した選挙区割り案は、以下の視点で検討しました。
選挙区割りの基本的な考え方
- 抜本的な選挙区割りの変更を行うべきであり、恣意的な議席に増減は行わず、人口比によって定数を平等に割り振る。
- 道州制のへの議論などを踏まえ、市町村の枠のとらわれない、広域的なブロック制などを検討すべき。
- 可能な限り1人区は減らすべきである。
- 広域ブッロク制の導入には公職選挙法の改正が必要とる。現行法との兼ね合いで3案を提示する。
第1案は、衆院選の小選挙区を基準に、3市町村程度の広域ブロックを選挙区とする選挙区割り案です。一票の格差は最大1.42倍と2倍以内に収まり、1人区もなくなります。
しかし、現行の地方自治法の規定では、議員一人当たりの人口より人口が多い市町村を一つの選挙区にすること(任意合区)はできないため、実現には公選法の改正が必要となります。
例えば、茨城第5小選挙区ないの日立市・高萩市・北茨城市は、一つの選挙区として定数を現行の7から5に削減します。
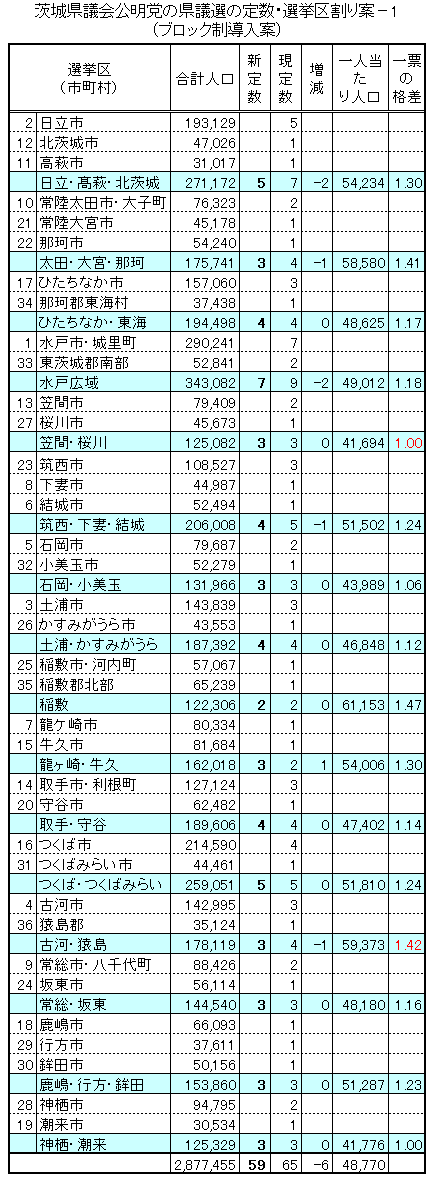
第2案は、公選法で任意合区が認められる議員一人当たりの人口より、市町村の人口が少ない市町村を最寄りの市町村と合区して、ブロックを形成する方式です。
具体的には、人口が31,017と議員一人当たりの人口を下回る高萩市は、最寄りの日立市に任意合区します。定数は5となり現行の6より1減とします。
この方式では、一票の格差は最大1.90倍となります。1人区も8選挙区残ります。
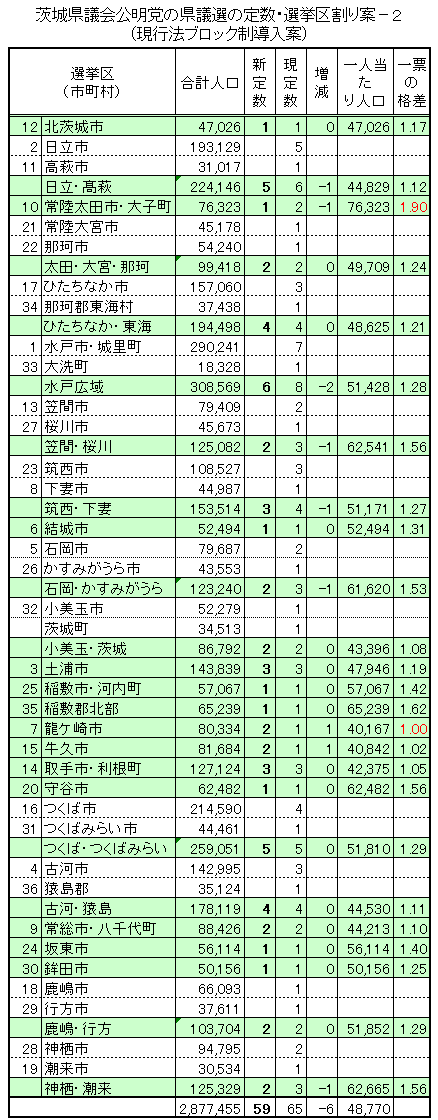
第3案は、現行の選挙区割りに定数59を、人口比例で機械的に配分しました。一票の格差は2.61倍となります。現行の3倍を超す状況よりは改善しますが、1人区は逆に24選挙区と増えてしまいます。