再挑戦できる「トランポリン型」安全網築け
長引く景気低迷などを背景に、生活保護の受給者が増え続けています。
厚生労働省によると、全国で生活保護を受けている人は今年2月時点で209万7401人。昨年7月から8カ月連続で最多を更新しています。
高齢者のほか、失業などを理由とした働き世代の受給者も増えており、生活保護費は今年度の3兆7000億円から2025年度には40%増の5兆2000億円へと増大する見通しです。
生活保護費に歯止めがかからない最大の要因は、受給者の医療費に相当し、生活保護費の約半分を占める「医療扶助」の急増です。医療扶助は全額公費で患者の窓口負担がないため、過剰受診を招きやすいとの指摘があります。また、受給者への過剰診療で診療報酬をかせぐ悪質な医療機関があることも看過できません。このため厚労省は、診療内容が適正かどうかを複数の医療機関で判断する対策を検討中です。
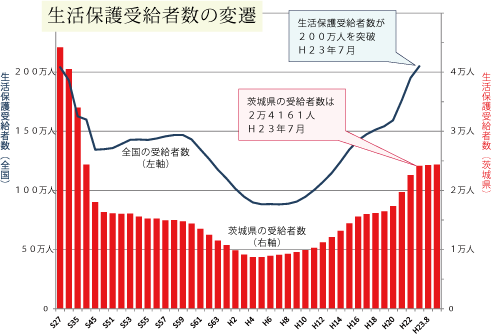
こうした中、漫才コンビの次長課長・河本準一さんの母親やキングコング・梶原雄太さんの母親の生活保護をめぐる問題が明らかになりました。いずれも高額の所得があるタレントの母親が生活保護を受けていたという問題で、たとえタレントといえど、プライバシーが白日の下に曝されていることに違和感を感ずるのは私一人ではないと思います。
これをキッカケに、小宮山洋子厚生労働相は親族が扶養できない場合、説明責任を義務付ける法改正を検討すると表明しました。自民党の一部には、生活保護費の一律カットを叫ぶ人たちもいます。
生活保護は、210万人が生活のよりどころにしている制度です。しっかりとした議論も成されない中出、芸人の例だけをもって制度改正にまで踏み込むのは、余りにも乱暴です。河本さんの母親は約15年前に、病気で働けなくなり保護を受給開始しました。その後、河本さんの収入が増え母親への援助額を増やしたため、生活保護費は減額されましたが、今年4月まで受給を続けていました。
確かに“親族の扶養義務”の問題は重要です。保護の申請があると、自治体は親子や兄弟姉妹などに年収や生活援助の可否を照会します。回答はあくまで自己申告です。核家族化が進み、複雑な事情を抱えたり、関係が疎遠になったりした家族が増えています。親子だからといって一律に扶養義務を果たせるとは限りません。むしろこうした事例の報が圧倒的に多いことを、政治家は知っているのでしょうか?にもかかわらず、小宮山厚労相の言うように機械的に説明責任を義務付けては、現場が混乱するだけです。
一番の問題は、自治体のマンパワーの不足です。自治体のケースワーカーを大幅に増員することを、政府は早急に着手する必要があります。
そして、受給者になると抜け出しにくい生活保護を「出やすい」制度にするため、自立を促す支援策を包括的に進めていかなければなりません。
例えば北海道釧路市では生活保護からの脱出策として、本人の同意の下にボランティア参加などを通して就労意欲を養う仕組みを「釧路方式」として導入し、効果を挙げています。こうした職業訓練の充実などを全国規模で力強く展開していくべきです。
きめ細かい相談支援で雇用へとつなげる努力も必要です。そのため、ケースワーカーの人員増に加え、NPO(民間非営利団体)などに協力を求めて民間のノウハウも大胆に取り込んでいきたいと思います。
生活保護家庭の子どもは進学率が低く、中退者も少なくありません。この「貧困の連鎖」を断ち切るため、就学援助などを拡充することも肝要です。
もう一つ、忘れてならないのが、生活保護を受ける状態になる手前で生活崩壊を食い止め、再挑戦できる「トランポリン型」安全網を年金・医療、雇用、住宅など各分野に構築することです。
公明党が「新しい福祉社会ビジョン」(2010年12月発表)の中で、低所得者への基礎年金25%加算や高額医療費の負担軽減、最低賃金引き上げ、生活困窮者向けの公営住宅確保などの具体策を提唱しているのも、このためです。
「まず生活保護費の抑制ありき」ではない、多角的な自立支援策の実施を急ぐべきです。



