支援の必要度、実態踏まえた判定に修正
難病患者もサービス対象に
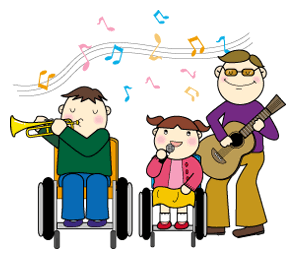 6月20日、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための障害者総合支援法(改正障害者自立支援法)が成立しました。
6月20日、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための障害者総合支援法(改正障害者自立支援法)が成立しました。
3党合意や民主党の分裂騒ぎの影で、マスコミ等にはほとんど報道されない障害者総合支援法の問題。この問題は、民主党のいわゆる『政治主導』がいかに脆弱で、無責任なものであったかを白日のもとに晒すことになりました。
公明党の主張が随所に反映された障害者総合支援法の改正の経緯とポイントについて、整理しておきたいと思います。
この法律のポイントは、障害者自立支援法の名称を「障害者総合支援法」に改め支援内容を充実させたほか、制度の“谷間”にあった難病患者を障がい福祉サービスの対象に加えました。さらに、これまで身体障がい者に限られていた「重度訪問介護」を、重度の知的障がい者、精神障がい者にも拡大しました。
これまでも公明党は、障害者自立支援法施行後、利用者や事業者から寄せられる声をもとに、利用者負担の大幅な軽減や事業者の激変緩和措置などのための特別対策、緊急措置を実施してきました。そして2010年12月には、ねじれ国会の中で、公明党が“接着剤”の役割を担い、民主、自民両党を説得して、家計の支払い能力に応じた応能負担を法律に明記するなどした改正障害者自立支援法(議員立法)を成立させました。
一方、民主党政権は、マニフェストに「『障害者自立支援法』を廃止して、障がい者福祉制度を抜本的に見直す」と掲げてきたことから、障害者自立支援法違憲訴訟の原告団・弁護団との間で、自立支援支援法を廃止して新たな総合的な福祉法制を実施するという基本合意文書を交わして和解しました。
しかしその後、突如、現行法に基本理念を盛り込み、法の名称や目的規定を変更することで対応する方針へと転換したのです。事実上、マニフェストの撤回です。このため同原告団・弁護団は「民主党政権は全てほごにした」と厳しく批判しています。この民主党の判断は、一にも二にも財源の確保の壁でした。和解の前提も、その財源確保の見通しも何もなく行ったことであり、「民主党も障害者側も、政権交代で『なんでもできる』というカン違いあった」とさえ言われています。また、廃止による自治体側の事務負担増大という大事な視点も全く考慮されていませんでした。
こうした中、公明党は障がい者団体と協議を重ね、「全く新しい制度をつくる必要があるのか」「これまで改善してきた自立支援法の完成形をめざしてほしい」などの意見を多くいただきました。そこで、これまで公明党が主張し、前回民主党の反対で盛り込まれなかった“宿題”を解決するため、障害者自立支援法の再改正を行うことに全力を上げました。
その結果、公明党の主張で「障害程度区分」の見直しや意思決定支援への配慮が盛り込まれました。
まず、支援の必要度を判定する「障害程度区分」の見直しです。現行制度では身体状況に重点を置いて障がい者を区分し、福祉サービスを決める参考にしていました。しかし、これでは外見から判断しにくい知的障がい者らの区分が低くなりやすく、障がい者団体などから見直しを求める声が挙がっていました。そこで、2014年4月1日を施行期日として障がい者の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」へと修正しました。併せて知的障がい、精神障がいなどの生活実態を踏まえたものにするよう、付則に配慮規定を追加しました。
また、意思決定支援への配慮が盛り込みました。重度の知的、精神障がい者であっても、必ず個人の意思は存在します。こうした観点から公明党は、障がい者に対する意思決定支援の明確化を主張しました。
今回の法律で多くの課題が解決に向け動き出しました。しかし、検討規定に盛り込まれたものもあり、まだ全て解決したわけではありません。また、今回対象に加えられた難病の範囲もまだ明確になっていません。難病の方たちへの支援は、障がい者福祉の分野だけでは解決できません。このため、公明党は総合的な難病対策を推進する「難病対策基本法」の制定や、障がい者の権利擁護のため「障害者差別禁止法」の制定を掲げています。共生社会構築に向けて、この二つの法律は不可欠です。



