絶対見逃せない健康被害の急増
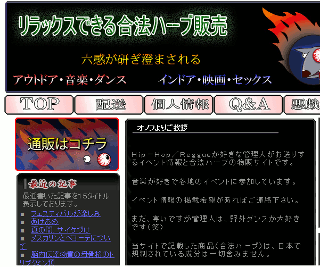 お香や芳香剤(アロマ)と称して販売されている「脱法ハーブ」を吸引し、幻覚症状などで救急搬送されたり、自動車事故を引き起こす事件が相次いでいます。
お香や芳香剤(アロマ)と称して販売されている「脱法ハーブ」を吸引し、幻覚症状などで救急搬送されたり、自動車事故を引き起こす事件が相次いでいます。
脱法ハーブは、幻覚や興奮作用のある薬物を植物片(ハーブ)に混ぜた脱法ドラッグの一種。厚生労働省は公明党が主導した2007年4月施行の改正薬事法によって、人体への作用を確認できた薬物から「指定薬物」に指定し、製造や輸入、販売を禁止しています。7月からは新たに9物質が加わり、77種類になります。
しかし、追加指定のたびに成分構造をわずかに変えた新種の薬物を含む脱法ハーブが出回り、法規制が追い付いていないのが実情です。
商品から禁止薬物が出た場合も、体内に摂取する薬物として販売しているなら薬事法違反になりますが、あくまでお香やアロマとして販売している限り、罪に問うのは難しいのが現実です。その上、吸引自体は罪にならないことも、若者を中心とした脱法ハーブのまん延につながっているといえます。
しかし、今年に入って脱法ハーブ吸引が原因とみられる死亡事故は全国で3件発生ており、東京都内では今年1~5月に脱法ハーブを吸って救急搬送を要請した人が99人に上ります。こうした健康被害の急増は断じて看過できません。
そればかりではありません。脱法ハーブを吸った男が車で商店街を暴走して2人に重軽傷を負わせた大阪市の事件など、第三者に被害を与える危険性からも、脱法ハーブの規制強化は急がねばなりません。
具体的には、(1)成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を導入する、(2)指定薬物が麻薬取締官による取り締まりの対象外であることを改め、疑いのある物品を発見した場合に収去ができる法整備を行う、などの対策を急ぐべきです。
薬物対策を推進してきた公明党の浜田昌良参院議員は、先月提出した質問主意書の中で、これらの具体策の必要性を指摘。政府は答弁書で(1)については法規制の実効性を高めるため導入を検討中とし、(2)については「可能な限り早く法案を国会に提出したい」と回答しています。政府の速やかな対応を強く求めるものです。
もう一つ、忘れてならないのが「薬物は絶対にダメ!」という強い意思を社会全体で共有することが肝心です。
今は薬物乱用防止の「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」期間(7月19日まで)。公明党議員が各地域で啓発活動を力強く後押ししていきたいと思います。
この脱法ハーブについて、井手よしひろ県議は、すでに2001年10月の県議会保健福祉委員会で、その存在に警鐘を鳴らし、県の対応求めていました。
当時の委員会記録には、「県としては,こういう事例をまず認識されているのかどうか。県内に被害者や,逆に言うと,そういう販売業者としてのいろいろな指導や取り締まりを行った事例があるのかどうか」担当部門の所見を求めている様子が残っています。行政の対応が後手後手に回っている現状があり、非常に残念です。



