 9月5日、茨城県議会公明党と公明党龍ヶ崎支部、利根支部、河内支部共催の健康セミナーを、龍ヶ崎市民文化センターで開催しました。
9月5日、茨城県議会公明党と公明党龍ヶ崎支部、利根支部、河内支部共催の健康セミナーを、龍ヶ崎市民文化センターで開催しました。
来賓として出席した中山一生龍ヶ崎市長は、「市民のいのちと健康を守るのは、地方自治体の一番大切な仕事。専門家である医師や様々な方の提案を真摯に受け止めて、福祉・医療行政の充実に努力していきたい」と挨拶しました。
このセミナーでは、龍ヶ崎済生会病院の副院長・海老原次男医師(茨城県医師会常任理事)を迎え、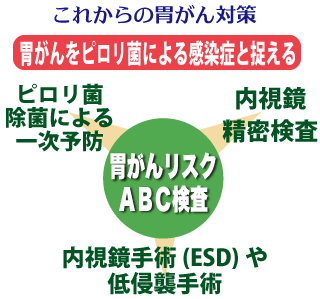 「胃の健康度チェックとABC検査について」と題して講演していただきました。海老原先生は、胃がんの主な原因であるピロリ菌検査と胃の萎縮を調べるペプシノゲン検査を組み合わせて、胃がんになりやすいリスク(危険度)を調べる“胃がんABCリスク検査”の有効性を強調。胃がんの対策は、従来のレントゲンとバリウムによる胃がん検診から、ピロリ菌の感染症と捉えてリスク検査を行い、1.ピロリ菌の除菌による一次予防、2.内視鏡による精密検査、3.内視鏡手術や低侵襲手術の三位一体の対策が必要になると訴えました。
「胃の健康度チェックとABC検査について」と題して講演していただきました。海老原先生は、胃がんの主な原因であるピロリ菌検査と胃の萎縮を調べるペプシノゲン検査を組み合わせて、胃がんになりやすいリスク(危険度)を調べる“胃がんABCリスク検査”の有効性を強調。胃がんの対策は、従来のレントゲンとバリウムによる胃がん検診から、ピロリ菌の感染症と捉えてリスク検査を行い、1.ピロリ菌の除菌による一次予防、2.内視鏡による精密検査、3.内視鏡手術や低侵襲手術の三位一体の対策が必要になると訴えました。
その上で海老原医師は、地方自治体における具体的な「胃の健康度チェック」制度の素案として、以下のポイントを提示しました。
- 市町村が実施する特定健診(メタボ健診)時に希望者にオプションとして“胃がんABCリスク検査”を実施する
- 40歳以上の5年毎の節目毎に検査を実施する
- ピロリ菌の除菌を行った者は対象外とする
- 住民負担は1000円以内とする
- 市町村は地元医師会の協力を得て厳密な精度管理を行う
- 結果はA:胃がんになりにくい、B:胃がんになりやすい、C:胃がんにとてもなりやすい、として受検者に郵送で伝える
- B群とC群の受検者には医療機関への受診を促し、保険診療として内視鏡検査を行う
- ピロリ菌保菌者には医療機関で除菌治療を促す
- 診察した医療機関はそれらの結果を市町村に報告する
- A群には5年後に“胃がんABCリスク検査”を、B群には3年毎に、C群には毎年の内視鏡検査受診を受けるよう、個別通知によって促す。医療機関は受診者の結果を市町村に報告する
- “胃がんABCリスク検査”、内視鏡検査を行う医療機関は、予め講習を受ける



