 9月7日に開会する茨城県議会第3回定例議会には、県立学校や県の施設の除染に関わる予算や原発事故に備える新たな体制整備に必要な予算が計上されます。
9月7日に開会する茨城県議会第3回定例議会には、県立学校や県の施設の除染に関わる予算や原発事故に備える新たな体制整備に必要な予算が計上されます。
県が行う除染に関する予算は5億460万円。除染の対象施設は、航空機によるモニタリングなどの結果、空間放射線量率が毎時0.23μSv以上の地域があり、汚染状況重点調査地域に指定されている北茨城、日立、ひたちなか、つくば、取手市など19市町村にある県の施設です。
市町村の除染実施計画に基づき高校などの教育施設、公園、県営住宅、保健所、職員住宅など40施設を選定されました。
また、県が管理する国道や県道の内、361キロを除染する計画です。
建物は壁面を高圧洗浄機で除染し、校庭や公園は表土や草木を除去し、側溝の汚泥を取り除きます。除去した土壌などは、原則的に敷地内に埋めるかビニールシートで覆って保管します。
道路は散水後にブラシで洗い、側溝を掃除、街路樹も伐採するとしています。しかし、洗浄した汚染水が側溝等に流れ込み、思わぬ高濃度の放射線量になる懸念も否定できず、処理方法が憂慮されています。
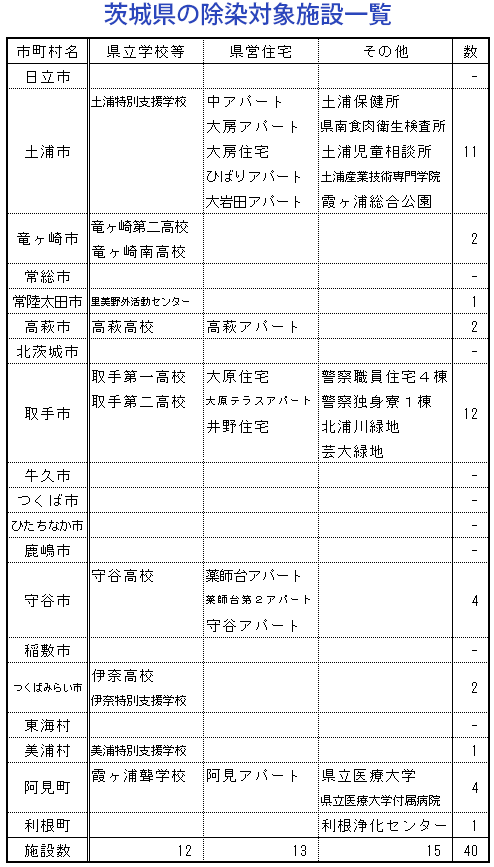
一方、国の原子力災害対策指針で、原発事故に備えて緊急の防護措置が必要な区域として、原発から30キロ圏のUPZが設定される見通しとなったことから、新たにUPZ区域に含まれる5つの市町に防災用の資機材を、2億円の予算で配備することになりました。
新たに資機材を配備するのは高萩市、常陸大宮市、笠間市と大子町、城里町。原発から10キロ圏の9市町村と同等の資機材(緊急連絡用のテレビ会議システムやIP電話、放射線測定器、線量計、防護服、防護マスク、医療活動に必要な資機材)を配備します。
原発事故で放出される放射性ヨウ素による内部被ばくを低減させるために、安定ヨウ素剤の購入に1300万円を予算化しました。



