 10月1日、井手よしひろ県議ら茨城県議会公明党議員会と東海村の議員団は、日本原子力発電東海第2発電所を訪れ、使用済燃料プールと乾式キャスク貯蔵施設を実際に視察しました。
10月1日、井手よしひろ県議ら茨城県議会公明党議員会と東海村の議員団は、日本原子力発電東海第2発電所を訪れ、使用済燃料プールと乾式キャスク貯蔵施設を実際に視察しました。
原子炉で使い終わった使用済核燃料は、放射能が強く、余熱も残っています。放射線を遮蔽し冷却すために、発電所の貯蔵プールのラックに入れて水中保管されています。また、東海第2発電所は、他の発電所に比べ燃料プールの容量が小さいため、発電所建屋外に使用済核燃料の貯蔵施設を設置しました。これが、2001年に完成した『乾式キャスク貯蔵施設』です。
その後、再処理のために、再処理工場に送られます。日本国内の再処理工場は青森県の六ヶ所村に計画されていますが、稼動が遅れ、現在、処理が行われていません。そのために、使用済核燃料を仮に40~60年間貯蔵する施設=中間貯蔵施設(リサイクル燃料貯蔵センター)が青森県むつ市に建設中です。
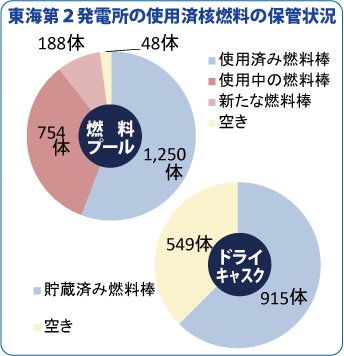 日本では使用済核燃料のリサイクル政策をとっていました。原子炉で発電に使用した後の使用済燃料には、まだ使えるウランや新たに生じたプルトニウムが含まれています。これらを再処理して再び燃料として利用する流れの輪を「原子燃料サイクル」と呼んでいます。しかし、夢の原子炉といわれた高速増殖炉『文殊』の開発は1990年代に放棄され、再処理工場の稼働も遅れているために、原発内に使用積燃料が溜まり続けています。すでに、東海第2発電所の燃料プールは97.9%が使用済みとなっています。ドライキャスクも62.5%が保管済みです。仮に再稼動させたといっても、わずか5~6年で使用済燃料の保管が出来なくなります。
日本では使用済核燃料のリサイクル政策をとっていました。原子炉で発電に使用した後の使用済燃料には、まだ使えるウランや新たに生じたプルトニウムが含まれています。これらを再処理して再び燃料として利用する流れの輪を「原子燃料サイクル」と呼んでいます。しかし、夢の原子炉といわれた高速増殖炉『文殊』の開発は1990年代に放棄され、再処理工場の稼働も遅れているために、原発内に使用積燃料が溜まり続けています。すでに、東海第2発電所の燃料プールは97.9%が使用済みとなっています。ドライキャスクも62.5%が保管済みです。仮に再稼動させたといっても、わずか5~6年で使用済燃料の保管が出来なくなります。
原発ゼロとは、言葉を換えれば「原子燃料サイクル」を放棄するということです。青森県では、県内の施設を原子燃料の最終処分場には絶対にしないとしています。ということは、各原子力発電所で使用した使用済原子燃料は、その原発に戻されてくるということです。「原発0(ゼロ)の日本社会をつくる」ためには、単に原子力発電所の運転を止めるだけでは、その目的を達成することは出来ません。使用済核燃料をどのように処理するかの結論も同時に得ることが必要です。



