 山中伸弥京大教授がノーベル賞を受賞し、iPS細胞研究とさい帯血バンクとの関係にスポットが当たっています。再生医療研究にあたっては、公明党がその推進を力強く支援してきました。「さい帯血バンク設立からiPS細胞研究支援に至る公明党の戦い」と題して、今までの経緯をまとめました。
山中伸弥京大教授がノーベル賞を受賞し、iPS細胞研究とさい帯血バンクとの関係にスポットが当たっています。再生医療研究にあたっては、公明党がその推進を力強く支援してきました。「さい帯血バンク設立からiPS細胞研究支援に至る公明党の戦い」と題して、今までの経緯をまとめました。
さい帯血と公明党の出会いは、15年前の1997年に遡ります。東京で開かれた「日本さい帯血バンク支援ボランティアの会」(有田美智世代表)第一回全国大会に浜四津敏子参議院議員(のちに代表代行)が出席しました。
その年(1997年)の夏、公明党は、浜四津敏子参議院議員を先頭に全議員が、党員・支持者の皆さん、有田美智世代表をはじめボランティアの会の皆さんとともに街頭に立って、さい帯血移植への保険適用と公的バンクの設立のための署名活動を行いました。署名は200万人を越え、地方議会から国への意見書も400を越えました。
 茨城県においても、井手県議ら公明茨城県本部では、公的な臍帯血バンクの早期設立を求める署名運動を展開。8月31日には、水戸駅北口において、女性議員を中心にした街頭署名活動も行いました。炎天下、短い時間でありましたが、500人を越える方々から、快く署名のご協力をいただくことができました。また、一般のボランティアからの署名協力の申し出でもあり、9月10日の締め切りまでに、19,876人の善意の署名が集まりました。
茨城県においても、井手県議ら公明茨城県本部では、公的な臍帯血バンクの早期設立を求める署名運動を展開。8月31日には、水戸駅北口において、女性議員を中心にした街頭署名活動も行いました。炎天下、短い時間でありましたが、500人を越える方々から、快く署名のご協力をいただくことができました。また、一般のボランティアからの署名協力の申し出でもあり、9月10日の締め切りまでに、19,876人の善意の署名が集まりました。
こうした大きな国民世論のうねりを受け、厚生労働省は翌1998年には異例の早さでさい帯血移植への保険適用を決定。また、その翌年の1999年には公的バンクが設立されました。
 わずか2年間でのスピード決着に対し、日本さい帯血バンク支援ボランティアの会の有田美智世代表は、「『大切な人命を救いたい』との思いで、私たちと一緒に、さい帯血移植の普及を推進してくださった公明党の皆さんには心から感謝しています」と語っています。(写真は土浦市内で講演する日本さい帯血バンク支援ボランティアの会の有田美智世代表:2004年5月)
わずか2年間でのスピード決着に対し、日本さい帯血バンク支援ボランティアの会の有田美智世代表は、「『大切な人命を救いたい』との思いで、私たちと一緒に、さい帯血移植の普及を推進してくださった公明党の皆さんには心から感謝しています」と語っています。(写真は土浦市内で講演する日本さい帯血バンク支援ボランティアの会の有田美智世代表:2004年5月)
この15年間、我が国のさい帯血移植件数は着実に増加し、現在では世界一となりました。しかし、今なお移植を希望する全ての患者が移植を受けられているわけではありません。毎年、約5000人の患者が移植を望んでいますが、その約5割から6割しか受けられていません。また、患者にとって移植した後の生活も大事ですが、その視点が今まで欠けていました。
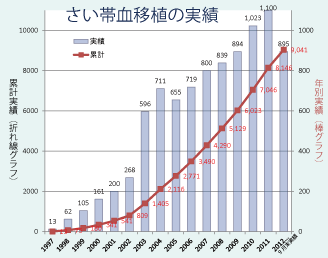 そこで、移植を希望する全ての患者が公平かつ安心して移植が受けられるようにするとともに、造血幹細胞移植には、さい帯血移植の他、骨髄移植、末梢血幹細胞移植がありますが、この三つの移植方法を一体的に推進することによって、患者自らが最適な移植方法を選べ、より良い治療を受けられるようにするために、公明党は「造血幹細胞移植推進法」を成立させました。
そこで、移植を希望する全ての患者が公平かつ安心して移植が受けられるようにするとともに、造血幹細胞移植には、さい帯血移植の他、骨髄移植、末梢血幹細胞移植がありますが、この三つの移植方法を一体的に推進することによって、患者自らが最適な移植方法を選べ、より良い治療を受けられるようにするために、公明党は「造血幹細胞移植推進法」を成立させました。
この法律が成立したことにより、関係者の方々からは喜びの声を沢山頂いています。NPO法人さい帯血国際患者支援の会の有田美智世理事長は「幸せな気持ちで成立を迎えることができた」と語り、骨髄移植に長年係わってこられたNPO法人血液情報広場つばさの橋本明子理事長は「これまで活動に際して政治家に頼るという発想はなかった。公明党の中に真の政治家の姿を見た」とまで語っています。
この法律が全会一致によって成立したことにより、平成25年度の概算要求において造血幹細胞移植に係わる予算が倍増しています。例えば、さい帯血移植など3つの移植方法の全てを実践する造血幹細胞移植拠点病院を整備します。また、移植後をフォローアップすることによって、患者さんが三つの移植方法から最適なものを選べるよう、情報提供する仕組みも整えます。法律制定によって、より多くの患者さんの命が救われるとともに、より良い治療が受けられる体制整備づくりがスピードアップすることとなったわけです。
また、この法律においては、「移植に適さないさい帯血を研究のために提供できる」という規定を盛り込みました。さい帯血は採取・保存して10年を越えると移植に適さないものとなります。また、ある一定数の細胞数がなければ移植には用いられません。移植に適さないさい帯血は、残念ながら廃棄処分となっていました。
ここに、ノーベル医学生理学賞を受賞された山中伸弥教授との大きな関わりが生まれました。廃棄されてしまうさい帯血に対して、「もったいない。患者のために使わせて欲しい!」と手を挙げてこられたのが、山中教授でした。
 山中教授は、さい帯血でiPS細胞を作って、iPS細胞ストックを作りたいと提案しています。iPS細胞を患者毎に作るとお金も時間もかかります。一人分のiPS細胞を作るには、1000万円以上、半年近い時間がかかるといわれています。しかし、事故で脊髄損傷になった場合、1ヶ月以内に治療しないと効果はありません。つまり、事故が起きてから患者の皮膚などからiPS細胞を作っていたら間に合わないのです。そこで、あらかじめさい帯血からiPS細胞を作ってストックをするという計画を、山中教授は進めています。
山中教授は、さい帯血でiPS細胞を作って、iPS細胞ストックを作りたいと提案しています。iPS細胞を患者毎に作るとお金も時間もかかります。一人分のiPS細胞を作るには、1000万円以上、半年近い時間がかかるといわれています。しかし、事故で脊髄損傷になった場合、1ヶ月以内に治療しないと効果はありません。つまり、事故が起きてから患者の皮膚などからiPS細胞を作っていたら間に合わないのです。そこで、あらかじめさい帯血からiPS細胞を作ってストックをするという計画を、山中教授は進めています。
ただ、他人の細胞を移植するには細胞の血液型であるHLA型が一致しなければなりません。山中教授によると、今、全国のさい帯血バンクに眠っているさい帯血の中から日本人に多いHLA型をいくつか選んで、それを培養すれば、効率的でかつ良質のiPS細胞ストックを作製することができます。
造血幹細胞移植推進法により、さい帯血を研究目的で利用することが法的に認められました。つまり、この法律により、山中教授のiPS細胞など再生医療研究のために、将来にわたって安定的にさい帯血が利用できることになったのです。山中教授は、今年10月18日の公明党再生医療PTの会合で、「造血幹細胞移植推進法の意義は大きい。法律成立にご尽力した公明党に心から感謝したい、本当にありがとうございました」と語りました。この言葉の背景には、こうした公明党の戦いがあったのです。
造血幹細胞移植推進法策定・成立まで1年あまり。この間、紆余曲折様々ありました。党内に2011年5月、法整備のためのプロジェクトチームを立ち上げた後、公明党案をとりまとめ、他党に早期成立を強力に働きかけました。与党である民主党議員に何度も説明に行きました。しかし、約2ヶ月間、棚晒しにされてしまいました。
「この法案成立をこれ以上遅らせてはならない」―そこで、6月12日、野党4党(公明党・自民党・共産党・新党改革)で参議院へ法案を提出しました。多くの患者がこの法律を待っている。なんとしても今国会で成立させたい。公明党は国会で「患者さんのために」との思いで野党4党での法案提出後も民主党をはじめ全党に粘り強く働きかけ続けました。
多くの患者支援団体の方々も全党へ「患者さんのためになる法律をなんとか多くの国会議員の賛同を得たい。全会派の賛同を得たい」と動いて下さいました。また関係学会の医師の方々も「患者のために」と心を合わせてご協力下さいました。そうした努力の甲斐あって、先の通常国会閉会直前(9月6日)に、衆参全会一致で可決・成立させることができました。まさに、滑り込みセーフの奇跡的な出来事でした。
公明党の15年にわたるさい帯血移植推進の地道な活動によって、白血病など多くの血液難病の患者さんの命が救われました。そして、今回の法律によって、更に患者のための造血幹細胞移植が格段に進んでいきます。また、山中教授がさい帯血を活用して良質のiPS細胞を作ることにより、血液難病のみならず様々な疾患の患者の命を救うことにもつながっていきます。
「1人でも多くの患者さんの命を救いたい」――これからも命を守る公明党は、造血幹細胞移植、再生医療研究支援に全力で取り組んでまいります。




夕方の忙しい時間と思いながらも、一気に読ませ頂きました。友人&知人を転送します
公明党の戦いに感動