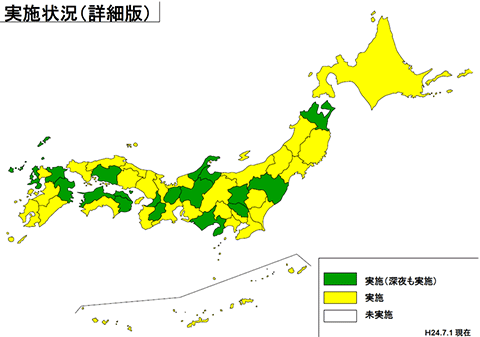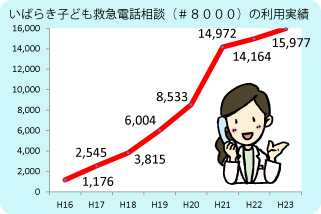 昨年8月31日付のブログ「茨城子ども救急電話相談の拡充を」でも指摘しましたが、茨城県のように小児科医が不足している地域では、電話による相談窓口の充実は喫緊の課題です。
昨年8月31日付のブログ「茨城子ども救急電話相談の拡充を」でも指摘しましたが、茨城県のように小児科医が不足している地域では、電話による相談窓口の充実は喫緊の課題です。
茨城県は子どもの急な病気やけがについて、夜間、電話で相談に応じる「茨城子ども救急電話相談」を2004年からスタートさせました。電話番号は短縮ダイヤル「#8000」。毎日午後6時半から11時半まで(休日は午前9時から午後5時まで)、県メディカルセンターの一室で10年以上のキャリアがある看護師2名が応対しています。
すぐ受診すべきか翌朝まで様子を見るべきかアドバイスをします。急を要すると判断すれば救急医療機関の紹介もしています。漠然とした不安を抱いた保護者にとって、力強い味方となっています。状況によっては、直接担当の医師に電話を転送することも出来ます。
茨城県では、平日・土曜日は18:30~23:30、日曜・祝日が9:00~17:00、18:30~23:30となっています。残念ながら夜中の相談体制はできていません。事業費は約2000万円、その内840万円が国庫補助となっています。
この#8000の事業は、厚労省の補助金を受けた全国展開の事業です。しかし、その運用、特に相談員は確保は各都道府県に任されており、受付時間などは全国まちまちの状態です。
具体的な状況は厚労省のHPを見ていただくほうが早いと思います。
 参考:「小児救急電話相談事業実施状況」
参考:「小児救急電話相談事業実施状況」
平日24時間体制で実施しているのは、青森、福島、群馬、埼玉、石川、岐阜、静岡、滋賀、大阪、奈良、広島、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、長崎、大分の18県にとどまっています。小児科が不足している地域が、24時間体制がとれていないという皮肉な結果になっています。
ちなみに、東京都の場合は、#8000は24時間体制ではありませんが、東京消防本部が行なっている#7119が24時間体制で救急搬送も含む相談体制を敷いているという特殊な状況があります。
#7119は東京消防庁の独自制度であり、全国レベルには至っていません。ここは24時間、すべての世代に対応してくれています。しかしその利用状況は救急要請において25%しか事前に利用していないことが東京都福祉保健局の資料でわかりました。まだまだ認知度は低いようです。もっと多くの方が#7119を利用すれば、救急車の出動回数も減少する。真に必要な方が利用するようになると考えられます。
こうした全国の状況を鑑み、以下の提案をさせていただきたいと思います。
- #8000の運用を全国単位に再編する。また、全国を幾つかのブロックに分割した広域体制に移行する。小児科医は、都市部に集中する傾向が強いために、電話相談を全国数カ所のデータセンターで受け付けるようにし、緊急の入院や救急対応が必要な場合、各都道府県に振り分ける形にする。
- 場合によっては、相談業務を民間の医療相談サービス事業者に委託することを検討する。
- 全国統一的な運用ができるように、小児救急医療相談の#8000の統一的運用と全世代の救急相談#7119に相当する制度の普及のために、地方自治体に人材と財源を国や都で拡充することが喫緊の課題です。