1ヶ月間の調査では、追加被ばく量の増加認められず
 つくば市では、市民の生活環境における放射線積算量(総量当量)を測定し、効果的な放射線対策を行うため、産業技術総合研究所(産総研)の協力を得て実証実験を行いました。
つくば市では、市民の生活環境における放射線積算量(総量当量)を測定し、効果的な放射線対策を行うため、産業技術総合研究所(産総研)の協力を得て実証実験を行いました。
3月4日、その結果がまとめられ1ケ月間測定した被験者全員が、期間中の追加被ばくがほとんどなかったことがわかりました。実験に使用した機器は、産総研の鈴木良一計測フロンティア研究部門副研究部門長らのグループが開発したものです。鈴木副部門長らは、これまで培かってきた放射線関連機器の小型化・省エネ化技術を応用して、デジタルカメラ等に使われるSDカードよりも小さく、20g以下の軽量な積算線量計を開発しました。この小型線量計は、3Vのボタン電池1個で1年以上動作します。測定・表示可能な被ばく量は、ガンマ線で0.1μSVです。測定記録されたデータは、パソコンなどと電気的に非接触の光通信アダプタを介して読み取り、1時間単位、1日単位などの被ばく量を知ることが出来ます。
つくば市では、昨年9月4日から1ケ月間先行試験を、10月21日から1ケ月間、本試験を実施しました。先行試験に47人、本試験に183人が参加しました。その230人被験者の被ばく量の平均値は0.61mSv/年となり、つくば市の平均的な自然放射線量(0.61mSv/年)を引いた追加被ばく量は0となりました。最大値でみてみると、0.87mSv/年となり、追加被ばく量は0.26mSv/年となりました。平常時の一般公衆の年間追加被ばく線量限度の1mSv/年を大きく下回わりました。
一方、実証実験の結果を検証するために、ガラスバッジ(非電子式積算線量計)も併用して測定を行いましたが、被験者全員が検出限界値以下(ND)となりました。
今回の実験を受け、職場や自宅通勤や余暇など、日常生活の中での追加線量がほとんどないという結果は、県民生活の安心の上から大きなプラスであると考えます。
尚、産総研では、この小型積算線量計を活用して福島県内の市町村住民の線量調査を行う予定です。
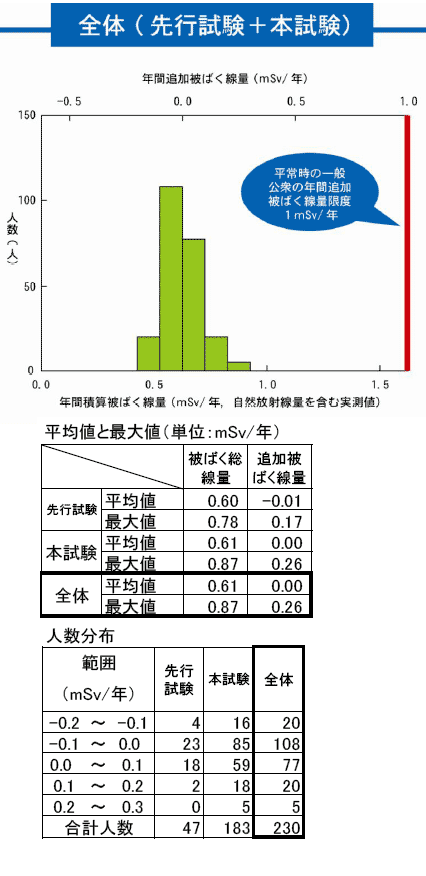
 参考:小型放射線積算線量計実証試験結果
参考:小型放射線積算線量計実証試験結果



