先月(2013年2月)21日から、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染による慢性胃炎を治療するため、胃の中のピロリ菌を取り除く「除菌」を行う場合も、健康保険が適用されるようになりました。
ピロリ菌は胃がんの大きな原因であり、胃がん予防にもつながると期待されています。今回の保険適用拡大に関する公明党の取り組みを公明新聞の記事などからまとめてみました。
わずか2年余のスピード実現
100万人超の署名、国会質疑などで/胃がん予防へ公明が対策リード
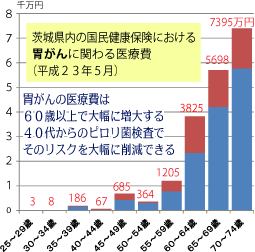 ピロリ菌の除菌は、これまで胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの病気に限って保険が適用されてきました。今回、それよりも症状の軽い胃のもたれや不快感などの慢性胃炎であっても、呼気検査などでピロリ菌の感染が確認され、内視鏡で慢性胃炎だと診断されれば、除菌に保険が適用されることになりました。具体的には、製薬企業12社が販売する抗生物質と胃酸を抑える薬への保険適用が認められたのです。
ピロリ菌の除菌は、これまで胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの病気に限って保険が適用されてきました。今回、それよりも症状の軽い胃のもたれや不快感などの慢性胃炎であっても、呼気検査などでピロリ菌の感染が確認され、内視鏡で慢性胃炎だと診断されれば、除菌に保険が適用されることになりました。具体的には、製薬企業12社が販売する抗生物質と胃酸を抑える薬への保険適用が認められたのです。
除菌は、それらの薬を組み合わせ、1週間ほど服用するだけです。除菌が成功すれば、再感染の可能性は極めて低いといわれています。胃炎の治療として除菌を行う場合、これまでは全額自己負担で1人当たり数万円掛かっていたが、保険適用によって窓口での支払いが3割負担の人は6000円程度で済むことになった。
日本では毎年約12万人が胃がんと診断され、約5万人が亡くなっています。胃がんは、がんによる死因では肺がんに次いで2位に位置しています。ピロリ菌を除菌すると、胃がんの発生を抑えることができるため、今回の保険適用拡大により、胃がんの原因そのものを取り除く胃がん予防が大きく前進すると期待されています。
公明党が胃がん対策に積極的に取り組み始めたきっかけは2010年12月、党がん対策推進本部(本部長=松あきら副代表)がピロリ菌研究の第一人者である浅香正博・北海道大学特任教授を講師に招いて行った勉強会でした。席上、浅香特任教授から「ピロリ菌の検診と除菌の強化を通じて胃がんは撲滅できる。公明党に頑張ってほしい!」との熱い期待を寄せられました。
そこで松副代表、秋野公造・同本部事務局長の両参院議員が質問主意書や国会質疑などを通じて、ピロリ菌対策を強く迫っていきました。また、公明党党九州方面、北海道本部が2012年春、ピロリ菌の除菌への保険適用拡大などを求める署名活動を行い、100万人を超える賛同の声が寄せられました。
そうした公明党の強力な取り組みにより、12年6月に策定された「がん対策推進基本計画」(12年度から16年度までの5カ年)の中にも当初記載されていなかった胃がん予防が国の方針として明確に位置付けられ、ピロリ菌除菌が胃がん予防に有用であることなども盛り込まれました。
そして今回の保険適用拡大へと至ったわけです。昨年12月の衆院選重点政策(マニフェスト)に掲げた「ピロリ菌の除菌を早期段階から保険適用とし早期治療を図る」との公約が早くも現実の“カタチ”となり、公明党が胃がん対策に動き出してわずか2年余りのスピード実現となりました。
厚労省が方針転換 公明党の粘り強い主張実る
公明党は、質問主意書や国会質疑を通じて政府を動かしてきました。
2011年2月、医学博士でもある秋野参院議員の質問主意書への答弁で政府は、ピロリ菌が胃がんの発生原因だと初めて認めました。それまで世界保健機関(WHO)の下部組織である国際がん研究機関(IARC)が胃がんの原因の一つはピロリ菌だと結論付けていたにもかかわらず、日本政府はかたくなに拒否し続けていたのです。つまり、この質問主意書こそ、厚労省が胃がん対策を方針転換する契機となった画期的なものでした。
2011年3月、松副代表が参院予算委員会で、吐き出した呼気によってピロリ菌検査を行う尿素呼気試験の機器を持ち出し、検査の手軽さをアピールしながら、胃がん検診にピロリ菌検査を追加するよう、政府に迫りました。その様子について、上村直実・国立国際医療研究センター理事・国府台病院院長は「あれはインパクトがあった」と述べているように、首相からは「厚労省に対して積極的に取り組むよう指示したい」と前向きな答弁を引き出しています。
さらに秋野参院議員は同年12月、海外の知見を紹介してピロリ菌検査の実施と保険適用の前提となる除菌の薬事承認について検討を迫り、厚労省から「12年度にがん検診の在り方に関する検討会を設置する」「効率的な除菌の治験環境が整っていることを踏まえ適切な審査をする」との具体的な答弁を引き出しました。
こうした粘り強い公明党の主張が政府を動かし、ついに保険適用の拡大を実現させたのです。
今後の課題は、『ピロリ菌ABCリスク検査』への公費助成
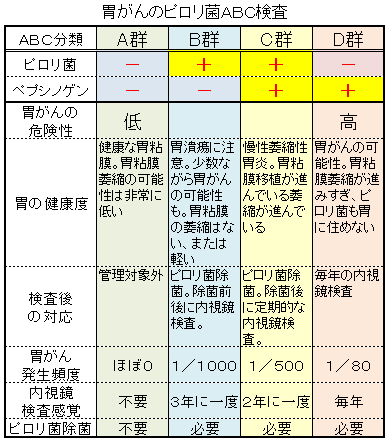
一方、ピロリ菌の感染の有無を胃がん予防に活用することも重要です。
ピロリ菌に感染している人が必ずしもみな胃がんになるわけではありません。そこでほかの検査で補って、正確に胃がんになるリスクを予測しようという取り組みが進んでいましす。
胃がんリスクを調べる手段に胃の粘膜が「前がん状態」ともいえる慢性胃炎の萎縮(いしゅく)性胃炎になっているかどうかの検査があります。これにピロリ菌の有無の検査を組みあわせた「ピロリ菌ABCリスク検査」を、浅香教授や三木一正東邦大学名誉教授らが提唱しています。
胃の粘膜が萎縮していると、ペプシノゲン(PG)という酵素の分泌量が減ります。PGの分泌量が多いかどうかは血液中に漏れ出るPGの量を測ってわかるため、ピロリ菌の有無と組みあわせてリスク群を分けるという検査法です。
ピロリ菌の感染がなく、胃粘膜の萎縮がないA群は自覚症状がなければ内視鏡検査は不要です。ピロリ菌がいて胃粘膜が萎縮しているC群は2年に1度、内視鏡検査の必要となります。
井手よしひろ県議は、昨年、直接三木先生にもお会いしました。三木先生は「リスク検診は、いま胃がん検診で推奨されているX線検査より手間がかからず、検査を受ける人の身体的、金銭的な負担も軽い。そのために検診率を一挙に上げることもできる。検査による放射線の被曝もない。ピロリ菌の有無と胃の萎縮状況を知ることで、検診を受けた人は、自分が将来胃がんに気をつけなければいけないのかどうか、その意識付もできる。なぜ、良い事ずくめのABCリスク検査を国が認めないのか不思議なくらいだ。」と、熱く語っていらっしゃいました。
このABCリスク検査を、群馬県の高崎市医師会では5年前から採用しています。東京都目黒区など、いくつかの自治体や事業所で取り組みが始まっています。
茨城県内でも井手県議ら公明党の働きかけによって、牛久市や水戸市でもABCリスク検査が導入されています。(牛久市では平成25年度より導入予定)
国は、このABCリスク検査が胃がんの有無を直接検査する方法ではないために、胃がん検診のメニューとしては認めていません。しかし、レントゲン・バリューム検診より患者負担が少なく、予防効果も高いABCリスク検査を胃がん検診として認めること、公費助成を国レベルで認めること、次のステップとなっています。
ピロリ菌とは
1980年代に発見された細菌で、胃の粘膜に炎症などを引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんなどの原因となります。胃酸の分泌が不十分な子どものころに生水を飲むなどして感染した人が多いとされ、その後、成人になっても胃の粘膜にとどまり続けます。そのため、日本人の50歳以上の45%程度が感染しているといわれる一方、上下水道が完備した時代に育った若年世代の感染は激減しています。現在、日本人のピロリ菌感染者数は3500万人以上といわれています。
『前例のないことで驚き。胃がんの“芽”を摘むチャンス広げる』
国立国際医療研究センター理事・国府台病院長・上村直実氏のことば
今回の保険適用拡大は、松あきらさんと秋野公造氏の2人のおかげで実現したと言って過言ではない。むしろ、保険適用について報じた主要紙の記事に2人の名前が見当たらないことが不思議であった。率直に言って2人に感謝して然るべきだと思う。また、公明党員による100万人を超える署名活動も大きな力になったと聞いている。
胃がんの90%以上はピロリ菌の感染による胃炎が原因で、ピロリ菌を除菌すれば、胃がんの発生を抑制することが可能である――これは既に1990年代から2000年代初頭にかけての研究結果から、医学的には世界の常識になっている。
ところが、実際に患者を治療する医療の現場ではこれまで、その医学界の常識がなかなか受け入れられずにいた。背景として、日本のピロリ菌感染者は3500万人以上ともいわれ、対策に掛かる財源が莫大になることなどの課題があったものと推測される。
そうした医学と医療の間に横たわっていた不一致が見事に解消された。私の専門領域では前例のないことで驚いている。松、秋野両氏が真摯に取り組んでくれたことがうれしい。
胃がんは早期発見することで治癒する病気だ。国府台病院がある千葉県市川市でも13年度から実施される予定だが、採血による血液検査により、胃の中のピロリ菌の有無と胃の粘膜の萎縮を調べ、胃がんの発症リスク(危険)の度合いに応じてA・B・Cなどと分類・判定する検診方法を導入する自治体が広がっている。
そうした流れの中で、今回の保険適用拡大は、胃がんの“芽”を摘む早期発見のチャンスを広げてくれるものだ。胃がん予防が前進し、将来的に胃がんで亡くなる人が間違いなく減ると思われる。
さらに、「慢性胃炎」はこれまで定義が曖昧な病気だった。そのうちピロリ菌感染による慢性胃炎の治療方法が「除菌」と明確になったことで、その他の原因による慢性胃炎の治療方法も今後、定まってくると思われる。これは、医療の現場ではエポックメーキング(画期的)なことでもある。
現状の課題として、ピロリ菌の感染診断や除菌治療の副作用、除菌の判定方法などを熟知している医師が少ないので、早急に体制を整えないといけないと思っている。
ともあれ、胃がんの早期発見・治療に向けた公明党の今後の取り組みにさらに期待したい。
うえむら・なおみ 1951年、福岡県生まれ。広島大学医学部卒。専門は消化器病学、特にピロリ菌と胃がんの研究。同大学病院、呉共済病院、国立国際医療研究センター病院などを経て現職。日本ヘリコバクター学会副理事長、日本消化器病学会理事、日本消化器内視鏡学会理事などを兼務。



