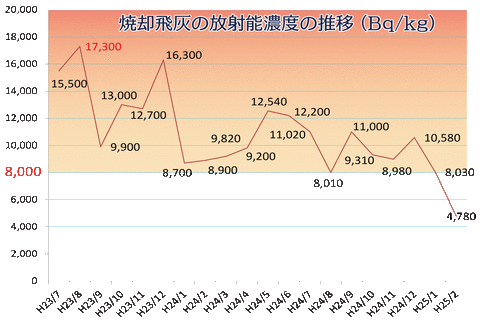7月9日、井手よしひろ県議は舘野清道日立市議と共に、日立市の指定廃棄物の一時保管場所を現地調査しました。
7月9日、井手よしひろ県議は舘野清道日立市議と共に、日立市の指定廃棄物の一時保管場所を現地調査しました。
東日本大震災による福島第一原発事故で発生した放射性物質を8,000ベクレル/kg以上含む廃棄物は、国から「指定廃棄物」に指定され、発生した市町村で一時保管されています。日立市には1,260トンの指定廃棄物があり、フレコンバックに入れられて頑丈な鉄筋コンクリートの施設内に保管されています。
日立市の場合、市の清掃センターで一般焼却された際に発生した焼却灰に放射性物資が含まれ、平成23年の8月には平均で17,300ベクレル/kgまで濃度が上昇しました。その後は上昇と下降を繰り返し、全体的には低減傾向を示していました。今年1月に8,030ベクレル/kgと基準値である8,000ベクレル/kgをほぼ並び、2月には4,780ベクレル/kgまで低下しました。その後、基準を超える飛灰はありません。
井手県議らの聴き取りによると、施設の外の空間線量は、0.14マイクロシーベルト/hと日立市内の一般の空間線量とほぼ変わりありませんでした。
茨城県内には3,212トンの指定廃棄物が一時保管されています。約13年程度(2024年頃)には0.6トン程度に減衰するとの試算もあり、各県一箇所と最終処分場をつくるとの国の方針の見直しも議論になっています。次回開催される市町村長会議の中で議論されることになっています。
なお、実際に廃棄物が保管されている施設内も調査しましたが、保安上の配慮から、写真等の公開は差し控えさせていただきます。