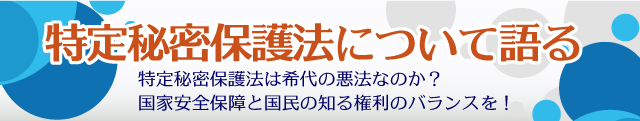
一部のマスコミ報道には、国民に誤解を与えているものがある
 11月26日に衆院を通過した「特定秘密保護法案」について、一部のマスコミ報道には、国民に誤解を与えているものがあります。
11月26日に衆院を通過した「特定秘密保護法案」について、一部のマスコミ報道には、国民に誤解を与えているものがあります。
この採決は、「強行」ではありません。なぜなら、野党であるみんなの党からも賛成を得ており、日本維新の会も採決を退席したものの、可決された修正案の共同提案者に名を連ねています。与党だけで一方的に可決したわけではないのです。これを「数の横暴」と呼ぶ人がいますが、まったく的外れです。
また、衆議院の委員会での質疑時間も44時間に達しており、慎重審議に値する時間を取ったと言えます。野党やマスコミの一部は、時間不足だとか「なぜ今なのか」と言いますが、議事録を見れば、野党議員が同じ質問を繰り返していることが一目瞭然です。
今回の法案を「現代の治安維持法」などと呼ぶ批判があります。しかし、何の根拠もありません。この法律の目的は、治安維持ではなく、国民の安全や国益を守るための情報が漏えいしないようにすることです。そもそも、守るべき情報が国家にある、という点については、与野党で共通の認識を持っています。
個人でも、クレジットカードの暗証番号は人に教えられない秘密ですし、家庭でも会社でも公開できない秘密は必ず存在します。国家にも当然あります。特定秘密として想定されている数が、42万と報道されていますが、そのうち9割は情報衛星の写真なのです。これは意外と知られていません。
国家の情報は国民のものであり、原則公開されるべきだ、という意見に私は賛成です。憲法で保障された「国民の知る権利」は尊重されるべきです。ただし、公開することで国益が損じられ、結果として国民生活に重大な影響を及ぼす情報については、それを特定し、一定期間秘密にする必要はあります。
秘密に特定する情報は、なるべく限定的にすべきです。今回の法案では大臣や官僚が法律を恣意的に拡大解釈することを明確に禁じています。「法の適用に当たっては、これを拡張して解釈してはならず、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない」(第21条)これは、公明党の修正案が反映されたものです。
この条文に対して「法律で拡大解釈が禁じられていても、政府が勝手に秘密を作ることをチェックできない」という反論があります。しかし、政権交代が起こった場合、前政権の大臣が恣意的に特定秘密を作っていたことは、すぐ判明してしまいます。その危険を冒してまで、違法な特定秘密を作ることは、非現実的だと言えます。
公明党の主張により設置が決まった「有識者会議」も重要です。「何を特定秘密にするか」という基準は、政府の外から専門家が入るこの会議で定期的にチェックされます。外部の専門家の関与があるので、政府は自由に特定秘密を作ることはできません。
さらに、与野党修正で、政府は毎年、有識者会議の意見を付して、特定秘密の指定・解除や適正評価の実施状況について国会に報告し、公表することになりました。ということは、毎年、この内容は新聞等に報道される事になります。秘密の具体的中身は出せないが、秘密の数の増減や適正であったかについては、毎年公開されます。
もうひとつの批判論点として、メディアの「国に対する取材が委縮する」というものがあります。国の特定秘密を取材したら懲役刑などの重罰があるので、委縮するという主張です。
しかし、今までの通りの普通の取材活動で特定秘密を仮に入手しても、それを漏えいした公務員は罰せられますが、入手した側は罰せられません。「人を欺き、人に暴行を加え、もしくは人を脅迫する行為により、または財物の窃取もしくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為」(第23条)などの違法な方法により特定秘密を入手した場合に、罰せられることになっていますが、それ以外の通常の取材での入手は問題ありません。
国会議員すら特定秘密にアクセスできない、という批判もありましたが、これも与野党修正で改善されています。国会に特定秘密情報に関する委員会や組織を作り、漏えい防止対策をした上で、必要があれば、米国議会のように秘密会形式で国会議員が特定秘密情報の提供を受けることができるような方向になりました。「政府は信用できない。法律の拡大解釈を必ずやり、運用で国民の権利を侵す」という意見を持つのは自由です。しかし、私たちは、そういうことがないように、全力を尽くします。
14年前に国会で大騒ぎになった「通信傍受法」は、当時「盗聴法」と呼ばれ、マスコミの強烈な批判にさらされました。通信傍受法が可決された当時のマスコミ論調には、「これで国が勝手に国民の会話を盗聴できる道を開いた。戦前回帰だ。」というものまでありました。あれから、14年たちました。通信傍受は薬物犯罪組織の幹部などに対し、毎年行われています。今、これを「戦前回帰」と書くマスコミはありません。
通信傍受法に基づく犯罪組織に対する通信傍受は、毎年数十件行われ、その結果逮捕に結びつく成果も挙げています。一般国民の会話を盗聴した例は、私の知る限りありません。いずれにせよ、基本的人権の尊重は日本国憲法の大原則であり、それを侵す法律を作ろうという人は、今の政権与党にはいません。
戦後68年。日本は成熟した民主主義国家になりました。戦前の統制国家の背景には、隣組があり、憲兵がおり、特高警察があり、そのネットワークの中で、国民の相互監視と軍部独裁による人権抑圧システムが形成されました。現代の日本は、その当時とまったく環境が違います。「戦前回帰」や「現代の治安維持法」との批判には、かなりの無理があると言わざるを得ません。
とはいえ、「権力は、必ず腐敗する」という至言があります。国会議員はこの言葉を常に忘れず、肝に銘ずる必要があると思います。常に自戒の念を持ちつつも、国民の生命と財産、自由と人権を守るための政策を考え、実行していく姿勢を堅持していかなければなりません。
特定秘密法案の審議は、その舞台を参議院に移しました。衆議院の審議でも、足らざる論点があるならば、参議院で大いにやってもらいたいと思います。衆議院での審議と重複しない、重厚な質疑を期待しています。批判は大いに結構だと思います。批判や疑問を受けて、政府は真正面から答え、さらに良い法律にしてゆくことが大切です。
私も皆様からの批判や疑問に対して、これからも現場で、丁寧な説明を尽くしていきます。



