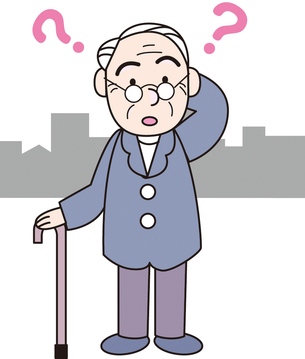 3月1日、最高裁は認知症の91歳の男性が徘徊中、JR東海の列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JRの損害賠償請求を認めない判決を下だしました。
3月1日、最高裁は認知症の91歳の男性が徘徊中、JR東海の列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JRの損害賠償請求を認めない判決を下だしました。
平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で、男性が電車にはねられて死亡しました。JRは振り替え輸送にかかった費用などの賠償を求める民事裁判を提起しました。男性は妻が6~7分ほどうたた寝をしている間に、自宅をぬけ出し、線路内に入りました。1審はJRの請求を認め、男性の妻と長男に合計720万円の賠償を命じました。2審も妻の責任を認め360万円の支払いを命ずる判決を下しました。
1日の判決で、最高裁判所第3小法延の岡部喜代子裁判長は、認知症の人や精神的な障害がある人の家族などが負う監督義務について「同居しているかどうかや介護の実態、それに財産の管理など日常的な関わりがどの程度かといった生活の状況などを総合的に考慮するべきだ」という画期的な判断を示しました。そのうえで、「このケースでは妻も高齢者で介護が必要なうえ、長男仕事のために離れて暮らしていたことなどから認知症の男性を監督義務や賠償することが可能な状況ではなかった」と指摘し、家族の監督責任を認めない判決を言い渡しました。
この判決は、認知症の人の家族などが無条件に損害賠償責任を負うのではなく介護者の生活や心身状況、認知疾患者の問題行動の有無、介護の実態などを総合的に判断すべきとしたものです。
一方、どんな義務を怠った場合に、賠償責任が問われるのかには、一切触れませんでした。認知疾患者が他人を傷付けたり、交通事故を起こしたりした場合、賠償責任を誰が果たすのかという課題が残りました。
厚生労働省の推計では、65歳以上の7人に1人が認知症で、2025年には5人に1人に増えるとされています。家族が認知症になって事故を起こすことは、誰も人ごとではいられません。
行政と地域が協力して認知疾患と家族をサポートする体制を作る必要があります。公明党が強く推進する地域で医療、介護、生活支援サービスを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の早期構築が望まれます。
認知症の行方不明者が出た時、登録者にメールで情報発信して早期発見・保護につなげるなど、先進自治体の取り組みも参考になります。
そして何よりも地域コミュニティーの再生を図るべきです。徘徊など問題行動を起こす高齢者や障がい者に対して、地域住民が声をかけ、見守る体制を使ることが重要です。政府は認知症対策の国家戦略を着実に実行に移すととも、地方自治体は、一人ひとりの高齢者、障害者を見守るしくみづくりに全力を上げるべきです。



