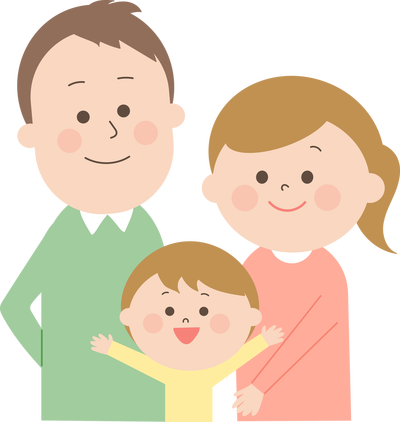 予期せぬ妊娠などで実の親が育てられない子どもを、実のつながりがない親が育てる制度を「特別養子縁組」制度といいます。6歳未満の子どもを実親とは異なる戸籍で、安定した家庭で育てる仕組みを強化する必要があります。
予期せぬ妊娠などで実の親が育てられない子どもを、実のつながりがない親が育てる制度を「特別養子縁組」制度といいます。6歳未満の子どもを実親とは異なる戸籍で、安定した家庭で育てる仕組みを強化する必要があります。
今国会では、民間事業者が適切に養子縁組をあっせんできるようにするための法律が審議されており、参議院を全会一致で通過し、本日(12月7日)衆議院の厚労委員会で全会一致で可決されました。これまで法的基盤が弱かった民間事業者の養子縁組を促進するための画期的な法整備です。大いに評価したいと思います。
日本には、一般的に養護施設で暮らし、家庭養護は1割程度に過ぎません。特別養子縁組は増加傾向にあるものの成立件数は年に500件程度です。イギリスなどと比べると、日本は人口は2倍程度あるにもかかわらず、成立件数は10分の1にすぎません。
欧米など世界が「施設から家庭」の流れにある中で、なぜ日本で養子縁組制度が進まないのか。その要因の一つとして、児童相談所の養子縁組の談相談・支援体制が十分でないことがあげられます。
このため、民間のあっせん事業者の役割が増加しています。届け出をした全国22事業者を中心に、縁組成立件数は5年で約6倍に増えています。少し古い数字ですが、2012年の全成立件数339件のうち116件にのぼり、実に成立件数の3分の1は民間事業者のものでした。
一方で、安易なあっせんによるトラブルも懸念されます。適正な民間事業者の取組みを後押しし、悪質な事業者を排除するための法制度が求められて来ました。
現在審議中の法律は民間のあっせん事業を届け出制から都道府県の許可制に変更するものです。また、許可事業者が健全な業務を行えるよう、国や地方自治体による「財政上の措置等」が明記されました。
子どもの最善の利益のため活動する民間事業者を応援するもので、時宜にかなったものです。
特別養子縁組を進める“愛知方式”の普及を
特別養子縁組制度の具体的な運用について、全国的にも注目を集めているのが“愛知方式”です。
2014年度中に発生、発覚した虐待死事例は44件。このうち0歳児が6割を超える27件、うち15人は生後24時間以内に死亡していました。この15人のうち14人は予期しない妊娠で産まれた子どもでした。
レイプなど望まない性交で妊娠した人や、経済的な理由などで産んでも育てられない妊婦の中には、誰にも相談できず、結果的に孤立し、最悪のケースに至ってしまう人もいます。
子どもの命を助けるために、特別養子縁組を前提とした新生児里親委託(赤ちゃん縁組)制度の導入が必要です。
一般的な養子縁組みと、特別養子縁組みとは仕組みが大きく異なります。普通の養子縁組は、当事者間の契約で決まります。それに対し、特別養子縁組は家庭裁判所の「審判」で決まります。産みの親が何らかの事情で育てられない「要保護児童」に恒久的な家庭を与えることが目的です。子どもは養親の実子として扱われ、実の親との法律上の親子関係は消滅します。養親側はどちらかが25歳以上の夫婦であることが求められ、原則として親子関係の解消(離縁)は認められません。
この特別養子縁組を前提として、新生児里親委託の仕組みを、愛知県の産婦人科医会や児童相談所、NPOなどが作り上げられてきたことから、“愛知方式” と呼ばれています。
愛知県産婦人科医会は、1976年から1999年まで「赤ちゃん縁組無料相談」を行っていました。愛知県内の児童相談所の児童福祉国が、産婦人科医会の取組みに、子どもの人権を守る視点、子どもを迎える夫婦の視点なども加えて、児相業務の中に、新生児を里親に委託する仕組みを加えました。
子どもを迎える夫婦には、①おおむね40歳まで、②子どもの性別などは一切不問、③子どもに障害がある可能性を受容し、自分たちの出産と同じ覚悟で臨む、④適当な時期に、自分たちが産みの実子でないことを告知する(真実告知)、⑤子どもが成長して、出自を知りたいという希望があれば、親として協力する、などの厳しい条件が課せられます。
この取組みは1982年にスタートしましたが、現在は名古屋市も含めて、愛知県の12か所の児童相談所の全てで、一般的なケースワークとして実施されています。
子どもが育つ上で大切なのは、子どもの側に「この人の胸に抱かれていれは安心だ」という愛情の絆で強く結ばれていることです。最近の脳科学の研究では、生後3か月までにこの絆を結ぶことが重要と指摘されています。現場の専門家は、「生後すぐから里親の元で育った子どもに比べ、数か月以上たってから里親に引き取られた子どもは、試し行動や赤ちゃん返り、愛着障害があったり、不幸な姿が見られます。また愛着関係は、特定の保護者による継続な世話によって形成されますが、職員が交代で世話をする養護施設では、愛着関係は結ばれにくい」と語っています。
国もこの愛知方式を評価し、2011年3月に出された厚生労働省の里親委託ガイドラインでは、愛知県の取り組みが参考資料として紹介されました。2011年7月の厚労省通知では、匿名での妊娠相談でも対応するよう促し、妊娠中からの相談も含め、特別養子縁組を前提とした里親委託が有用だとしています。
2016年5月には改正児童福祉法により、児童相談所の業務に、里親の支援や養子縁組の利用促進に向けた相談などが明文化されました。
茨城県でも愛知方式を学び、子どもの幸福を増大させる養子縁組の取り組みを行うことが強く望まれます。



