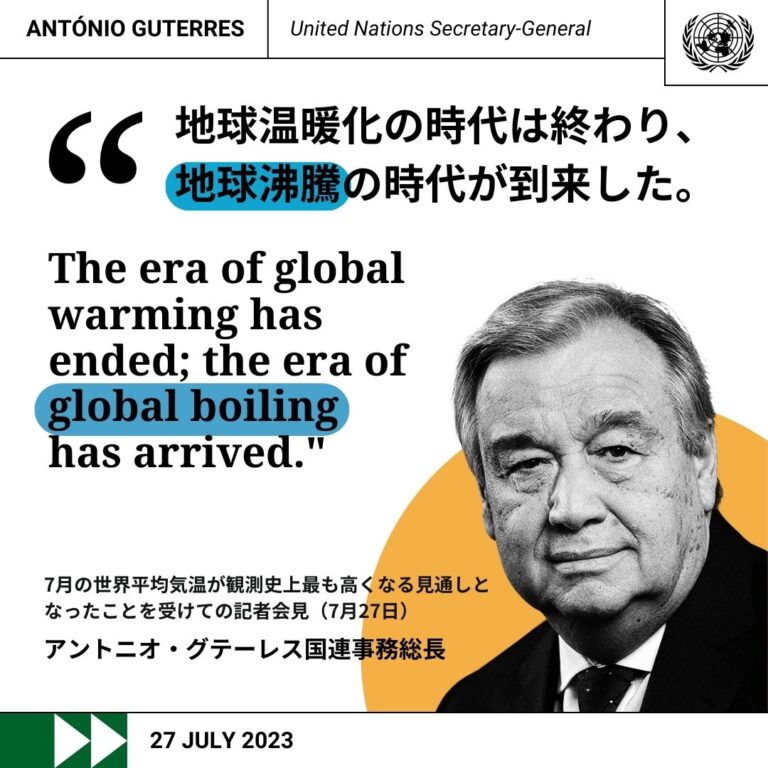3月15日、井手よしひろ県議ら茨城県議会公明党議員会は、大井川和彦知事に対して、「茨城県におけるSDGsへの取り組みに関する提案書」を提出しました。
公明党の岡本三成外務政務官にも、同席していただき、SDGsが世界共通の物差しとなり「誰も置き去りにしない社会」構築への動きが起こっていることを強調していただきました。
このブログでは、その内容をご紹介します。
「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」は、2015年9月に国連で採択されました。開発途上国の開発に関する課題にとどまらず、世界全体の「経済成長、社会的包摂、環境保護」の3つの核となる要素を、不可分のものとして調和させ統合的に解決する取組みです。
これらの要素は相互に関連し、そのすべてが個人と社会の安定にとって不可欠となります。
私たちは、地球を構成する一員として「誰一人取り残さない」社会を実現するために、SDGsによる現状の変革が急務となっています。
地方自治体がSDGsに取り組むことは、以下の4点のメリットがあります。
第1に「現状を改めて認識する機会となる」。SDGsに取り組むにあたり、自らの地域の状況を17のゴール、169のターゲット、、230の指標により見つめ直すことで、地域の特長や課題が明確になります。
第2に「バックキャスティング型手法で施策展開が図れる」。SDGsの特徴は、現在の延長線で未来を考えるフォーキャスティング型ではなく、目標を設定してから現状とのギャップを埋めていくバックキャスティング型の取り組みであることです。地方創生のあるべき姿を見据えて、バックキャスティング型手法で施策展開を図ることができます。
第3に「具体的な指標による進捗管理」が可能となる。SDGsの実施にあたり、活用する指標は各地共通のものとなります。自らの地域と他の地域との客観的比較ができるようになります。合わせて、自ら設定した目標の達成度を確認することで明確な進捗管理ができます。それの基づくPDCAサイクルを回すことができるようになります。
第4に「海外への展開の可能性」。SDGsが設定する目標の中には、すでに地域で解決された目標もあります。こうした課題克服のノウハうムや経験を海外の地域にも提供することができるようになります。地域が世界に大きく貢献することができるようになります。
このような基本的な考え方のもと、茨城県においては、以下の具体的な視点を持ってSDGsを推進することが必要と考えます。
1.茨城県におけるSDGs推進方針の策定
①地方自治体におけるSDGs推進方針の策定
あらゆる人々の目標であるSDGsの達成には、グローバル、ローカルの枠組みを超えて、一人ひとりがその課題解決に向けて取り組むことが求められており、地域住民や企業に最も近い位置におり、複数のステークホルダーが関係を構築するに当たって中心的な役割を果たすことのできる自治体行政がリーダーシップを持って進めることが必要となります。
茨城県としてSDGsを推進することの基本的な理念や県・県民・事業者等の責務を示した条例、県民憲章などを制定するなど、SDGs推進の拠り所となる指針の策定などが求められます。
また、SDGs推進に当たっては、指針の策定のみならず、行政による可視的な先導も重要です。知事をはじめとした県職員が、SDGsを理解するとともに、SDGs推進に向けて、積極的な周知に努めることが求められます。
特に、SDGsに係る社会問題は、経済、社会、環境という枠を超えた領域横断的なものとなっていることから、特定の部局のみによる解決は望めません。このことから、「縦割り」行政を打破し、部局間の横のつながりを強化して、統合的に課題解決を図る体制を構築する必要があります。
(具体的な施策提案)
*SDGs推進に向けた条例、県民憲章の制定を検討
*県職員のSDGsの理解促進と広報活動(ゆるキャラや名刺へのロゴ活用など)
*SDGs推進を担う体制の確立(縦割り行政の打破、水平連携の強化)
*SDGsの普及・啓発を全県的に推進する県民運動の組織化、中核組織の創設
*市町村のSDGs事業の支援や連携を図る組織体の創設
*市町村との連携のもと国の「SDGs未来都市」「SDGsモデル事業」への取り組み強化
②各種県計画とのマッチング
茨城県では、「茨城県総合計画」を現在改定作業中です。各分野において様々な計画を策定し、未来性豊かで戦略的な茨城県づくり進めてきています。また、県政改革の中核的な手法として「行政評価システム」を位置づけ、事務事業評価も実施してきています。
SDGsの導入にあたっては、これらの既存計画における目標設定やその進行管理の状況と、関連するSDGsとを照らし合わせ、現段階における達成状況を把握するとともに、SDGsの特徴である「バックキャスティング手法」を活用しつつ、具体的な達成目標を設定し、政策や政策手段の形成を図ることが求められます。
(具体的な施策例)
*新たな県総合計画の策定にSDGsの考え方を導入
*SDGsとの関連性を踏まえた各種計画の策定・見直し
*目標達成に向けた政策・政策手段の形成
2.県民の行動様式としてのSDGsの浸透
①SDGsの浸透に向けた普及・啓発
SDGsを推進するに当たっては、行動様式として県民全体にSDGsを浸透させることが必要となります。そのような観点から、市民の認知・理解を醸成するために、有識者等による(行政・企業・民間各々を対象とした)講座・講演会を地域各地で実施することが求められます。
また、SDGsに係るロゴやアイコンを広報紙、イベント、公共物装飾等に使用し、さらにその取組を民間企業や教育機関に普及させるなど、市民・企業等の認知・理解の促進を図ることが求められます。
普及活動に当たっては、専用ホームページやSNS等、電子媒体の効果的な活用や、分かりやすく印象深いキャッチコピーを作成・活用することなども求められます。
(具体的な施策例)
*有識者、大学等高等教育機関、NPO団体等と連携した講演会・市民講座の実施
*県が発信する各媒体や公共施設におけるロゴの活用
*教育機関、企業による理念の共有・ロゴ使用の促進
*電子媒体を活用した情報発信(県のホームページやSNS、いばキラTVなど)
*県民理解を浸透させるキャッチコピーの検討・活用
②SDGsを取り入れた教育の推進
教育は「全てのSDGsの基礎」とも言われています。
中でもESD(Education for Sustainable Development:持続可能な社会のための教育のこと)は、持続可能な社会の担い手づくりを通じて、SDGsの17全ての目標の達成に貢献するものとなっています。
学習指導要領にも、総則および各教科の指導要領双方においてESDを重視する記載があることから、ESDを基調としたSDGs教育の推進が望まれます。
各学校の教育目標・学校経営方針の中核にESDを位置づけるとともに、総合学習、各教科、道徳、特別活動などにおいてESDを実施・推進していくことが求められます。各地域での取組に当たっては、地域における優先課題やこれまでの学校の取組を踏まえつつ、マクロな社会問題に焦点を当て、地域社会、教育機関、企業などと連携し学びを深めていくことが重要となります。
また、文部科学省および日本ユネスコ国内委員会では、ユネスコスクールをESDの推進拠点と位置づけ、加盟校増加に取り組んでいます。
これらの教育活動を通して、多様性を尊重し、グローバルな課題を身近な課題として捉え、主体的に解決していける人材を育成することが求められます。
(現在、ユネスコスクールとして登録されている県内教育機関は、茨城県立並木中等教育学校、茨城キリスト教学園中学校高等学校の2校のみです)
(具体的な施策例)
*各校の教育目標の中核部にESD、SDGsを位置づけ
*教育分野でのSDGsを推進するため、教員の啓発・研究機会の拡大、児童生徒への啓発活動の強化
*ユネスコスクールの拡大
3.SDGsの包摂性とシナジー効果を踏まえた施策の展開
①「誰一人取り残さない」を基軸とした施策の展開
脆弱な立場の人に焦点を当てた「誰一人取り残さない」は、SDGs推進に当たって根幹的な理念です。
その中でも、茨城県お対応が遅れている目標としては、「SDGs目標1:貧困、SDGs目標5:ジェンダー、SDGs目標10:不平等」が挙げられます。
このことも踏まえ、「誰一人取り残さない」に直接的に関わる、「貧困、ジェンダー、不平等」に重点を置いた取組を推進する必要があります。
例えば「重点施策としてSDGs目標5:ジェンダー=女性活躍推進」に取り込むことで、間接的に、貧困や不平等など「複数のSDGsの達成が可能」というように、各問題の連関性(シナジー効果)を意識して取り組むことが重要となります。
②SDGsのネクサスアプローチ
貧困や飢餓といったテーマごとの前進を図ったミレニアム開発目標とは異なり、SDGsは、全ての課題は相互に深く関連し包括的に解決を進める必要があるとの認識に立って、新たなアプローチが志向されていることです。
つまり、個々の課題解結を連動させる形で、他の目標の達成も進めていくという「好循環」を生み出すことを目指しています。
例えば、安全な水の確保ができれば(SDGs:目標6)、病気や感染症に苦しむ人が無くなり(目標3)、毎日毎晩のように水汲みをしてきた女性や子どもたちの負担が軽減され、女性が就業する機会が増え(目標5)、所得が増える(目標1)、また子供たちは学校に通るようになる(目標4)といったプラスの連鎖が始まります。これは「ネクサスアプローチ」と呼ばれています。
SDGsは、17分野にわたる169の項目があります。多岐に及ぶ課題の関連性を見いだしながら、その困難な課題に対して同時進行的に解決を図っていくアプローチを、茨城県も展開していくべきです。
4.企業、大学、団体等の主体的なSDGs推進の支援
SDGsの達成は、自治体の力のみならず、各ステークホルダーとの連携・パートナーシップの構築が重要であり、民間の知見や技術、資金の活用が不可欠です。
行政と民間、民間と民間の関係を強化することで、SDGsに係る個々の取組を点から線、線から面へ広げていくことが求められます。
①企業によるSDGs推進の支援
SDGsは、イノベーションの創出や雇用の増大など、新たな市場機会の拡大につながります。
SDGsの社会的な認知度が高まっていない現状において、企業が導入する意義等を周知するため、SDGs導入に係る説明会を開催することなどが求められます。
また、SDGsに関して先端的な取組をしている団体・企業(例えば貧困問題、環境問題等の解決に積極的に取り組んでいる企業など)を「(仮称)いばらきSDGsアワード」において表彰することで、そのノウハウを社会的に共有するとともに、他団体・企業のインセンティプ強化を図ることも有効な取組と考えます。
さらに、委託事業者等の入札参加資格や選定基準として、SDGsの各目標を挿入することで、民間への導入を促進することも考えられます。
(具体的な施策例)
*企業向け導入説明会の開催
*(仮称)いばらきSDGsアワードの創設
*SDGsに関する取組等を入札参加資格や業者選定基準等として設定
②「オールいばらき」でのSDGs推進の仕組みづくり
茨城県では、企業や大学の他にも、地域の住民組織、NPO、ボランティアグループやサークルなど様々な団体が活発に活動しており、そのなかには、SDGsのそれぞれの目標に関する取組を推進している団体も多数あります。
たとえば、学区などの地域の住民組織では、「SDGs目標7:持続可能なエネルギーヘのアクセス」、「SDGs目標12:持続可能な消費と生産」、「SDGs目標13:気候変動対策」に関連するコミュニティ活動や、「SDGs目標11:住み続けられる街づくり」に関連する自主防災の取組など、すでにSDGsが推進されているともいえます。
しかし、そのような団体でもSDGsを意識して活動している団体はまだまだ少ないといえます。そこで、それらの取組をSDGsと関連づけたり、SDGsの取組として見える化することにより更なるSDGsの推進が期待されます。
また、SDGsをキーワードに多様な団体が連携することにより、新たな取組を生み出すことも期待できます。
さらに、オールいばらきで取り組むことにより、茨城県の課題や目標を共有するとともに、SDGs達成に向けた取組を加速化させることができます。
そのためにも、官民を超えてオールいばらきでSDGsを推進するための仕組みづくりが必要です。
それにあたっては、今後見直しが検討されている「大好きいばらき県民会議」の新たの事業の一環としてSDGs推進を位置づけ、県民運動の中核とすることを検討すべきです。
(具体的な施策例)
*オールいばらきでSDGsを推進する(仮称)いばらきSDGs推進プラットフォームの創設
*SDGsポータルサイトやアプリの構築
*多様な団体のSDGs活動を支援し、連携を図るための窓口やコーディネーターの設置
5.世界共通言語であるSDGs推進を通じたいばらきブランドの向上
①世界湖沼会議で茨城県のSDGsの取り組みをアピール
世界湖沼会議は、1984年に滋賀県の提唱により開かれた「世界湖沼環境会議」の後身として、世界各地で開催されてきました。以来、世界湖沼会議は研究者・行政担当官・NGOや市民等が一堂に集まり、世界の湖沼及び湖沼流域で起こっている多種多様な環境問題やそれらの解決に向けた取り組みについての議論や意見交換の場となっています。
茨城県で世界湖沼会議が開催されるのは、1995年に第6回会議を開催して以来、23年ぶり2回目となります。
SDGsでは、特に湖沼環境に関連するものとして、「水・衛生の持続可能な管理」や「陸域生態系、森林管理、砂漠化への対処、生物多様性の保全・回復」が掲げられています。こうしたSDGsと湖沼との密接な関係を参加者や県民にアピールできる内容を充実させるべきです。
(具体的な施策例)
*世界湖沼会議で茨城県のSDGsの取り組みを積極的にアピール
②茨城の強みをSDGsの視点で内外に発信
茨城県にはつくば、東海地域を中心に世界的な知の集積が見られます。現在進められているつくば国際戦略総合特区での活動は、SDGsの理念を具体化した事業展開に他なりません。
また、茨城県は日本第二の農業大県です。水産業、林業も全国に誇るべき産業です。自然を守り、自然を生かした農林水産業モデルを構築することは、SDGsの理念にかなう取り組みです。
こうした茨城県の様々な先進的な取り組みをSDGsの視点で全国に、国際的に発信することはいばらきのブランド力向上に直結すると考えます。
さらに、「(仮称)いばらきSDGsアワード」受賞の民間企業・団体等と協力し、公民連携によって、SDGs向上に関する知見や技術を海外都市に提供する取組を促進することが求められます。
(具体的な施策例)
*茨城の強みをSDGsの視点から、国内外に紹介する(広宣物、ホームページ・SNS、いばキラTVなどを活用)
*(仮称)いばらきSDGsアワードを創設し、いばらきのブランド力の向上を図る