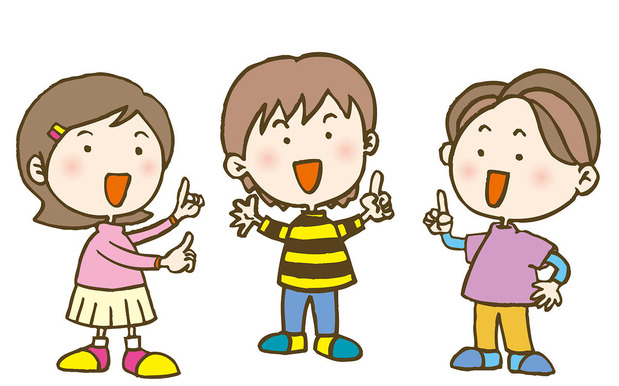
9月27日、茨城県議会9月定例議会の最終日に、手話普及促進条例(茨城県手話言語の普及の促進に関する条例)が議員提案され、全会一致で可決成立しました。
手話は、物の名前や意思、概念等を手や指、体の動きや表情を使って表現する独自の言語です。日本では、明治時代に始まり、手話を使い生活を営む方の間で大切に受け継がれてきました。その一方で、言語としての手話を学び、使用する環境が整えられてこなかったことから、手話を使い生活を営む方は、多くの不便や偏見を受けてきました。
こうした中、平成23年に改正された「障害者基本法」や平成26年に我が国も批准した「障害者の権利に関する条約」により、手話が言語に含まれることが明確化されました。
また、茨城県では、平成28年に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」を制定し、取組を進めているところです。
しかし、いまだに手話に対する理解や普及は、大きな広がりを見せていない状況であり、手話を広く県民に普及するとともに、手話を使用しやすい環境を整備していくことが求められています。
このため、手話が言語であるとの基本的な認識を確認し、手話を使い生活を営む方もそうでない方も相互に尊重し合いながら共生する社会を実現するため、手話普及促進条例が提案されました。
この条例では、手話言語の普及の促進を図るため、基本理念として、手話を使い生活を営む方にとって、手話は知的かつ心豊かな生活の実現に重要な役割を担うものであること、また、そうした方の意思疎通を行う権利を尊重することなどを掲げています。
その上で、県の責務として、基本理念にのっとり、手話の普及など手話を使用しやすい環境の整備に関する総合的な施策を策定し実施すること、また、市町村や関係団体との連携を図るとともに、手話による意思疎通の支援に重要な役割を担っている手話通訳者の方などの協力を得るよう努めることを、規定しました。
さらに、市町村の役割として、県と連携し施策を実施するよう努めることを規定しました。
そして、県民の役割として、基本理念に対する理解を深めるよう努めることを規定するとともに、手話を使い生活を営む方や、手話通訳者をはじめ手話に関わる方、事業者それぞれについて、その役割を規定しました。
県の実施する施策として、県民が手話を学ぶ機会の確保や、手話を用いた情報の提供、手話に関する調査研究への協力を規定しています。
また、手話を使い生活を営む方の意思疎通の機会の確保と、手話通訳者の負担の軽減のため、手話通訳者等の確保、養成や、その活動に対する理解の増進を規定しています。
あわせて、手話を使い生活を営む生徒などが通学する学校の設置者は、教職員の手話の習得に必要な措置のほか、その生徒や保護者などに対する手話の学習機会の提供や手話を使用した教育相談などの支援を行うよう努めるよう、規定しています。
そのほか、県は、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるとの規定を設けています。
すべての聴覚障がい者の生活を支援する条例検討を!
冒頭にも記しましたが、この条例は全会一致で認められましたが、案文に他県の同様の条例のように「ろう者・手話を使い日常生活又は社会生活を営む聴覚に障がいのある者等をいう」との一文があり、全体を通して「ろう者」という表現が使われています。
法律にも「ろう者」と言う表現はありません。旧民法には「聾唖」という言葉が使われていましたが、現在は使われていません。手話を使う聴覚障がいの方に「ろう者」という定義を与えることには、聴覚障がい者の中で手話を使わない障がい者との新たな差別を生んでしまうのではないかとの懸念もあります。この手話普及条例は差別を拡大したり固定化するものでは絶対にありません。
繰り返しになりますが、「手話を使い生活を営む方もそうでない方も相互に尊重し合いながら共生する社会を実現するため」との制定の目的を確認しながら、手話以外の聴覚障がい者の意思疎通方法にも県として十分に配慮し、普及拡大を図っていく必要があります。
聴覚障がい者は600~800万人いると言われています。手話を主たるコミュニケーション手段とされている方は2割に満たないといわれていいます。聴覚障がい者の多くは中途で障がいを持った中途失聴・難聴者です。
コミュニケーション手段としては、手話は重要ですが、補聴器や人工内耳を装用して残存聴力を生かす方法や、筆談、要約筆記、身ぶり、口の動き、指文字などのいろいろな視覚情報などがあります。こうしたことにも十分配慮し、すべての聴覚がい害者を支えられる条例も検討すべきです。



