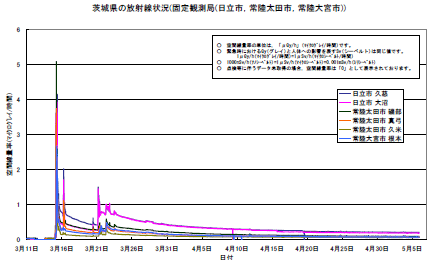
茨城県は、東電福島第1原発の事故に伴う放射線量のモニタリング体制を、連休明けに県内全市町村に拡大します。
県は、分析機器大手の堀場製作所から、小型線量計(環境放射線モニタ PA-1000 Radi・ラディ)の寄付を受けた、全市町村に配布します。 市町村の担当者向けに測定方法の説明会も開催することにしています。
市町村の担当者向けに測定方法の説明会も開催することにしています。
また、これまで測定を実施していない市町村でモニタリング車による移動測定を行うことにしています。
その背景には、放射線に関する県民の根強い不安感があり、具体的な数値を示すことで、その解消を図りたい考えです。
すでに茨城県内には、JCO臨界事故を受けて、放射線量を常時監視する固定局が、東海村や大洗町周辺の9市町村に合計41カ所設置されています。また、福島第1原発事故を受け、3月13日から順次、北茨城市と高萩市、大子町の3市町内に各1カ所、さらに4月27日に神栖市の鹿島港湾事務所でそれぞれ観測を開始しました。県内の測定カ所は13市町村までに拡充されており、常時その結果は、ホームページで公開されています。
 これまでの測定では、3月15日未明に放射線量が急上昇し、16日に北茨城で毎時15.8マイクロシーベルトの最大値を記録しました。測定開始から4月28日までの積算の放射線量は、北茨城市で約670マイクロシーベルトで、年間換算で約2ミリシーベルトに達す計算です。これは、全世界平均の年間2.4ミリシーベルト、日本における値は1.4ミリシーベルト(1998年10月国連科学委員会報告の推定値)と比べても、極端に高い値ではなく、24時間屋外にいても健康には影響がないレベルです。
これまでの測定では、3月15日未明に放射線量が急上昇し、16日に北茨城で毎時15.8マイクロシーベルトの最大値を記録しました。測定開始から4月28日までの積算の放射線量は、北茨城市で約670マイクロシーベルトで、年間換算で約2ミリシーベルトに達す計算です。これは、全世界平均の年間2.4ミリシーベルト、日本における値は1.4ミリシーベルト(1998年10月国連科学委員会報告の推定値)と比べても、極端に高い値ではなく、24時間屋外にいても健康には影響がないレベルです。
 参考:携帯電話向けサイトでも現在の放射線量がご覧になれます。
参考:携帯電話向けサイトでも現在の放射線量がご覧になれます。



