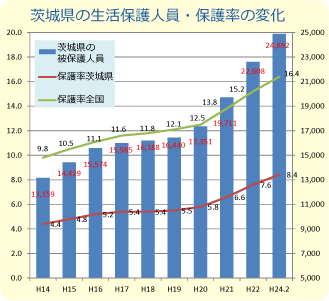 6月6日までに昨年度の県内生活保護受給者の統計がまとまりました。それによると、2011年度の生活保護受給者の平均値は、前年度比1811人増の2万4419人となりました。増加比は8%で、18年連続で上昇しました。2000年代に入り倍増し、保護率は8.4(1000人当たり8.4人)で、120人に1人は生活保護を受けている計算となります。しかし、全国平均は16.4ですので、半分程度の数値です。
6月6日までに昨年度の県内生活保護受給者の統計がまとまりました。それによると、2011年度の生活保護受給者の平均値は、前年度比1811人増の2万4419人となりました。増加比は8%で、18年連続で上昇しました。2000年代に入り倍増し、保護率は8.4(1000人当たり8.4人)で、120人に1人は生活保護を受けている計算となります。しかし、全国平均は16.4ですので、半分程度の数値です。
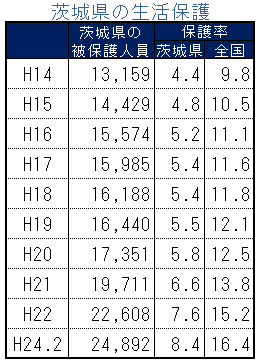 茨城県の生活保護受給者は、戦後の一時期を除いて徐々に減少し、1993年度は8720人にまで少なくなりました。その後は、バブル景気の破綻と共に上昇に転じ、2008年のリーマン・ショック以降は対前年度比の伸び率が1割を超え急上昇しました。生活保護費の総額は421億円に上ります。
茨城県の生活保護受給者は、戦後の一時期を除いて徐々に減少し、1993年度は8720人にまで少なくなりました。その後は、バブル景気の破綻と共に上昇に転じ、2008年のリーマン・ショック以降は対前年度比の伸び率が1割を超え急上昇しました。生活保護費の総額は421億円に上ります。
生活保護受給者急増の対策には、就労対策の強化や指導体制の充実など、生活保護受給者を支える仕組みを強化する必要があります。受給者の増加に、保護世帯を支援・指導するケースワーカーも絶対数が不足しています。社会福祉法はケースワーカー1人当たりの担当世帯を市部80世帯、郡部65世帯と規定していますが、茨城県内36の福祉事務所のうち12事務所が配置基準を満たしていません。
また、不正受給者への対策も不可欠です。厚生労働省は、生活保護費の約半分を占める「医療扶助」の不正受給を監視するため、電子化されたレセプト(診療報酬明細書)を活用し、不審な点が疑われる事例を瞬時に発見するソフトを開発し、今秋から全国の自治体に導入するとしています。
生活保護費は、2012年度当初予算ベースで3兆7千億円。うち受給者の医療費に当たる医療扶助は1兆7千億円に上り、全体の45.9%余りとなっています。この医療扶助は受給者の窓口負担がないため、過剰な診療、薬の投与が起きやすいとの指摘があります。向精神薬などを転売目的で不正に薬が処方され、問題となった事例なども報道されています。生活保護受給者と医療機関が一体となった不正も指摘されており、監視ソフトの導入効果が期待されます。



