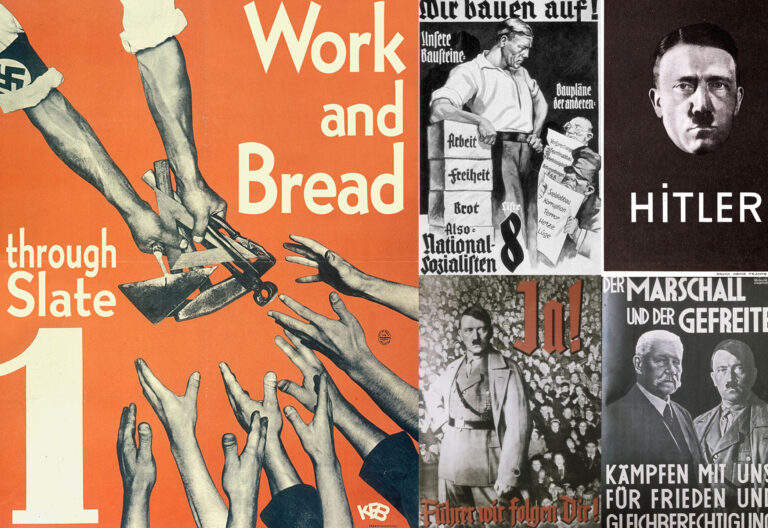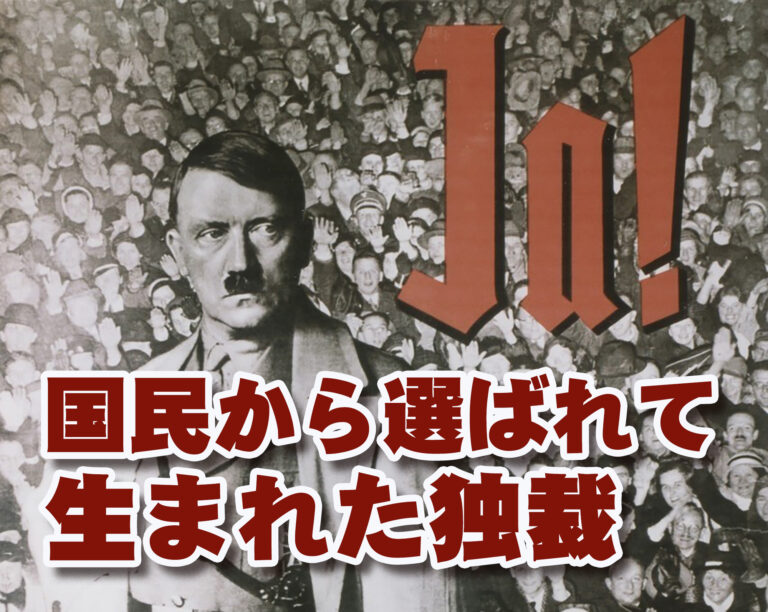新聞宅配制度は、国民の「知る権利」を保障する
 読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、茨城新聞、常陽新聞そして政党の機関紙・公明新聞、支持団体の機関紙・聖教新聞、以上7紙が、毎朝、私の自宅事務所に配達されてきます。インターネットが普及し、主要記事はネット上でほとんど確認できるとはいえ、この新聞各紙に目を通すのは、毎日の日課です。
読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、茨城新聞、常陽新聞そして政党の機関紙・公明新聞、支持団体の機関紙・聖教新聞、以上7紙が、毎朝、私の自宅事務所に配達されてきます。インターネットが普及し、主要記事はネット上でほとんど確認できるとはいえ、この新聞各紙に目を通すのは、毎日の日課です。
この新聞の宅配制度は、今、大きな曲がり角に差し掛かっています。公正取引委員会が、新聞の宅配制度を支えている「特殊指定」の見直し作業を進めているからです。6月までに結論を出す方針ですが、指定廃止が決定されれば価格競争や販売競争が激化し、配送コストがかさむ山間部や離島などでは値上げや配達切り捨てが起こりかねない状況です。
特殊指定制度は、特定分野での不公正な取引を防ぐために、公正取引委員会が独占禁止法に基づき新聞や教科書など7分野に適用している制度で、このうち新聞を含む5分野について、公正取引委員会は2005年11月に見直しの方針を打ち出しました。
新聞の特殊指定は1955年に告示され、同一新聞社が地域や読者によって価格を変えたり、割り引いたりすることを禁じています。過疎地でも都市部でも、同じ新聞は同じ時間に同じ条件で公平に届けられるべきとの考えからです。と同時に、新聞に対する特殊指定は読者の利益、公共の利益の確保につながり、社会の情報格差を埋める役割も果たします。
このことは結果的に、民主主義の根幹である言論の自由や国民の知る権利を保障することにもなると、私は考えます。
公正取引委員会が、新聞の特殊指定を見直す姿勢を崩さないのは、「規制緩和は時代の流れ」との考えからです。事実、公正取引委員会は、公明党の独禁法調査検討委員会との意見交換の場で、「『再販制度』があるので、宅配維持は守られる」との見解を示しています。しかし、再販制度は、販売店が新聞社の指定価格を守らずに割り引きした場合、新聞社が取引契約を解除してもよいと定めているにすぎません。いわば、二つの制度は車の両輪であって、特殊指定が撤廃されるなら再販制度も骨抜きになりかねません。
規制緩和は大事な考え方ですが、新聞宅配が無くなってしまうメリットとデメリットを慎重に検討すべきだと主張します。
日本新聞協会が2005年に行った読者調査や、共同通信社が3月に実施した世論調査などに明らかなように、国民の9割近くは宅配制度が続くことを支持しています。
公正取引委員会は、こうした国民の声に率直に耳を傾けるべきです。国会審議が必要な再販制度見直しと異なり、特殊指定の見直しは公取委の告示だけで済むだけになおさらです。
2005年7月には、超党派の国会議員提出による「文字・活字文化振興法」が施行され、「すべての国民が等しく活字文化の恵沢を受ける環境の整備」が基本理念として掲げられました。国を挙げて活字文化の振興を目指そうという矢先の特殊指定見直しは、この法の精神にも時代の要請にも逆行しているのではないでしょうか。