平成の大合併に伴い「在任特例」制度を使って合併した市町の議会に対して、住民が「議員が多すぎて、スリムで効率的な行財政運営を行うという合併の主旨に反する」として、議会の解散を求める署名運動が茨城県内各地で行われています。
既に2005年2月に旧常北町、桂村、七会村が合併して生まれた城里町では、在任特例で42人に膨れあがった議員に対して、市民団体が約7000人の署名を集めて、住民投票が行われました。2月に行われた住民投票では投票総数の85%が議会解散を支持し、出直し選挙が行われて議員定数は18人と少なくなりました。
5月5日現在では、常陸大宮市、常陸太田市、桜川市で議会解散の運動が行われています。また、笠間市でも署名運動を呼びかけるチラシが新聞折り込みで配布されています。
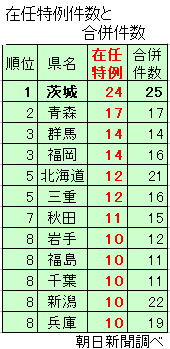 いずれも、在任特例で一定期間、議員が旧町村の枠組みのまま在任しているため、議員数が非常に多くなっています。具体的には常陸大宮市が75人(在任特例が満了後の定数は26人)、常陸太田市68人(26人)、桜川市47人(26人)です。
いずれも、在任特例で一定期間、議員が旧町村の枠組みのまま在任しているため、議員数が非常に多くなっています。具体的には常陸大宮市が75人(在任特例が満了後の定数は26人)、常陸太田市68人(26人)、桜川市47人(26人)です。
在任特例は、市町村合併を円滑に進めるために、合併した市町村の議員の任期を一定期間延長して、旧市町村の議員がそのまま在任することが出来る制度です。「合併を進める上では旧市町村の議員の同意を得るためにどうしても必要な制度」、「合併した後に地域の格差を生じさせないためには、旧町村の議員を在任させることが必要」、「合併後も様々な行政上のシステムの整合性を図るために、議会の仕事は山積みされており、在任特例による任期の延長が必要」などとの在任特例に対する肯定論も多いが、一般住民としては、あまりに多い議員の数は不自然に映っているようです。
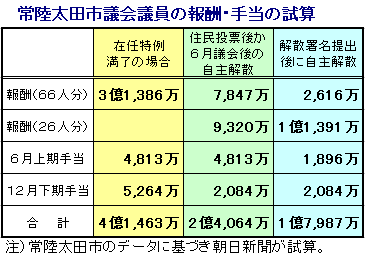 4月27日付けの朝日新聞は、地方版の一面を使ってこの茨城県内の情勢を特集しました。
4月27日付けの朝日新聞は、地方版の一面を使ってこの茨城県内の情勢を特集しました。
その中では、全国的にみても茨城県は、在任特例を利用した合併が最も多かったことを具体的に報道しています。
また、同紙では在任特例通りで議会を運営した場合と早期に解散した場合の報酬・手当を具体的に試算しています。それによると、在任特例通りの場合は4億1463万円、解散署名提出後に議会が自主解散した場合は1億7987万円となるとしています。実際には、議員年金の負担金や議会の費用弁済が試算には含まれていませんので、経費の差はもっと大きくなります。また、住民投票の費用も数百万円かかるとされ、経費の面だけを考慮すれば、議会は自主解散をするべきということになります。
◇報酬、早期解散でどう変わる? 常陸太田、特例通りは4億円
朝日新聞(2006/4/27付け茨城版)
在任特例を適用した議会の場合、早期解散でどの程度の財政削減が見込めるのか。常陸太田市議会を例に想定できるケースを基に試算してみた=表参照。
1町2村の編入合併後、同市議会は議員報酬を最も高い旧常陸太田市議の水準に引き上げ、月額39万5千円になった。
すでに5人の議員が辞職しているが、仮に在任特例に基づき4月1日時点の66人が07年3月まで在籍した場合、報酬と年2回の期末手当は、年金の積み立て分などを除いても、1年間で計4億円を超える。
住民投票後か6月議会終了後に解散、7月選挙の場合は、年間の報酬と手当は計約2億4千万円(6月1日に議員として在籍していれば全額支払われる上半期の期末手当を含む)。
解散請求の署名提出後に議会が自主解散した場合の報酬と期末手当の総額は約1億8千万円になる。
4月で仮に解散すると、66人に上半期の手当はなく、66人が来年3月まで在籍する場合に比べ、約2億3千万円少なくなる計算だ。



