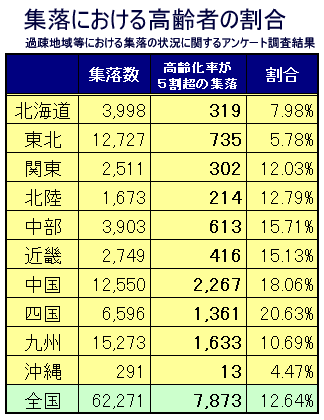 限界集落とは、過疎化などで人口の半数以上が65歳以上の高齢者となり、冠婚葬祭などの社会的共同生活の維持が困難になった集落のことを言います。(詳しくは「『限界集落』という言葉を知っていますか?」をご参考下さい)
限界集落とは、過疎化などで人口の半数以上が65歳以上の高齢者となり、冠婚葬祭などの社会的共同生活の維持が困難になった集落のことを言います。(詳しくは「『限界集落』という言葉を知っていますか?」をご参考下さい)
この言葉は、長野大学産業社会学部の大野晃教授が1991年に提唱したもので、国土交通省の調査では、今後10年の間に消えてしまうと思われる集落は2109もあるといいます。高齢化と過疎化により活力を失った集落は、そのまま将来の日本の縮図なのかもしれません。
国土交通省は過疎地域自立促進特別法に基づき、過疎地域に指定されている775市町村を対象に、集落の将来予測に関するアンケートを行いました。その結果、全国の集落6万2271のうち、65歳以上の高齢者が半数以上の限界集落は7873にのぼりました。これは全体の12.7%に当ります。このうち全国で2641の集落が消滅の危機に瀕しており、422の集落は10年以内に消滅する可能性があるといいます。
限界集落が消えてしまうことの影響は、その村だけではなく、他の地域にも及びます。山間部にある棚田は、水を溜めることで保水機能を果たし、豪雨などの際の緩衝作用として機能してきました。しかし耕作を放棄された棚田は、数年でもとの山地に戻ってしまい、プールの役目を果たさなくなります。保水力のなくなった山はそのまま雨水を流してしまい、下流での洪水の原因にもなります。
過疎地の衰退に歯止めをかけるためには、国レベルでの山村活性化のための施策が必要になります。



