 5月2日、井手よしひろ県議は、茨城県内で地球温暖化の影響を具体例を調査するため、野内健一町議(公明党)とともに大子町のリンゴ栽培農家を訪れました。
5月2日、井手よしひろ県議は、茨城県内で地球温暖化の影響を具体例を調査するため、野内健一町議(公明党)とともに大子町のリンゴ栽培農家を訪れました。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)の研究(果樹農業に対する地球温暖化の影響予測モデルの開発とその影響評価)によると、リンゴ栽培に適する年平均気温7~13℃の地域は、2060年代には東北地方の平野部のほぼ全域が範囲外となるなど、現在の主産地の多くが、暖地リンゴの産地と同程度の気温になる可能性があるという予測を公表しています。一方、現在は温度が低すぎる北海道の平地部が、リンゴ栽培の最適地となるとされています。
この予測が正しいとすると、大子町の主要な農産物の一つであるリンゴ栽培も、今後大きく見直す必要があることになります。
井手県議らはこうした状況の変化を前提に、最近の温暖化の影響などについて、農家のご主人より様々なご意見を伺いました。まず、長期的な温暖化への対応は品種の更新により、ある程度対応できるのではないかという見通しを伺いました。大子町の場合、リンゴ狩りや産直販売により直接消費者にリンゴを販売するため、状況の変化に柔軟に対応できるとの説明を受けました。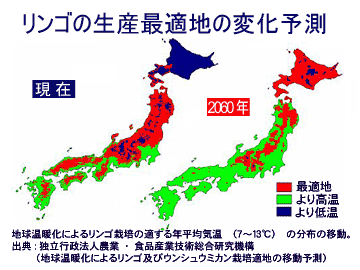
また、リンゴ自体の問題よりもダニやカメムシなどの病害虫への対応の方が、より深刻な問題となる可能性があるとの指摘がありました。今までは、越冬できないとされていた害虫が冬を越すようになり、害虫の影響が数多く出る懸念があるとのことでした。実際、昨年はカメムシが大発生し、大きな被害を出ました。薬剤の散布回数もそれに比例して増え、コスト増にもつながってしまっています。
さらに、気温の上昇により、リンゴの着色不良が起こっていることも報告されました。今後、気候温暖化が進行すると果肉の成熟に果皮の着色が後れを取ることとなり、販売に耐えうるリンゴの生産が困難になることも考えられということでした。
この日の意見聴取により、県内のリンゴ栽培を過度に不安視する必要はないものの、気候変動を先取りした品種の更新と病害虫へのしっかりとした対応が不可欠であることが明確となりました。
(写真は白い可憐な花を付けたリンゴの木、5月2日撮影)



