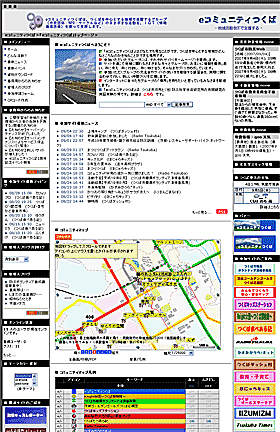 9月4日、井手よしひろ県議は、独立行政法人防災科学技術研究所を訪れ、「eコミュニティ」について、災害リスクガバナンス研究チームのプロジェクトディレクターである長坂俊成主任研究員、増田和順地域コミュニティ研究チームリーダーより説明を受けました。井手県議は、8月20日、県議会土木委員会の一員として、同研究所を視察し講演を伺いました。(土木委員会で防災科学技術研究所を視察)今回の視察は、現在つくば市内で進められている「eコミュニティつくば」の事業展開について、具体的に説明を聴取する目的で行われました。「eコミュニティつくば」を地元で中心的に進めている、小野やすひろつくば市議も同行しました。
9月4日、井手よしひろ県議は、独立行政法人防災科学技術研究所を訪れ、「eコミュニティ」について、災害リスクガバナンス研究チームのプロジェクトディレクターである長坂俊成主任研究員、増田和順地域コミュニティ研究チームリーダーより説明を受けました。井手県議は、8月20日、県議会土木委員会の一員として、同研究所を視察し講演を伺いました。(土木委員会で防災科学技術研究所を視察)今回の視察は、現在つくば市内で進められている「eコミュニティつくば」の事業展開について、具体的に説明を聴取する目的で行われました。「eコミュニティつくば」を地元で中心的に進めている、小野やすひろつくば市議も同行しました。
災害リスクガバナンス研究チームの研究のひとつは、地域防災力を高めるために地域コミュニティでは普段からどのような社会関係を結んでいればよいかというものです。その関係性を結ぶツールとして、インターネットの技術を活用した「eコミュニティ」が研究され、全国で先駆的な取り組みが行われています。
現在、構築されている「eコミュニティ」は地域のポータルサイトとして構築されています。地域情報の提供だけではなく、利用者が情報を入力しながら、その体験を蓄積したり、新たに情報を付け加えたりすることで、地域の新しい活動が産まれることが期待されています。
「eコミュニティ」は、SNSやブログのシステムを市町村という基礎自治体レベルで立ち上げたもの考えると、理解しやすいと思います。
パソコンや携帯電話を利用して、インターネット上のホームページに誰でも簡単に文書や写真、動画、音声などを投稿したり、閲覧、交換することができます。個人の日記やグループ活動記録、地域のイベント情報、町内会のお知らせなどを発信できます。
そして、「eコミュニティ」では地図情報が重要な役割を果たします。自治体などが提供する基本的な地図(例えば国土地理院の数値地図、オルソ化航空写真、行政が作成した防災ハザードマップなど)の上に、レイオヤー機能を活用し、階層的に個人やグループで作成した地図を作ることが出来ます。例えば、地域の防災マップや防犯マップなどを簡単に作成することが出来、その情報を共有したり、再利用することが出来るようになっています。こうした情報共有が経験の共有につながり、お互いへの信頼が増していきます。
防災研では、「eコミュニティ」を構築する基本ソフトを現在、開発しています。現在、稼働している「eコミュニティ」では、XOOPSを基本としてシステムが構築されていますが、今年度中には、さらに使いやすく、メンテナンスなども手軽なオープンソースのシステムを開発し、来年度からは自治体などに配布する計画です。
井手県議は、こうした防災研の取り組みを、茨城県内のつくば市以外の市町村に水平展開することの重要性を実感しました。地元である日立市でも、具体的な導入を目指して関係部門に働きかけを行う予定です。
 参考:eコミュニティつくばのHP
参考:eコミュニティつくばのHP
 参考:防災科学技術研究所・災害リスクガバナンス研究チームのHP
参考:防災科学技術研究所・災害リスクガバナンス研究チームのHP
以下、内閣府経済社会総合研究所編の「イノベーション事例集2007」から、「eコミュニティ」の具体例などを紹介します。
eコミュニテ:社会関係力
内閣府経済社会総合研究所編の「イノベーション事例集2007」
地域防災からリスクガバナンスへ
地域防災の研究から、地域の防災力を向上させるためには、地域コミュニティのあり方が重要であることがわかってきました。地域防災力には次のような多くの課題があります。
①少子・高齢化、都市化による地域コミュニティの脆弱化
②自主防災組織の形骸化・平常時の防災活動のマンネリ化
③災害文化の継承が困難(被災経験、ヒヤリハット、地域固有の対策)
④行政や専門家の防災情報が地域で活用されていない
⑤想定を超える大規模災害への共助の備えが不十分
⑥自治会、自主防災組織、災害ボランティ、防災NPO、企業市民、行政等の平時の連携とネットワークづくり
⑦活動圏域、相互援助を考慮した広域連携とそれを支える情報共有のしくみづくり
これからの地域防災には、地域の多様な主体の協治により災害リスクの軽減を図るという「リスクガバナンス」の考え方がますます重要になると考えられます。
eコミュニティによる社会イノベーション
こうした課題を解決するために大切なのは、平時の地域社会に形成される多様な社会関係であり、地域防災に必要なのは、この社会関係の力(社会関係力)なのです。
eコミュニティを活用することで、地域の社会関係力を強化することができると考えられます。
たとえば、静岡県島田市の大津地区では、町内の住民活動や安全安心に関する情報を収集し共有したいというニーズがありました。
島田市には「eコミュニティしまだ」という地域情報ポータルサイトが運用されています。同地区の住民の有志はこのサイトの機能を活用し、フィールドワークなどを通じて、地域住民から情報を寄せてもらい、住民参加型のハザードマップづくりを行いました。
さらにこのハザードマップにランドマークを加える活動や、被害情報の収集訓練、災害ボランティアの案内用地図として利用する活動が産まれ、参加による経験の共有が地域住民の社会関係を厚くすることにつながり、地域防災力を高めることができたのです。
eコミュニティの活用事例
eコミュニティしまだの活用事例をさらに推し進めていくと、様々な技術と情報を組み合わせて、地域の防災力を向上させることができます。
たとえば、地理情報システム(GIS)に地域住民から収集した危険情報を反映させたり、携帯電話端末を活用して、災害情報の配信、収集を行ったりすることが技術的に可能です。
個々の技術が発達して高度な機能を実現していますが、ここで大切なのは様々な技術がシステムとして機能するということです。地域防災には住民一人一人の協力が欠かせませんし、その基盤となるのが地域コミュニティの「社会関係力」なのです。
eコミュニティにハザード情報を
神奈川県藤沢市には「ふじさわ電縁マップ」というeコミュニティがあり、住民が藤沢の観光名所や散策コース、バリアフリー情報、グルメ情報などを地図情報として公開しています。
このサイトではレーダーによる高精度の降雨量の情報を利用して、10mXlOm単位の浸水位や水害危険度の情報をリアルタイムで配信する試みを行いました。
ここでも地域住民の協力は欠かせません。住民による被害調査を行うほか、過去の経験知を掘り起こして情報化し、地域内の危険情報を整備していきます。
リアルタイム浸水被害予測システム(あめリスクナウ)とeコミュニティ(ふじさわ電縁マップ)とはもともと別のシステムですが、「分散・相互運用技術」を用いてそれらを結びつけて、さらに地域住民の収集した被害情報を反映すれば、公民連携による地域防災活動(リスクガバナンス)の情報基盤として大きな威力を発揮します。
子どもも参加して情報収集
藤沢市の片瀬地域では少年少女を対象に防災ワークショップを開催しました。成果は防災教育の効果だけでなく、津波の避難場所に指定されているマンションのオートロックの問題など、大人では気がつかないような課題を子どもたちの視線で発見できたことです。
災害時の情報収集と配信
災害時には被災住民や災害救援ボランティアから様々な情報が投稿されます。各種メディアが協力して配信する仕組みが必要です。
また、投稿された災害情報を整理・集約しないと、災害時に責垂な情報が活かされないケースがあります。
藤沢市ではeコミュニティに加え、コミュニティFM、衛星放送などの各種メディアを用いて、公民連携により情報を整理し適切に配信していく災害情報センター(仮称)の什組みづくりや、そこで中心的な役割を担う災害情報コーディネーターの育成に関する研究に取り組んでいます。
地域防災力は社会関係力
地域コミュニティは、地域住民の関係がどのようにつくられているかによって、機能の仕方が異なってきます。
地域防災研究の成果から、災害が発生したときに地域コミュニティに適切な対応ができるかどうかは、住民の社会関係力の強さに関係していることがわかってきました。
地域住民がどのような経験を共有し、準備をしているかで災害時の影響が異なってきます。こうした社会関係の積み重ねは、社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)であり、積極的に評価されてしかるべきものです。
安全・安心な社会を実現するためには、ハードの技術開発もさることながら、社会関係の厚みを増やすためのソフトな技術も大切です。
eコミュニティの補完性
地域住民の地域コミュニティへの関わり方は人それぞれです。昼間は遠くの職場に通勤していて、日頃は関わり合いの少ない人も多いことでしょう。
eコミュニティは現実の地域コミュニティに関わりを持ちにくい住民にとって、地域の情報を得ることができたり、発信することができたりする利点があります。eコミュニティの経験がきっかけとなって、現実の地域コミュニティに主体的に関わっていくこともあるでしょう。
eコミュニティは現実の地域コミュニティと対立するものではなく、補完的な役割を担いながら、地域コミュニティの形成を推し進めます。
eコミュニティもまた社会関係の厚みを増やす機能を有しており、ソフトな社会資本の一部だと言ってよいでしょう。
多様なコミュニケーションが信頼の源
地域の社会関係力を向上させるのは多様なコミュニケーションです。
島田市や藤沢市の例では、防災ワークショップの経験によって、危険情報を収集、集約しました。ありきたりな防災訓練では参加者は少なかったかもしれません。eコミュニティを活用し、地域住民が主人公として主体的に関わる仕組みを用意したからこそ、住民の潜在的能力が発揮され、多様なコミュニケーションが展開されたのです。
じつはこうしたコミュニケーションの輪は一つの地域のなかにとどまりません。様々な地域のeコミュニティが連携すれば、地域防災の情報を教えあうことができます。そこでは行政区域を越えた地域間の支えあいや協働の可能性が広がります。これも広い意味のリスクガバナンスの向上です。
eコミュニティによる社会イノベーションの実現
eコミュニティの活用事例では、様々な技術を組み合わせて活用し、地域の社会関係力を引き出しながら、地域防災力を向上させることができました。
社会関係力は社会への信頼度と置き換えてもよいでしょう。信頼度と経済成長には相関関係があることがわかっています。eコミュニティを活用することで行政区域や物理的な距離を越えた協働の可能性も見えてきました。こうした動きは地方分権、地域再生が課題となる中で、より良い社会への変化をもたらしていると言えます。
eコミュニティの活用はより良い社会への変化(社会イノベーション)だけでなく、経済成長にも貢献するものです。



