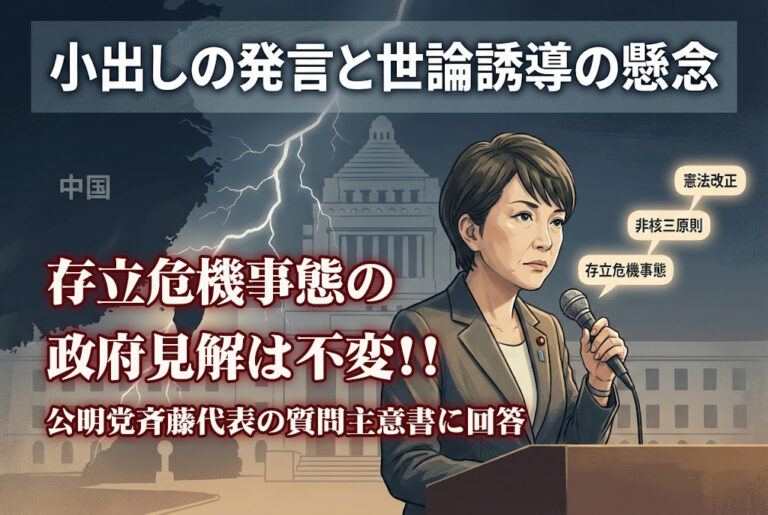与党と民主党、被災者支援法改正で合意
時事通信(2007/11/06-20:50)
住宅本体に適用-能登、中越沖地震も救済
与党と民主党は11月7日、それぞれが今国会に提出している被災者生活再建支援法改正案について、与党案を軸に一本化することで合意した。住宅本体にも支援金の適用範囲を広げたのが特徴。民主党が求めていた新潟県中越沖地震や能登半島地震の被災者に改正法をさかのぼって適用する措置は、特例で認める形で決着した。
参院災害対策特別委員会に自民、民主、公明の3党で共同提案し、9日の衆参本会議での成立を目指す。与党幹部は記者会見で「被災者は苦しんでいる。1日も早く(改正案を)通していかないといけない」と述べた。
特例措置を適用するのは、3月の能登半島地震と7月の新潟県中越沖地震、9月の台風11、12号による大雨災害。改正法公布後の被災申請は新制度で対応するとの内容を付則に盛り込み、実質的に遡及(そきゅう)適用して救済する。
 11月6日、自民・公明の与党と民主党の間で行われていた被災者生活再建支援法改正案をめぐる修正協議がまとまり、双方の案を一本化し今国会で成立させることで合意しました。
11月6日、自民・公明の与党と民主党の間で行われていた被災者生活再建支援法改正案をめぐる修正協議がまとまり、双方の案を一本化し今国会で成立させることで合意しました。被災者生活再建支援法は、地震などの自然災害被災者を支援する法律で、住宅が全壊するなど生活基盤を奪われた人々に対し支援金を支給する制度です。阪神・淡路大震災をきっかけに公明党などの推進で1998年に制定されました。生活必需品などの購入に最大100万円、住宅の解体・撤去などに最大200万円を支給するもので、被災者は合計で最大300万円を受け取ることができます。
しかし、その後の実績は、被災した世帯に対する支給額の平均は約56万円(居住関係経費)にとどまるなど、被災者の生活再建には不十分との声が上がっていました。特に、被災した住宅本体の建設や購入のは使えないなど、制度の見直しが求められていました。
全壊世帯には100万円、住宅建築に200万円を渡し切り
修正案では、これまで認められていなかった住宅本体の建設・購入にも使えるようにしました。支援金の使途の制限を外し、住宅の再建の仕方に応じて定額(渡し切り)を支給することにしました。
全壊世帯には100万円、大規模半壊世帯には50万円を一律に見舞金の形で支給。加えて住宅を建設・購入する世帯に200万円、住宅を補修する世帯に100万円、住宅を賃借する世帯には50万円を上乗せします。さらに、現行法では支給要件を前年度の年収を原則500万円以下としていますが、この年収・年齢要件も撤廃します。これにより被災者は簡素な手続きで支援金を受け取れるようになり、制度の使い勝手が大きく向上するものと期待されています。
この法案は与党案が衆院に、民主党案が参院に別々に提出されていましたが、「被災者支援の充実を図る」との立場から政策協議で歩み寄りが実現しました。参院で野党が多数を占めるねじれ国会下で実った初の政策協議であり、与野党の垣根を越えた、国民生活を最優先に据えた取り組みとして評価されます。
修正協議では、今年(2007年)1月以降に発生した災害への適用を認めることでも合意しています。能登半島地震、新潟県中越沖地震、台風11、12号災害を「特定4災害」とし、改正法公布後に申請すれば、新制度を適用します。特例措置とはいえ、事実上、過去の災害にさかのぼって適用する異例の改正となります。
修正協議は与党側の呼び掛けで始まりました。粘り強い協議の結果まとまった修正案に盛り込まれた上限金額や支給方法、対象、支給要件などについては「ほぼ与党案に沿った内容となり、民主党側の譲歩が目立つ」(11月7日付、朝日新聞)と評価されています。同法の見直しに当たって公明党は、独自の改正案を示し、与党案をまとめたほか、今回の修正協議においても、与党案の考え方に基づいて修正案の合意形成をリードしてきました。
「大連立」騒動で大きく混乱した国会ですが、国民生活を第一に考えた国会審議が是非とも必要です。こうした、真摯な対話が今後続くことを来したいと思います。
(写真は、中越沖地震での被災地の模様)