 自転車と歩行者の交通事故が、10年前に比べて5倍近くになっています。
自転車と歩行者の交通事故が、10年前に比べて5倍近くになっています。
茨城県内では、自転車が当事者となった事故件数は、減少傾向にありますが、最近5年間で12名の死亡者が出ています。特に、平成19年には5名が亡くなるという、痛ましい結果となっています。
最近の報道によると、東京・渋谷警察署は2月18日、昨年11月に電動自転車で歩行者をはねて死亡させた女性を重過失致死容疑で書類送検しました。この事件だけではなく群馬・桐生署も、桐生市の市道で昨年9月に自転車で登校途中、主婦をはねて死亡させた高校3年生の男子を、重過失致死の疑いで送検しています。
渋谷の事故は、道路を横断しようとしていた75歳の女性に47歳の女性が乗った自転車が衝突したものですが、そのとき自転車は30~40キロのスピードを出していたといいます。また、桐生市の事故では、高校生は雨のため左手でカサを持ち、前がよく見えない状態で自転車に乗り、前を歩いていた主婦に後ろからぶつかって死亡させてしまいました。
これらの事故では、自転車の運転マナーの悪さが大きな問題になっています。
一般に自転車は交通弱者であると考えられており、乗っている人も「自分は守られるべきもの」と思われていますが、それは対自動車などの場合で、対歩行者では、自転車は危害を与えるかもしれない強者の立場です。そのことをもっと自覚して歩道などを通るときは慎重に運転する必要があります。
交通ルールは自転車も自動車も同じ
 最近の自転車のマナーの悪さは、携帯電話と携帯音楽プレーヤーのせいだというの指摘もあります。実際、電話で話しながらとかメールを打ちながら自転車に乗っている人は若者を数多く見かけます。
最近の自転車のマナーの悪さは、携帯電話と携帯音楽プレーヤーのせいだというの指摘もあります。実際、電話で話しながらとかメールを打ちながら自転車に乗っている人は若者を数多く見かけます。
また、携帯音楽プレーヤーを聞きながら自転車に乗っている人も多いのですが、これもルール違反です。イヤホンで音楽を聴きながらだと、周囲の音がよく聞こえませんから自動車などの警笛も聞きづらく、また注意が散漫になるため、事故を起こしやすくなります。
 交通ルールは自転車も自動車も基本的には同じです。たとえば、歩道で自転車が歩行者の通行をさまたげたら、歩行者通行妨害で2万円以下の罰金または科料です。一時停止違反や信号無視は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、夜間無灯火も5万円以下の罰金です。酒酔い運転は自転車の場合でも5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
交通ルールは自転車も自動車も基本的には同じです。たとえば、歩道で自転車が歩行者の通行をさまたげたら、歩行者通行妨害で2万円以下の罰金または科料です。一時停止違反や信号無視は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、夜間無灯火も5万円以下の罰金です。酒酔い運転は自転車の場合でも5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。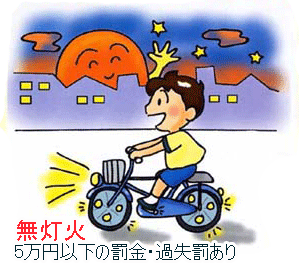
これまで警察はこれらのルールを厳正には適用せず、注意などで済ませてきましたが、今後は厳格に対処するようになると思われます。
また、6歳未満の幼児2人を自転車の前後に乗せた「3人乗り」についても、違反すれば「2万円以下の罰金、または科料」の対象となります。警察庁は2月3日、特例として「安定性が確保できる自転車の開発」を前提として、3人乗りを容認する方針を発表しましたが、既存の自転車での3人乗りを認めたわけではありません。
加害者になってしまったときための備えも必要
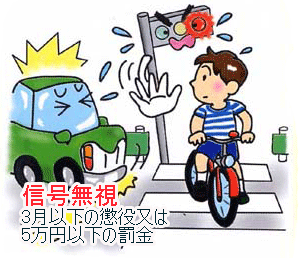 万が一、自転車で事故を起こし加害者になってしまった場合の対応を確認しておきたいと思います。
万が一、自転車で事故を起こし加害者になってしまった場合の対応を確認しておきたいと思います。
まず、負傷者がいる場合は何よりも先に救護し、119番に通報します。次に、小さな事故でも、必ず警察に通報し、調書を作成してもらうことが大事です。これを怠ると交通事故証明書が発行されませんから、保険に入っていても保障されません。
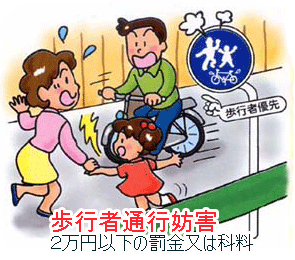 保険に加入している場合は、事故の状況をすぐに保険会社か代理店に連絡します。もし、相手が重度の障害を負ったり、死亡してしまった場合、個人で支払いきれないほどの損害賠償金を負わなければならないことになります。その点からも保険には入っておいたほうがいいでしょう。保険は、自転車総合保険のように専用のものもありますが、もし交通事故傷害保険や普通傷害保険に入っているなら、それに付帯する特約を付けておくといいでしょう。
保険に加入している場合は、事故の状況をすぐに保険会社か代理店に連絡します。もし、相手が重度の障害を負ったり、死亡してしまった場合、個人で支払いきれないほどの損害賠償金を負わなければならないことになります。その点からも保険には入っておいたほうがいいでしょう。保険は、自転車総合保険のように専用のものもありますが、もし交通事故傷害保険や普通傷害保険に入っているなら、それに付帯する特約を付けておくといいでしょう。



