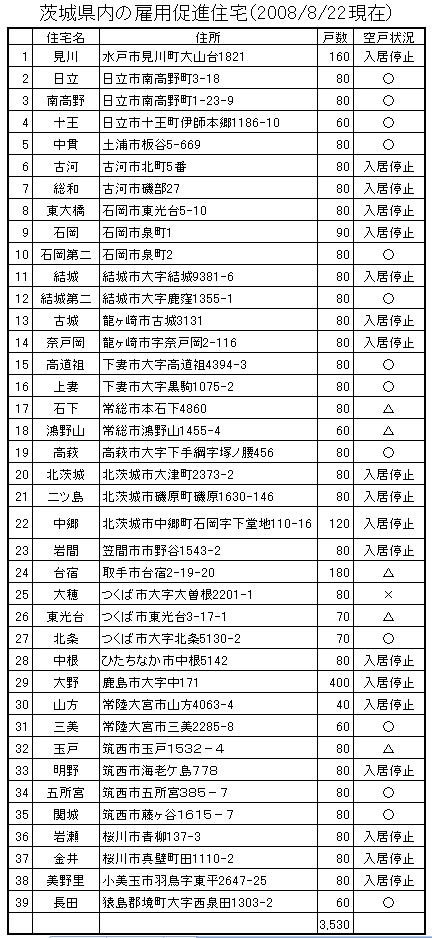雇用促進住宅の半数を平成23年までに売却または廃止
 全国に1532箇所ある雇用促進住宅は、平成34年までに15年間掛けて、売却または廃止されることになっています。そのそも、雇用促進住宅とは、労働者の地域間移動の円滑化を図るため、雇用保険三事業(保険料は事業主負担)の雇用福祉事業により設置された勤労者向け住宅です。現在、独立行政法人雇用・能力開発機構において、1,532住宅、3,838棟(141,722戸)所有されており、。約35万人が居住しています。平成17年12月、「民間事業者等の知見・ノウハウを活用しながら、総収益の最大化を図りつつ、入居者がいることを踏まえた上で、できるだけ早期に事業を廃止すること」という方針が閣議決定されました。これを受けて、平成19年2月、雇用・能力開発機構の「雇用促進住宅管理経営評価会議」で、15年間で雇用促進住宅を譲渡・廃止する旨の方針が決定されました。さらに、平成19年12月に「独立行政法人整理合理化計画」が閣議決定され、「廃止予定住宅数について、平成23年までに全住宅数の2分の1程度を前倒しして廃止決定する」方針が決められました。
全国に1532箇所ある雇用促進住宅は、平成34年までに15年間掛けて、売却または廃止されることになっています。そのそも、雇用促進住宅とは、労働者の地域間移動の円滑化を図るため、雇用保険三事業(保険料は事業主負担)の雇用福祉事業により設置された勤労者向け住宅です。現在、独立行政法人雇用・能力開発機構において、1,532住宅、3,838棟(141,722戸)所有されており、。約35万人が居住しています。平成17年12月、「民間事業者等の知見・ノウハウを活用しながら、総収益の最大化を図りつつ、入居者がいることを踏まえた上で、できるだけ早期に事業を廃止すること」という方針が閣議決定されました。これを受けて、平成19年2月、雇用・能力開発機構の「雇用促進住宅管理経営評価会議」で、15年間で雇用促進住宅を譲渡・廃止する旨の方針が決定されました。さらに、平成19年12月に「独立行政法人整理合理化計画」が閣議決定され、「廃止予定住宅数について、平成23年までに全住宅数の2分の1程度を前倒しして廃止決定する」方針が決められました。
これを受けて、雇用・能力開発機構から、今年5月に、入居者の皆様へということで、突然、退去通知が送られてきた住宅もあります。対象住民にとって、「住む家がなくなる」「立ち退き先の確保が困難」など、悲痛な声が上がっています。
茨城県内には、39団地3,530戸の雇用促進住宅があります。この内すでに、19団地で入居停止(募集停止)の措置が執られています。
こうした状況の中、公明党では、入居者の不安を軽減するために、8月21日、厚生労働省職業安定局に申し入れを行いました。その結果、厚労省として、廃止決定住宅の入居者の退去スケジュールを大幅に見直す方向が打ち出されました。
今年4月までに廃止決定された住宅は784宿舎、戸数で40,632戸(定期借家契約15,118戸、普通借家契約25,514戸)です。
公明党の申し入れで契約解除期間を1年延期
今回の見直しでは、改めて本年度一杯で丁寧な説明会を行い、来年4月から順次、契約解除の手続きに入ることになりました。したがって、20年12月末から契約解除が行われる予定でしたが、1年延ばして21年12月末から契約解除に入ることになります。
この場合、退去困難と認められる事由がある場合、22年11月まで明け渡し期間の猶予措置をとることなどが予定されています。
定期借家契約の場合も、退去困難と認められる事由がある場合は、22年11月末までの新たな契約を結んで、猶予される予定です。 廃止計画そのものを見直すことは、行政改革を進める上で困難ですが、できる限りの柔軟な対応を行なうこととになったものです。
また、改めて、地方公共団体と連携を強化し、入居者への情報提供体制を整備することになりました。
茨城県の場合は、残念ながら雇用促進住宅を県や地元市町村が買い取る計画は全くありません。
(写真は日立市内の雇用促進住宅)