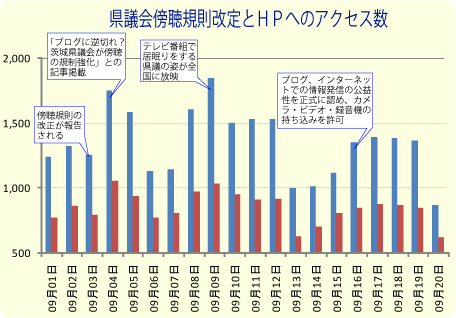11月21日に開催される全国都道府県議長会主催の「第8回都道府県議会議員研究交流大会」の第5分科会『インターネットを活用した議員の情報発信』で、井手よしひろ県議がパネリストを務めることになりました。議員は地域の住民を代表して民意を自治体の行政に反映させると共に、自治体が進める行政の方向性を広く住民に伝える機能も有しています。その意味で、直接の対話や街頭演説やチラシなどでの広宣活動と共に、いわば第3のツールといえるインターネットの活用も重要になってきています。井手県議が、自らのHP「いばらき県政情報・ほっとライン@ひたち」(http://www.y-ide.com)を開設したのは、1996年4月16日。独自ドメインでHPを開設した議員は県議会議員レベルでは誰もいなかったため、それだけで新聞や雑誌の取材対象となりました。早いもので、今年で満12年の歳月が流れました。その間に議員のインターネット活用の状況を大きく変わってきました。今回の発表では、インターネットを活用した議員の情報発信を、自らの体験を踏まえて語ると共に、今日的な話題をもとに現状の問題点に言及してみたいと考えています。
第8回都道府県議会議員研究交流大会
第5分科会『インターネットを活用した議員の情報発信』
第5分科会『インターネットを活用した議員の情報発信』
議員は、住民を代表しその意思を行政運営に反映させるとともに、長の行政執行を監視することが重要な職務である。このため、住民に対し常に県政の状況を周知するとともに、住民との関係を緊密に保つためインターネットを活用したホームページやブログによる情報発信が急速に広がっている。その事例紹介等を行なうとともに、その有効な活用方法について検討する。
【日時】11月21日(金)13時30分~17時50分
【会場】都市センターホテル(東京都千代田区平河町)
【日時】11月21日(金)13時30分~17時50分
【会場】都市センターホテル(東京都千代田区平河町)
「第8回都道府県議会議員研究交流大会」
第5分科会『インターネットを活用した議員の情報発信』用レジュメ原案
議員によるインターネットを活用した
情報発信についての事例報告
私達の議員活動にも、その変化の波は押し寄せてきました。特に、ホームページ(以下HPと記述します)やブログ、電子メールに代表されるインターネット技術の進歩は、一国の政治の動向を左右するほどの大きな力を持つようになってきました。
ホームページを開設して12年。
議員がHPを持てば評価された時代は終わった。
私が自らのHP「いばらき県政情報・ほっとライン@ひたち」(http://www.y-ide.com)を開設したのは、1996年4月16日でした。当時は、地方議員でHPを自前で開設するものはほとんどなく、まして、独自ドメインでHPを開設したのは、県議会議員レベルでは誰もいなかったため、それだけで新聞や雑誌の取材対象となりました。早いもので、今年で満12年の歳月が流れました。その間のアクセスは40万件を突破しました。(2008年10月末現在)
私はHPを作る上で、3つのコンセプトを明確にしました。1.地域の情報(選挙区である日立市や茨城県の情報)に特化する。2.介護保険やさい帯血移植の推進など専門的な話題を、「特集企画」として個別のHPを立ち上げる。3.更新は出来るだけ毎日行う、の3点です。
開設当時、議員が開設するHPは、選挙用のパンフレットを電子化したような作りが一般的でした。トップページは、大きな写真が掲載され、フラッシュなどのソフトで作られた動画が奇抜さを競っていた時期でした。反面、HPの内容は、議員のプロフィールや政策、主な実績、ご意見や要望を受けるメールフォームなど、固定された内容が主体でした。半年に一回更新されれば良いといった程度のHPが大多数を占めていました。
このような政治家のHPが、一般市民から支持を受けることはなく、同僚の議員からも、「高い金を出してHPを作ったが、一日10件のアクセスもない」「パンフレットや名刺にHPのアドレスが書いていないとカッコつかないので開設してみたが、効果はさっぱり上がらない」といった声が聞こえてきました。
しかし、コンセプトを明確にして、地道に作り続けたHPは、それが議員が開設したものであっても、一定のアクセスをいただくことができました。
2000年の介護保険導入に先立って開設した「介護保険を考えるページ」は、議員という立場でいち早く入手した具体的情報を、逐次掲載することで、スタート当初の情報不足とあいまって、1年間で10万件を越えるアクセスを記録しました。
2001年に発生した東海村でのJCO臨界事故の際は、事故発生直後から立ち上げた「臨界事故アーカイブ」には、1時間で1万件以上のアクセスがありました。
いかにしてHPへのアクセス数を増やすか
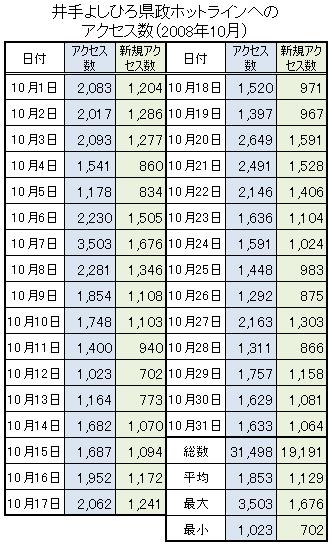 一般的に議員がHPを開設し、運営する場合、自らの名前や政策・実績をどのようにアピールするかを第一に考えます。しかし、こうした発想では、戦略的なHPは運営できないと考えています。
一般的に議員がHPを開設し、運営する場合、自らの名前や政策・実績をどのようにアピールするかを第一に考えます。しかし、こうした発想では、戦略的なHPは運営できないと考えています。
それは、いくら時間やお金をかけて立派なHPを作っても、アクセスしてもらえなければ(見て、読んでもらえなければ)何にもならないからです。
ちなみに、私のHPに一般の有権者がどのようにしてアクセスしてくれるかを分析して見たいと思います。
08年の10月一カ月を分析して見ますと、私のHPに新規にアクセスして来た方の合計5万6161件のうち、64.6%がヤフーやグーグルに代表される検索サイト(検索システム)の検索結果から来訪しています。残りに大半は、他のサイトからのリンクを手繰っての来訪で、名刺などに記入しているHPのアドレスを直接打ち込んで、HPを訪れる人はほとんどいないことがわかります。
また、検索サイトにどのような検索語を入力してやって来たかを見てみると、「井手よしひろ」などという議員名で、検索してくる人は、皆無に等しい現実があります。参考までに、2008年10月一ヶ月の検索語のベストテンは、①さくらシティ日立(476件)、②定額減税とは(258)、③定額減税+年末調整(174)、④不明(161)、⑤イオン土浦(142)、⑥さくらシティ日立+閉店(134)、⑦イーアスつくば+プレオープン(117)、⑧臨時福祉特別給付金(114)、⑨茨城空港(113)、⑩イオン+土浦(111)となっています。
つまり、マスコミなどに頻繁に名前が登場する一部の国会議員などを除いては、HPに記載された内容が検索サイトに登録され、それが一般閲覧者の望む情報と合致した時に、はじめて、HPを見てもらえるということになります。
閲覧者は、ほしい情報を求めて検索サイトから、HPにやってくる。そして、そのHPが自分にとって役に立つ情報や共感できる内容であったとき、HPの作成者に興味を持つ。それが、「井手よしひろ」のHPであることを知って、支持の輪が広がる。この流れがHPを活用した、広報戦略の基本であることを理解しなくてはいけないと思います。
こうしたことに気が付くと不思議にHP作りにも変化が現れました。
一番のポイントは内容の充実や更新頻度を増やすことです。また、いかにして検索サイトから検索されやすくするかという取り組み(SEO)も重要になります。
ブログによる情報発信
さて、こうした観点でHP作りを始めた矢先に登場したのが、ブログというシステムでした。
ブログは、WEB・LOGから派生した言葉とされ、日本語では「簡易ホームページ」などと訳されています。文章や写真などを専用のソフトやエディターなどで書き、インターネット上にアップロードしなくても、常時接続されたインターネット環境で、HPに直接文章を記入していくことにより、誰でも簡単に、いつでも、どこでもHPの新規作成や更新ができるシステムです。専門の知識がなくても数時間で自分のHPが持てるということから、「簡易ホームページ」と呼ばれているようですが、その本質は「簡易」という言葉では表現できない大きな潜在能力を持っています。
繰り返しになりますが、ブログは自宅のパソコンでなくても、インターネットに接続された環境であればどこでも更新ができます。したがって、私は、議会でも、時間調整のための図書館や、インターネット喫茶などでも更新作業を行っています。視察先のビジネスホテルなどは、最も良い更新場所になります。また、電子メールでの更新も可能ですから、携帯電話からメールを打ち、写真を添付すれば立派な画像つきの記事が完成されます。
ブログの特徴の二番目に、ヤフーやグーグルなどの検索システムとの相性が非常に良いということがあります。検索エンジンは登録されているWebページをキーワードに応じて表示します。その際の表示順位はそれぞれのサーチエンジンが独自の方式に則って決定しています。この順位が上にある方が検索エンジン利用者の目につきやすく、訪問者も増えるため、企業などでは検索順位を上げるために様々な試みを行っています。この様々な技術や手法を総称してSEOといっています。
Webページの全文検索を行なって一定のアルゴリズムに従って順位を決定しているロボット型のサーチエンジンでは、そのアルゴリズムを分析することで、特定のキーワードで検索された時に上位に表示されやすいWebページを記述することができます。SEOの知識が全くなくても、ブログでは検索エンジンのアルゴにズムに適合した、検索されやすいホームページを作ることが可能です。
ブログ導入の3つ目のメリットは、ランニングコストがほとんどかからないという点です。国内の主要なブログサービスはほとんどが広告収入で運営されており、使用料は無料です。専用のHP作製ソフトなどの購入も必要がないため、大変安価にインターネットでの情報発信が可能となります。
こうした点を重視し、私は、2004年1月からHPの主要な部分をブログ形式に変更しました(ほっとメール@ひたち・井手よしひろ活動記録BLOG版・http://blog.hitachi-net.jp/)。その結果、一日のアクセス数は平均70から80件であったものが、10倍以上の1000件以上に跳ね上がりました。
ちなみに、10月の実績は総アクセス件数56,161件、一日平均1,812件、一日最高3,503件、最低でも1,023件となっています。
11月10日現在の総アクセス数は1,591,918件となりました。
「長寿医療制度+茨城」や「茨城空港」など話題となっている事をインターネットで調べようとしたら、偶然、井手さんのHPにたどり着いた」などという声を良くいただくようになりました。まさに、これが私のHPのねらいです。更新の簡単さも大いに内容の充実に貢献しています。新規に掲載した記事は、この4年半間で4700件を越えています。
議員のホームページが世論を作る時代に
<事例紹介:茨城県議会での傍聴規則改正問題>
議員のホームページが、テレビや新聞などのマスコミに伍して世論を作るような時代になってきました。この9月、茨城県議会での事例を紹介します。
議会冒頭、9月3日の議会運営委員会で、議長より県議会傍聴規則の改正が表明されました。議長は、インターネットに不適切な写真が載ったことを契機に、セキュリティー強化のため議会傍聴規則の改正を行うとしました。
県議会傍聴規則の改正の概要は、①写真撮影等について、報道関係者又は公益的見地から必要と認められる者であって、撮影等の目的が議会広報に資する場合のみ許可を受けて例外的に認める。②撮影等の許可を受けた方を除き、写真機、ビデオカメラ、録音機等の持ち込みを禁止する。③傍聴を希望する者は、住所、氏名を確認するため、必要に応じ、身分証明書等の提示を求める場合がある。との3点でした。
この傍聴規則の改正には、2つの問題がありました。一つは、傍聴券を必要としない傍聴者を県政記者クラブに加盟するマスコミの記者に限ったことです。従来の規則では、「第4条会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなくてはならない。ただし、報道関係者であって、あらかじめ議長の承認を受けた者はこの限りでない」となっていました。しかし、改正傍聴規則では、現状全てが県政記者クラブ加盟各社の記者であるとして、「報道関係者(県政記者クラブ加盟各社に限る。以下同じ。)」との括弧書きをあえて加えました。マスコミ内にも記者クラブ制度の是非に対して議論がある中で、この改正には課題がありました。
もう一点が、「写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止」の規定です。今までは、「第12条傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない」となっていました。撮影の申請さえすれば、原則許可されてきたわけです。しかし、今回の改正では「第12条傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者又は公益的見地から必要と認められる者であって、議長の許可を得た者については、この限りではない」と改正されました。カメラ、ビデオ、録音機の持ち込みに対して、議長が「公益性」判断をどのようにするのか、大きな問題が残りました。
【インターネット版朝日新聞に「ブログに逆切れ?茨城県議会が傍聴の規制強化」との記事掲載】
この議会運営委員会での傍聴規則の改正が、翌日(9月4日)の朝日新聞と時事通信系のマスコミで報道されました。今回の傍聴規則改正の引き金は、茨城空港を題材に扱ったブログに、常任委員会での無届けで撮影された写真が掲載されたことでした。しかし、このブログには、県議会の本会議で居眠りをしている特定の議員の写真が大きく扱われていたことから、傍聴規則の改正はその写真掲載への対抗措置であるといった報道が広まりました。最初にこの問題を詳細に取り上げた朝日新聞茨城版の記事では、「議会傍聴、規制を強化ブログで批判契機」との見出しを打って報道されました。この記事への反応は、全国的には余り大きくなかったようですが、朝日新聞のインターネット版(asahi.com)が、「ブログに逆切れ?茨城県議会が傍聴の規制強化」との見出しを打ったことで、事態は急変しました。様々なブログで、このニュースは大きく扱われ、2チャンネルではわずか数日で1000件を超える書き込みがありました。
【身分証提示は「まず未来永劫にない」と議長が見直しの発言】
ブログやインターネットでの報道や書き込みが加熱する中で、9月8日の議会運営委員会では、議長が、「6月に開かれた県議会総務企画委員会で、委員長の撮影許可を受けないまま撮影された写真などがインターネットの個人ブログに掲載され、それをキッカケに安全面での規制強化を検討開始した」「今回の傍聴規則の改定は、公開の原則は堅持しなければならないが、セキュリティーとのバランスを考えた結果である」「通常は身分証の提示を求めることは、まず未来永劫にないであろう」などと語りました。議長は、身分証の提示は、明らかに偽名での入場や挙動不審者への例外的な措置であることを強調したものです。
この説明などを受け、8日から改正された新たな傍聴規則の下でも、身分証の提示を求められた事例は一度も起こっていません。
【テレビ番組で居眠りをする県議の姿が全国に放映】
また、このニュースはテレビでもとり上げられました。9月5日には大阪の毎日放送が生番組で取り上げました。8日は、在京のテレビ局3社(TBS、フジテレビ、テレビ朝日)が、県議会に取材に訪れました。翌日(9月9日)の朝のワイドショー番組では、TBSの「朝ズバッ!」とテレビ朝日の「スーパーモーニング」で大きく取り上げられました。「懲りずに居眠りを続ける県議たち」との見出しのテレビ画像は、茨城県議会の負の部分が全国に報道されました。
【茨城県議会:インターネットでの情報発信の公益性を正式に認める】
こうしたマスコミ報道の過熱の中で、私は「ブログやインターネットで、マスコミ以外の方が情報発信することも『公益性がある』と認めて、写真、ビデオ、録音機などの持ち込みを『ブログ、インターネットへの掲載』を理由に許可するべきだ」と強く主張してきました。
こうしたブログでの情報発信に、アクセス数も敏感に反応していました。「ブログに逆切れ?茨城県議会が傍聴の規制強化」との記事が掲載された日には1752件。テレビ番組で居眠りをする県議の姿が全国に放映された日には1850件のアクセスがありました。
議長も、8日には一部インターネットニュースへの取材に対して、ブログ、インターネットの公益性を認める発言を行っており、私は12日の議会運営委員会で、改めて「ブログやインターネットで掲載することを目的にした撮影、録画、録音を認めるのか」と、規則の運用を確認しました。それに対して、議会事務局は「ブログやインターネットも、議会広報の一環として公益性がある」との議長の見解(取意)をもとに、判断すると正式に回答しました。
週明けの16日の常任委員会では、茨城空港に関するブログを掲載しているGさんが、県議会を訪れ委員会の傍聴。その際、「ブログのため」という理由を記した録音機の持ち込みを申請し、許可されました。実際に運用でも、茨城県議会では「ブログやインターネットでの情報発信にも公益性がある」ことが認められました。
この一連の流れの中で、茨城県議会が「ブログやインターネットでの情報発信にも公益性がある」と判断したことは、大きな意義があると思います。結論に至るまでに、一民間人のブログとマスコミのインターネットの記事、そして議員のブログによる情報発信が、大きなテコとなったことは否定できない事実です。
議員のインターネットによる情報発信が、地域や日本全体の世論を大きく動かす時代が、すぐそこにあると確信します。
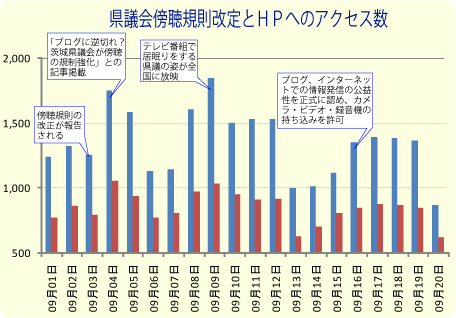
第5分科会『インターネットを活用した議員の情報発信』用レジュメ原案
情報発信についての事例報告
茨城県議会議員井手よしひろ
私共の回りにITという言葉が浸透し初めて久しくなります。コンピュータを中核とするネットワークによって、情報交換の手法や通信、放送の在り方が大きく変わり、ネット通販やネットバンキングなど庶民の生活にも大きな影響を与えています。私達の議員活動にも、その変化の波は押し寄せてきました。特に、ホームページ(以下HPと記述します)やブログ、電子メールに代表されるインターネット技術の進歩は、一国の政治の動向を左右するほどの大きな力を持つようになってきました。
ホームページを開設して12年。
議員がHPを持てば評価された時代は終わった。
私が自らのHP「いばらき県政情報・ほっとライン@ひたち」(http://www.y-ide.com)を開設したのは、1996年4月16日でした。当時は、地方議員でHPを自前で開設するものはほとんどなく、まして、独自ドメインでHPを開設したのは、県議会議員レベルでは誰もいなかったため、それだけで新聞や雑誌の取材対象となりました。早いもので、今年で満12年の歳月が流れました。その間のアクセスは40万件を突破しました。(2008年10月末現在)
私はHPを作る上で、3つのコンセプトを明確にしました。1.地域の情報(選挙区である日立市や茨城県の情報)に特化する。2.介護保険やさい帯血移植の推進など専門的な話題を、「特集企画」として個別のHPを立ち上げる。3.更新は出来るだけ毎日行う、の3点です。
開設当時、議員が開設するHPは、選挙用のパンフレットを電子化したような作りが一般的でした。トップページは、大きな写真が掲載され、フラッシュなどのソフトで作られた動画が奇抜さを競っていた時期でした。反面、HPの内容は、議員のプロフィールや政策、主な実績、ご意見や要望を受けるメールフォームなど、固定された内容が主体でした。半年に一回更新されれば良いといった程度のHPが大多数を占めていました。
このような政治家のHPが、一般市民から支持を受けることはなく、同僚の議員からも、「高い金を出してHPを作ったが、一日10件のアクセスもない」「パンフレットや名刺にHPのアドレスが書いていないとカッコつかないので開設してみたが、効果はさっぱり上がらない」といった声が聞こえてきました。
しかし、コンセプトを明確にして、地道に作り続けたHPは、それが議員が開設したものであっても、一定のアクセスをいただくことができました。
2000年の介護保険導入に先立って開設した「介護保険を考えるページ」は、議員という立場でいち早く入手した具体的情報を、逐次掲載することで、スタート当初の情報不足とあいまって、1年間で10万件を越えるアクセスを記録しました。
2001年に発生した東海村でのJCO臨界事故の際は、事故発生直後から立ち上げた「臨界事故アーカイブ」には、1時間で1万件以上のアクセスがありました。
いかにしてHPへのアクセス数を増やすか
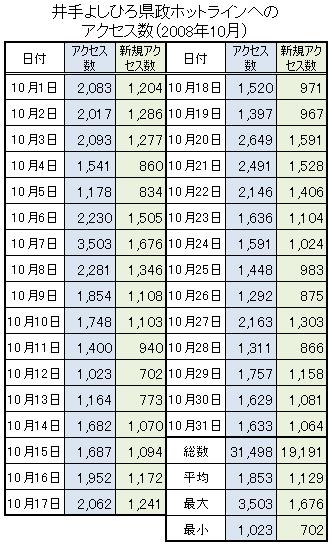 一般的に議員がHPを開設し、運営する場合、自らの名前や政策・実績をどのようにアピールするかを第一に考えます。しかし、こうした発想では、戦略的なHPは運営できないと考えています。
一般的に議員がHPを開設し、運営する場合、自らの名前や政策・実績をどのようにアピールするかを第一に考えます。しかし、こうした発想では、戦略的なHPは運営できないと考えています。それは、いくら時間やお金をかけて立派なHPを作っても、アクセスしてもらえなければ(見て、読んでもらえなければ)何にもならないからです。
ちなみに、私のHPに一般の有権者がどのようにしてアクセスしてくれるかを分析して見たいと思います。
08年の10月一カ月を分析して見ますと、私のHPに新規にアクセスして来た方の合計5万6161件のうち、64.6%がヤフーやグーグルに代表される検索サイト(検索システム)の検索結果から来訪しています。残りに大半は、他のサイトからのリンクを手繰っての来訪で、名刺などに記入しているHPのアドレスを直接打ち込んで、HPを訪れる人はほとんどいないことがわかります。
また、検索サイトにどのような検索語を入力してやって来たかを見てみると、「井手よしひろ」などという議員名で、検索してくる人は、皆無に等しい現実があります。参考までに、2008年10月一ヶ月の検索語のベストテンは、①さくらシティ日立(476件)、②定額減税とは(258)、③定額減税+年末調整(174)、④不明(161)、⑤イオン土浦(142)、⑥さくらシティ日立+閉店(134)、⑦イーアスつくば+プレオープン(117)、⑧臨時福祉特別給付金(114)、⑨茨城空港(113)、⑩イオン+土浦(111)となっています。
つまり、マスコミなどに頻繁に名前が登場する一部の国会議員などを除いては、HPに記載された内容が検索サイトに登録され、それが一般閲覧者の望む情報と合致した時に、はじめて、HPを見てもらえるということになります。
閲覧者は、ほしい情報を求めて検索サイトから、HPにやってくる。そして、そのHPが自分にとって役に立つ情報や共感できる内容であったとき、HPの作成者に興味を持つ。それが、「井手よしひろ」のHPであることを知って、支持の輪が広がる。この流れがHPを活用した、広報戦略の基本であることを理解しなくてはいけないと思います。
こうしたことに気が付くと不思議にHP作りにも変化が現れました。
一番のポイントは内容の充実や更新頻度を増やすことです。また、いかにして検索サイトから検索されやすくするかという取り組み(SEO)も重要になります。
ブログによる情報発信
さて、こうした観点でHP作りを始めた矢先に登場したのが、ブログというシステムでした。
ブログは、WEB・LOGから派生した言葉とされ、日本語では「簡易ホームページ」などと訳されています。文章や写真などを専用のソフトやエディターなどで書き、インターネット上にアップロードしなくても、常時接続されたインターネット環境で、HPに直接文章を記入していくことにより、誰でも簡単に、いつでも、どこでもHPの新規作成や更新ができるシステムです。専門の知識がなくても数時間で自分のHPが持てるということから、「簡易ホームページ」と呼ばれているようですが、その本質は「簡易」という言葉では表現できない大きな潜在能力を持っています。
繰り返しになりますが、ブログは自宅のパソコンでなくても、インターネットに接続された環境であればどこでも更新ができます。したがって、私は、議会でも、時間調整のための図書館や、インターネット喫茶などでも更新作業を行っています。視察先のビジネスホテルなどは、最も良い更新場所になります。また、電子メールでの更新も可能ですから、携帯電話からメールを打ち、写真を添付すれば立派な画像つきの記事が完成されます。
ブログの特徴の二番目に、ヤフーやグーグルなどの検索システムとの相性が非常に良いということがあります。検索エンジンは登録されているWebページをキーワードに応じて表示します。その際の表示順位はそれぞれのサーチエンジンが独自の方式に則って決定しています。この順位が上にある方が検索エンジン利用者の目につきやすく、訪問者も増えるため、企業などでは検索順位を上げるために様々な試みを行っています。この様々な技術や手法を総称してSEOといっています。
Webページの全文検索を行なって一定のアルゴリズムに従って順位を決定しているロボット型のサーチエンジンでは、そのアルゴリズムを分析することで、特定のキーワードで検索された時に上位に表示されやすいWebページを記述することができます。SEOの知識が全くなくても、ブログでは検索エンジンのアルゴにズムに適合した、検索されやすいホームページを作ることが可能です。
ブログ導入の3つ目のメリットは、ランニングコストがほとんどかからないという点です。国内の主要なブログサービスはほとんどが広告収入で運営されており、使用料は無料です。専用のHP作製ソフトなどの購入も必要がないため、大変安価にインターネットでの情報発信が可能となります。
こうした点を重視し、私は、2004年1月からHPの主要な部分をブログ形式に変更しました(ほっとメール@ひたち・井手よしひろ活動記録BLOG版・http://blog.hitachi-net.jp/)。その結果、一日のアクセス数は平均70から80件であったものが、10倍以上の1000件以上に跳ね上がりました。
ちなみに、10月の実績は総アクセス件数56,161件、一日平均1,812件、一日最高3,503件、最低でも1,023件となっています。
11月10日現在の総アクセス数は1,591,918件となりました。
「長寿医療制度+茨城」や「茨城空港」など話題となっている事をインターネットで調べようとしたら、偶然、井手さんのHPにたどり着いた」などという声を良くいただくようになりました。まさに、これが私のHPのねらいです。更新の簡単さも大いに内容の充実に貢献しています。新規に掲載した記事は、この4年半間で4700件を越えています。
議員のホームページが世論を作る時代に
<事例紹介:茨城県議会での傍聴規則改正問題>
議員のホームページが、テレビや新聞などのマスコミに伍して世論を作るような時代になってきました。この9月、茨城県議会での事例を紹介します。
議会冒頭、9月3日の議会運営委員会で、議長より県議会傍聴規則の改正が表明されました。議長は、インターネットに不適切な写真が載ったことを契機に、セキュリティー強化のため議会傍聴規則の改正を行うとしました。
県議会傍聴規則の改正の概要は、①写真撮影等について、報道関係者又は公益的見地から必要と認められる者であって、撮影等の目的が議会広報に資する場合のみ許可を受けて例外的に認める。②撮影等の許可を受けた方を除き、写真機、ビデオカメラ、録音機等の持ち込みを禁止する。③傍聴を希望する者は、住所、氏名を確認するため、必要に応じ、身分証明書等の提示を求める場合がある。との3点でした。
この傍聴規則の改正には、2つの問題がありました。一つは、傍聴券を必要としない傍聴者を県政記者クラブに加盟するマスコミの記者に限ったことです。従来の規則では、「第4条会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなくてはならない。ただし、報道関係者であって、あらかじめ議長の承認を受けた者はこの限りでない」となっていました。しかし、改正傍聴規則では、現状全てが県政記者クラブ加盟各社の記者であるとして、「報道関係者(県政記者クラブ加盟各社に限る。以下同じ。)」との括弧書きをあえて加えました。マスコミ内にも記者クラブ制度の是非に対して議論がある中で、この改正には課題がありました。
もう一点が、「写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止」の規定です。今までは、「第12条傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない」となっていました。撮影の申請さえすれば、原則許可されてきたわけです。しかし、今回の改正では「第12条傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者又は公益的見地から必要と認められる者であって、議長の許可を得た者については、この限りではない」と改正されました。カメラ、ビデオ、録音機の持ち込みに対して、議長が「公益性」判断をどのようにするのか、大きな問題が残りました。
【インターネット版朝日新聞に「ブログに逆切れ?茨城県議会が傍聴の規制強化」との記事掲載】
この議会運営委員会での傍聴規則の改正が、翌日(9月4日)の朝日新聞と時事通信系のマスコミで報道されました。今回の傍聴規則改正の引き金は、茨城空港を題材に扱ったブログに、常任委員会での無届けで撮影された写真が掲載されたことでした。しかし、このブログには、県議会の本会議で居眠りをしている特定の議員の写真が大きく扱われていたことから、傍聴規則の改正はその写真掲載への対抗措置であるといった報道が広まりました。最初にこの問題を詳細に取り上げた朝日新聞茨城版の記事では、「議会傍聴、規制を強化ブログで批判契機」との見出しを打って報道されました。この記事への反応は、全国的には余り大きくなかったようですが、朝日新聞のインターネット版(asahi.com)が、「ブログに逆切れ?茨城県議会が傍聴の規制強化」との見出しを打ったことで、事態は急変しました。様々なブログで、このニュースは大きく扱われ、2チャンネルではわずか数日で1000件を超える書き込みがありました。
【身分証提示は「まず未来永劫にない」と議長が見直しの発言】
ブログやインターネットでの報道や書き込みが加熱する中で、9月8日の議会運営委員会では、議長が、「6月に開かれた県議会総務企画委員会で、委員長の撮影許可を受けないまま撮影された写真などがインターネットの個人ブログに掲載され、それをキッカケに安全面での規制強化を検討開始した」「今回の傍聴規則の改定は、公開の原則は堅持しなければならないが、セキュリティーとのバランスを考えた結果である」「通常は身分証の提示を求めることは、まず未来永劫にないであろう」などと語りました。議長は、身分証の提示は、明らかに偽名での入場や挙動不審者への例外的な措置であることを強調したものです。
この説明などを受け、8日から改正された新たな傍聴規則の下でも、身分証の提示を求められた事例は一度も起こっていません。
【テレビ番組で居眠りをする県議の姿が全国に放映】
また、このニュースはテレビでもとり上げられました。9月5日には大阪の毎日放送が生番組で取り上げました。8日は、在京のテレビ局3社(TBS、フジテレビ、テレビ朝日)が、県議会に取材に訪れました。翌日(9月9日)の朝のワイドショー番組では、TBSの「朝ズバッ!」とテレビ朝日の「スーパーモーニング」で大きく取り上げられました。「懲りずに居眠りを続ける県議たち」との見出しのテレビ画像は、茨城県議会の負の部分が全国に報道されました。
【茨城県議会:インターネットでの情報発信の公益性を正式に認める】
こうしたマスコミ報道の過熱の中で、私は「ブログやインターネットで、マスコミ以外の方が情報発信することも『公益性がある』と認めて、写真、ビデオ、録音機などの持ち込みを『ブログ、インターネットへの掲載』を理由に許可するべきだ」と強く主張してきました。
こうしたブログでの情報発信に、アクセス数も敏感に反応していました。「ブログに逆切れ?茨城県議会が傍聴の規制強化」との記事が掲載された日には1752件。テレビ番組で居眠りをする県議の姿が全国に放映された日には1850件のアクセスがありました。
議長も、8日には一部インターネットニュースへの取材に対して、ブログ、インターネットの公益性を認める発言を行っており、私は12日の議会運営委員会で、改めて「ブログやインターネットで掲載することを目的にした撮影、録画、録音を認めるのか」と、規則の運用を確認しました。それに対して、議会事務局は「ブログやインターネットも、議会広報の一環として公益性がある」との議長の見解(取意)をもとに、判断すると正式に回答しました。
週明けの16日の常任委員会では、茨城空港に関するブログを掲載しているGさんが、県議会を訪れ委員会の傍聴。その際、「ブログのため」という理由を記した録音機の持ち込みを申請し、許可されました。実際に運用でも、茨城県議会では「ブログやインターネットでの情報発信にも公益性がある」ことが認められました。
この一連の流れの中で、茨城県議会が「ブログやインターネットでの情報発信にも公益性がある」と判断したことは、大きな意義があると思います。結論に至るまでに、一民間人のブログとマスコミのインターネットの記事、そして議員のブログによる情報発信が、大きなテコとなったことは否定できない事実です。
議員のインターネットによる情報発信が、地域や日本全体の世論を大きく動かす時代が、すぐそこにあると確信します。