与党、「定額給付金」を決定 1人1万2000円、下限は1800万円
産経新聞(2008/11/12)
政府の追加経済対策の目玉となる総額2兆円の生活支援定額給付金をめぐり、自民、公明両党の幹事長、政調会長らは12日午前、都内のホテルで協議し、給付金額を1人当たり1万2000円、18歳以下と65歳以上には8000円を加算することで合意した。懸案となっていた所得制限に関して、各自治体が実情に応じて判断することにし、制限する場合は所得1800万円(給与収入概算2074万円)を下限とすることを決めた。
名称について、自民党内に「『給付』では『お上が恵んでやる』との印象がある」との声があったが、最終的に「定額給付金」とすることが決まった。
与党合意では、所得制限については、各市町村がそれぞれの実情に応じて交付要綱を作成し、制限するかどうかを決めることにした。所得制限を設定した市町村では、返還された給付金を関連事務経費に充てることができるようにした。また、制限の対象となる所得とは、収入から必要経費を控除した後の金額とすることを確認した。
今回の与党合意を踏まえ、政府は総務省に設置された「生活支援定額給付金実施本部」が中心となり、市町村での具体的な支給方法など詰めの作業を急ぐ。<以下略>
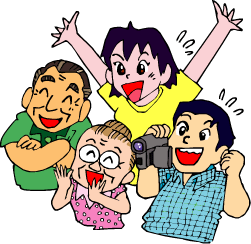 公明党の主張していた「定額減税」はもともと「納めていただいた税金のうち、定額を全世帯に戻しますよ」ということであり、当初から「全世帯」を支給対象に考えられていたものです。さらに、所得が課税限度以下で減税効果の及ばない方には、臨時福祉特別給付金などを検討していました。
公明党の主張していた「定額減税」はもともと「納めていただいた税金のうち、定額を全世帯に戻しますよ」ということであり、当初から「全世帯」を支給対象に考えられていたものです。さらに、所得が課税限度以下で減税効果の及ばない方には、臨時福祉特別給付金などを検討していました。
ただし、この定額減税と臨時福祉特別給付金のセットでは、実際にその減税の果実を実感してもらいためには、大きなタイムラグが生じてしまいます。緊急の経済対策としては、効果が限定的だとの意見から、この「定額給付」へ舵を切ったものです。 財源を赤字国債に求めず、特別会計の準備金を財源に充てるわけですから、「景気が減速する中で『景気対策』『生活支援』のために、『国民の皆さんに納めていただいた税金の一部を還付する』ことになるわけです。
その意味では、現場第一主義で、一番確実で手間のかからない方法で支給することが大切だと思います。実際の支給を担当する市町村が、昨日の全国市長会会長の発言のように、所得制限が事務処理手続き上困難であれば、所得制限を行わずに支給すればよいわけです。ここには、市町村の首長と議会の判断も必要になります。国民目線での判断が問われます。
この定額給付には、一部マスコミから的外れな批判が寄せられています。
毎日新聞は、12日付の「定額給付金 支離滅裂な施策はやめよ」との社説で、「政策目的が不明確で、効果も疑わしく、財政にも負担をかけるような定額給付金は白紙に戻すべきだ。生活対策というのならば、低所得層などに対象を絞った減税や、大胆な非正規雇用対策を講ずるのが責任ある政治の務めではないのか」と主張しました。『低所得層などに対象を絞った減税』とは具体的にどのようなイメージを毎日新聞は抱いているかまったくわかりません。所得の補足が難しいこと、課税最低限以下での生活をしている方への支援をどのように行うか、どのようにして時機を逸せずタイムリーに経済対策を実施するか、このような視点で「定額給付」という結論に至ったわけです。まさに毎日新聞の社説こそ「支離滅裂」な主張に他なりません。
定額給付の議論は、生活感が乏しい机上の議論であってはいけないと思います。今後は、具体的な補正予算案の提出、国会での審議という次のステップに議論は移っていきます。この臨時国会での二次補正の提出、成立は野党民主党の反対もあり、難しい状況になっています。
なぜならば、国会法により1月には通常国会を開会しなくてはいけません。したがって、この臨時国会の会期はどんなに延長しても、最大75日程度です。補正予算を具体的に組み上げて衆院を通し、参院で民主党の関連法案の審議引き伸ばしを受けるとする60日以上の審議時間が必要になるわけですので、物理的に臨時国会での成立は不可能ということになります。
政府与党は、1月の通常国会冒頭にこの補正予算を衆院で可決させ、総選挙での国民の審判を受けることなしには、3月末までに、この補正予算を実施することができなくなっています(その後市町村議会での支給法の条例審議も必要になります)。
民主党の対応如何で、自民・公明の与党は、この定額給付金を含む緊急経済対策の是非をもって、総選挙での審判を仰ぐと腹を決める必要があると決意を新たにしています。



