国会では定額給付金の話題ともに、製造業への派遣を禁止するかどうかが、大きな問題としてクローズアップされています。
2004年に製造業へも派遣が自由化され、昨年秋以降、輸出関連の製造業を中心とする業績不振から、大量の派遣社員が解雇され問題となっています。
このような状況に対して、民主党など野党は、製造業への派遣を禁止する法案を今国会に提出する方針です。
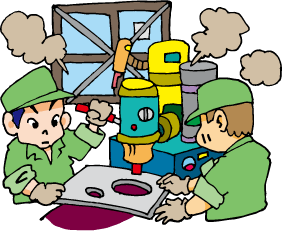 民主、社民、国民新三党は昨年12月、参院に提出した雇用対策4法案(廃案)で、派遣を含めた有期雇用自体を「臨時的・一時的な業務は3年」「専門的知識を有する労働は5年」などと、厳しく期間を限定する方針を打ち出しています。契約更新の際に経営側の都合だけで更新拒否はできなくする厳格な内容です。
民主、社民、国民新三党は昨年12月、参院に提出した雇用対策4法案(廃案)で、派遣を含めた有期雇用自体を「臨時的・一時的な業務は3年」「専門的知識を有する労働は5年」などと、厳しく期間を限定する方針を打ち出しています。契約更新の際に経営側の都合だけで更新拒否はできなくする厳格な内容です。
これが実現すれば、企業にとっては、今のように「雇用の調整弁」として派遣を雇うことはできなくなります。派遣労働は、原則自由化された1999年の前に戻る可能性が高く、契約社員のような有期契約の直接雇用も制限される見込みです。
民主党の小沢一郎代表は「終身雇用は一つの安全網だ。その下支えを前提とした、日本的な資本主義の在り方を世界に発信したい」(産経新聞の記事より)と明言しています。
それに対して、政府与党はまるで反対の立場です。「経済が低迷しているときに、有期雇用に制限を加えると、より雇用自体に慎重になり、雇用環境の改善にはつながらない」との考えです。
まず安定的な雇用を確保すれば、消費が拡大し企業経営も良くなるという野党の主張。企業経営が上向くことによって雇用が増大し、消費も増えるという与党の主張。これでは、卵が先か鶏が先かとの水掛け論になってしまいます。
さて、派遣労働に関する基本的な考えをまとめてみたいと思います。
- 企業は派遣労働者の変わりに請負業から労働者を入れ、期間工や季節工と言われる労働者に取って代わることになるでしょう。
- 請負業はこれを取り締まる法律も存在しません。下請けとして働く労働者の賃金や労働条件が向上するわけではなく、派遣労働者が請負労働者になるだけであって、これが大きな問題となります。
- 問題は下請けで働く労働者の労働条件を向上させることであり、そのための法律改正が必要になります。
- 現在の派遣法には派遣元事業主や派遣先企業の守らなければならないことが、指針として示されており、「派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに期すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連企業での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係わる派遣労働者の新たな就業機会の確立を図ること」等記されています。ただし、指針として書かれているので、より拘束力の強い法律の中に書き込むことが必要です。
- そこで、派遣業を行うものの許可条件を厳しくし、派遣元のマージン率に上限を設けることも必要になるのではないでしょうか(現在の平均値は31.2%もあります。これを2割程度に引き下げるべきです)。
- 派遣労働を解雇になった場合の安全ネットを明確にする必要です。労働期間にもよるが2~3ヶ月の賃金を受けさせることや労働、社会保険の保障を徹底する必要があります。
派遣規制緩和、見直し浮上 欠かせぬ「功罪」論議
産経新聞(2009.1.8)
派遣社員の雇用問題が深刻化する中、派遣労働に対する規制強化が春闘や国会の争点に浮上してきた。舛添要一厚生労働相が個人的としながらも製造業への派遣禁止の考えを示し、民主党も禁止の検討を始めた。日本経団連など経営側は「労使の間で議論していく」との立場を表明している。ただ一連の動きは、雇用機会の拡大や働き方の多様化、企業の国際競争力の強化を目指してきた規制緩和の後退につながる。派遣労働の見直しには、規制緩和の“功罪”を踏まえた論議が欠かせない。
■罪
年末の日比谷公園に開設された「年越し派遣村」。入村者は、最終的に約500人に膨れ上がり、雇用不安の“象徴”として年末年始のニュースで大きく報じられた。
厚生労働省によると、平成19年度の製造業への派遣社員は46万人に上り、全労働者に占める派遣を中心とした非正規社員の割合は38%に達している。小泉純一郎政権時代の構造改革の一環として進められた労働者派遣法改正による規制緩和が、派遣社員の増加を加速させた。
しかし、急激な景気悪化で企業の“派遣切り”が相次ぎ、同省の調査では、3月までに職を失う非正規社員は約8万5000人に達する見通しだ。
派遣契約は、派遣会社と派遣先企業の間の商取引のため、契約期間が終わり更新されない場合も、派遣会社は受け入れざるを得ない。さらに、「派遣先企業の立場が強いうえ、罰則規定がないため、契約の中途解除も多い」(業界関係者)という。
景気後退局面では、こうした不安定な雇用形態にある派遣社員にしわ寄せが集まる事態は当然、予想されていた。それだけに、「拙速に製造業派遣を解禁したツケが回ってきた」との批判が高まり、規制強化論につながっている。
■功
だが、派遣労働の規制緩和は、労使双方に大きな恩恵をもたらした。
日本商工会議所の岡村正会頭は「雇用の需給調整が可能となり、働き方の多様化にもつながった」と指摘。経済同友会の桜井正光代表幹事は「経営の柔軟性が高まった」と強調する。
グローバル化が加速するなか、日本企業は人件費の安い新興国企業との競争力を確保することが重要な経営課題になっている。人件費が高い日本では、生産の増減に応じて労働力を調整し、コスト削減を図る必要があり、派遣労働力のメリットは大きい。
労働者にとっても、派遣対象業種が増えれば、それだけ雇用機会が増えることにもなる。「規制緩和が進んだことで、日本の失業率が欧米に比べても低い4~5%台で推移している」(民間エコノミスト)との指摘もある。
日本経団連の幹部が「製造業派遣が禁止されれば、日本の製造業は今以上に海外に生産拠点を移す」と指摘するように、規制強化が、逆に正社員を含めた国内の雇用の一段の悪化を招く懸念は大きい。
ただ、規制強化に反対する経営側にも「派遣法改正の際に、不況時を想定した制度設計を行わなかったことは問題」との声が出ている。労使と政官が一体となって派遣社員のセーフティーネット(安全網)を整備することが急務だ。
電機連合委員長、製造業派遣禁止論議「結論急ぐな」
朝日新聞(2009/1/9)
電機メーカーの労働組合でつくる電機連合の中村正武委員長は9日、春闘前に労使が議論する「労使フォーラム」の講演で、「製造業派遣を禁止すべきだという論議があるが、性急な結論は出すべきではない」として、派遣禁止に反対する姿勢を示した。
上部団体の連合の高木剛会長は5日、「製造業派遣には問題がある」と禁止を求める立場を示しており、労働界の意見が割れていることが浮き彫りとなった形だ。
中村委員長は「製造業の派遣社員でも多様な働き方を求めている人が大勢いる。労組としても尊重すべきだ」と話し、正社員との処遇の格差是正、セーフティーネット(安全網)整備などを政労使で論議する必要性を訴えた。




労働行政を狂わす厚生労働省
厚生労働省調査結果の「数値(第3回:09/1/26時点)」が公表されました。それによると、非正規労働者削減人数(08年10月~09年3月)は12万4,802人に上るとのことです。先日(1/27)、派遣・請負の業界団体(加盟120社)によるヒアリング結果数値で「約40万人」と発表された直後だけに、今回も厚労省公表数値は「実態」との乖離が大きいのを否めません。厚労省調査結果の過小数値を非難するのみならず、この「過小数値公表の意義」が問われるものと思います。前記のとおり、民間団体が約40万人と現実的試算をしているにもかかわらず、厚労省が「中途半端な後追い数値」公表に止どまっているようでは、国の雇用対策が大幅に遅れるばかりです。詳細は、★「人事総務部」-ブログ&リンク集-の1/28日付記事:「厚生労働省の失政(人災)」をご参照ください。
株式会社OS総研
野々垣勝
名古屋市中村区名駅2-28-3
tel052-588-9930