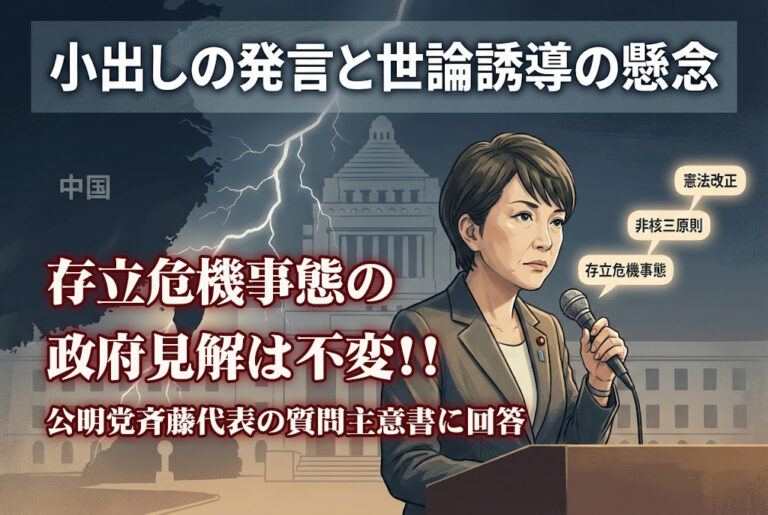12月6日午前、井手よしひろ県議らは、県内の農商工連携のモデルケースとして、ひたちなか市の「幸田商店」(鬼澤宏幸社長)を訪ね、茨城の特産品「干しイモ」を中心とした地域活性化の実例を視察しました。この視察調査には、党農林水産部会長の石田祝稔衆院議員、県本部代表・石井啓一衆院議員、たかさき進県議の他、地元ひたちなか市の市議会議員が参加しました。
12月6日午前、井手よしひろ県議らは、県内の農商工連携のモデルケースとして、ひたちなか市の「幸田商店」(鬼澤宏幸社長)を訪ね、茨城の特産品「干しイモ」を中心とした地域活性化の実例を視察しました。この視察調査には、党農林水産部会長の石田祝稔衆院議員、県本部代表・石井啓一衆院議員、たかさき進県議の他、地元ひたちなか市の市議会議員が参加しました。
茨城県の2007年の干しイモ産出額は69億円で、全国の98%を占めています。中でもひたちなか市は県全体の7割以上を占める最大の産地となっています。産出額はここ数年増えているものの、農家の高齢化が進み、生産者の減少や後継者不足が懸念されています。
こうした環境の中、10年前「幸田商店」の社長に就任した鬼澤宏幸社長は、「干しイモの購買層が中高年の女性に偏っていたことに危機感を持った」。年間を通じ、手軽でおいしい「健康なおやつ」として、低価格品を開発。ドラッグストア向きに販売を始めると、健康志向と重なって若い女性からの支持が爆発的に広がりました。 低価格は中国産の干しイモを輸入することで実現。自ら中国中を訪ね歩き、最適品種を発見し、世界で唯一のハサップを取得した干し芋工場で加工し、日本に輸入しています。角切りや焼いたもの、一口サイズ、ホワイトチョコで包んだものなど種類は豊富です。パッケージも若年層を意識。中国産干し芋の国内シェアを一気に高めました。
低価格は中国産の干しイモを輸入することで実現。自ら中国中を訪ね歩き、最適品種を発見し、世界で唯一のハサップを取得した干し芋工場で加工し、日本に輸入しています。角切りや焼いたもの、一口サイズ、ホワイトチョコで包んだものなど種類は豊富です。パッケージも若年層を意識。中国産干し芋の国内シェアを一気に高めました。
中国からの輸入を初めて、日本産の干しイモのすばらしさを再確認。徹底的に国産にこだわり、手作りの芸術品を作るような気持ちで世に出したのが「べっ甲ほしいも」でした。干し芋の一般的品種「タマユタカ」ではなく、希少品種「泉」を使うことで、独特の甘みや輝き、やわらかさを持った高級干し芋として、生産が間に合わないほど大ヒット商品になりました。
さらに、干しイモを加工、販売する幸田商店、農業生産法人の照沼勝一商店、木内酒造の3社と、ひたちなか商工会議所は、農商工連携などで干しイモの活用や消費拡大に取り組んむ、「ほしいも学校」を今年5月に設立しました。
7月には、ひたちなかテクノセンターで関係者約140人を集めたシンポジウムを開催しました。講演したグラフィックデザイナーの佐藤卓氏は、干しイモに関連するあらゆる要素を「解剖」することを提言。歴史や文化の現状、「解剖」による干しイモの分析、“ねちゃっ”とした食感など干しイモの特徴をとりまとま、年明けに出版を予定しています。今後は、3社で新商品の開発に取り組み、「ほしいも学校」のブランド名で売り込む計画です。
この「ほしいも学校」には、特産物を見直すことで地域の魅力を再認識し、ブランド価値を向上させるという攻めの側面と、地域の伝統を若い世代に引き継ぐという守りの側面があります。「ほしいも学校」には、地域から大きな注目が寄せられています。
視察では、鬼澤社長の地場の特産物を使って、新たな魅力を発見し、多くの消費者に喜んでもらおうという熱い心情に、大いに共感しました。こうした情熱が農業や地域活性化の新たな可能性をひらくと確信しました。
(写真上:「べっ甲ほしいも」の製造工程を視察する公明党の議員団、写真下:幸田商店の鬼澤宏幸社長)
 参考:幸田商店のHP
参考:幸田商店のHP