街角アンケートに7万6689人の回答
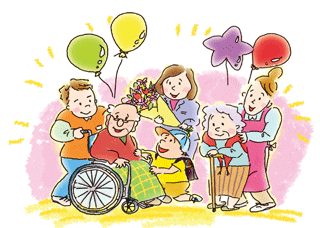 公明党は全国3000人を超える全議員が一丸となって、誰もが長寿を喜び、安心して暮らせる社会の実現に向けて、昨年(2009年)11月から12月にかけて介護現場の生の声を聞き、新たな政策の立案にむけて「介護総点検」に取り組みました。
公明党は全国3000人を超える全議員が一丸となって、誰もが長寿を喜び、安心して暮らせる社会の実現に向けて、昨年(2009年)11月から12月にかけて介護現場の生の声を聞き、新たな政策の立案にむけて「介護総点検」に取り組みました。
日本は今、世界に類を見ないスピードで超高齢社会に突入しています。15年後の2025年には、65歳以上の高齢者人口が3600万人(高齢化率30%)を超えるとされており、それに備えて、介護保険の抜本的な改革が急務となっています。
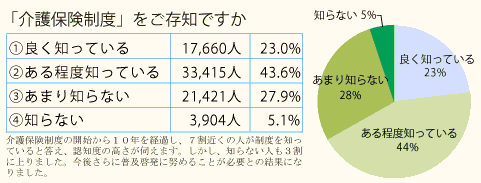
今回の介護問題総点検では「街角でのアンケート調査」を行いました。全国で7万6689人もの市民の皆様からお答えを寄せていただきました。そのほかにも、6265件の介護サービス利用者や家族の方、4587件の介護事業者の方、1万1286件の介護従事者の方、さらには全国市区町村の65%に当たる自治体(茨城県では44市町村すべて)からも回答が得られ、多角的に介護の現場の声を伺うことができました。改めて、ご協力いただいた皆様に、この場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。大変にありがとうございました。
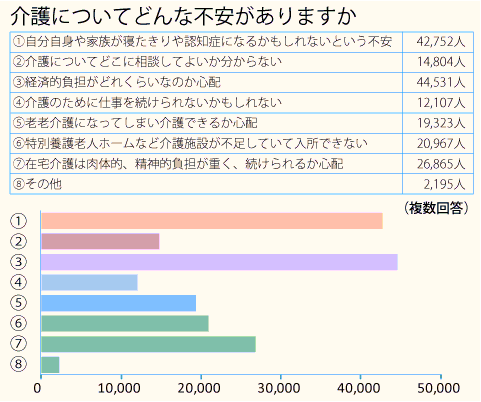
調査結果から介護現場が抱える様々な問題点が明らかとなりました。例えば、街角アンケートの結果では、「介護を受けたい場所は?」との問いに対して「入所系の介護施設」と回答された方が45.8%に対して、「自宅」が良いとされた方が42.3%と、共に高い比率でした。高齢者の中にも入所施設への期待が高く、抵抗感なく受け入れられている実態が浮彫りになりました。
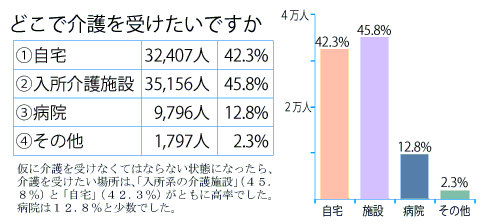
また、介護従事者の調査では7割の人が今後も仕事を続けたいと望んでいる事も分かりました。しかし、その一方で離職する人も多く、8割の離職者が「収入が低い」「心身の負担が大きい」と感じていることも明らかになりました。
公明党はこうした調査結果を基に、1月8日には山口代表が「安心して老後を暮らせる社会」の実現をめざして介護に関する提言を行ないました。
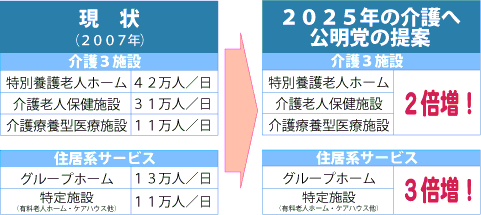
提言の柱は5つあります。1点目は、介護施設の整備が追いつかず、入所できない高齢者が増加している現状を踏まえ、2025年までに施設待機者の解消を目指します。具体的には、介護3施設といわれる特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の倍増と、有料老人ホームなどの特定施設、グループホームの3倍増を目指します。
2点目は、訪問介護サービスを大幅に拡充させ、24時間365日利用できる体制を整えます。住み慣れたわが家で介護を受け続けたいと希望している高齢者の方々も多くいらっしゃいます。厚労省の国民生活基礎調査(2007年)によると、要介護者と同居している家族のうち、介護者側の年齢が60歳を越えた比率は58.6%です。また、65歳以上の高齢者が高齢者を介護する“老老介護”世帯も全世帯の半数を超えたといわれています。高齢者が安心して自宅で、いつでも介護サービスが受けられるよう、公明党は在宅介護支援の大幅拡充を行います。
3点目は「介護保険制度の抜本的な基盤整備」です。まず現場の介護従事者の重い負担になっている保険手続きなど煩雑な事務処理の仕分けを行い、手続きを簡素化させます。また「時間がかかりすぎる」との声が多い、要介護認定審査の簡略化ですぐ使える制度に転換します。
4点目は、低賃金や厳しい労働環境におかれている介護従事者の待遇改善、大幅給料アップなどにつながる介護報酬の引き上げを行ないます。と同時に、5点目として、介護保険料上昇を抑制するために公費負担割合を5割から当面6割に引き上げ、2025年には介護保険の3分の2を公費で賄うようにします。
こうした公明党の総点検や提言に対して多くの方々から賛同の声が寄せられています。「高齢社会をよくする女性の会」で理事長を務める樋口恵子さんは「少子高齢化社会に直面する日本の将来像の基礎を設計する上でも非常に大事な資料」と語り、「3000人を超える議員ネットワークがある公明党ならではの取り組み」と評価してくださいました。
「調査なくして発言なし」とは、公明党の原点です。1月22日に行われた衆議院予算委員会において、公明党の井上幹事長は、介護総点検の結果を基に介護現場の窮状を訴えるとともに、課題解決への具体的な提案を示し、政府の対応を強くただし、政府から前向きな答弁も引き出しています。
公明党は皆様から寄せられたご意見をもとに、政策提言に役立て、国会だけでなく地方議会でも介護問題の改善に取り組んでまいります。現在、さらに詳細な 結果の分析をしており3月中旬には、さらに詳細な結果を公表する予定です。
また、その内容も反映させて公明党の新介護プラン(仮称「新介護ゴールドプラン」)をまとめ、介護保険制度の改善に活かして行く方針です。
 参考:介護保険総点検の結果をお知らせする井手よしひろ県政ホットライン
参考:介護保険総点検の結果をお知らせする井手よしひろ県政ホットライン
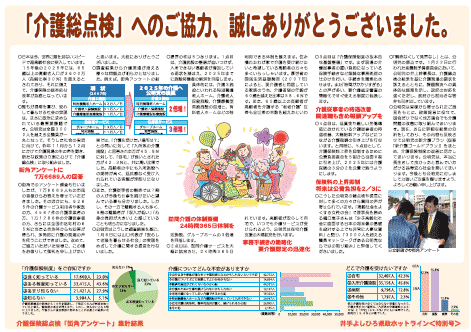



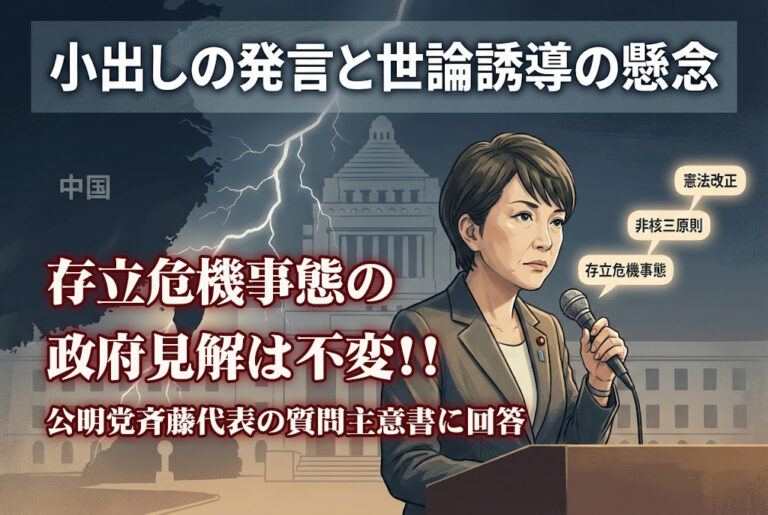
8
●行政のバックアップ
▼長野亮アナ「行政のバックアップで考えてみるといかかですか?」
▼高橋紘士教授「先ずは、新しく入ってきた人を支えるような仕組み、定着を見届けていけるような仕組み。言うまでもなく、介護報酬、賃金できちんと評価する。
もう一つは、とても大事だと思っているんですが、
『良い仕事をした所(施設)を評価する(介護報酬を増やす)。「単に寝かせきりにして収益を上げる」んじゃなくて、「改善努力に対してして収益が上がる」ような介護報酬を考えていく』。
これがとっても大事だと思います」
▼長野亮アナ「どんな人でも必ず歳を重ねるわけですから、介護の現場の問題は、いま起きていることであることと同時に、将来に向けての課題でもあるのではないのでしょうか」
7
▼長野亮アナ「表情と言いましょうか、利用者と介護職員の双方の笑顔を見てると、これが理想的な介護なんだなぁと思ってしまいます」
▼高橋紘士教授「『かけがえのない仕事をしている』ってことを実感しますよね。
こちらの新生会は全国的に大変有名だし、レベルの高い所ですが、
『実は、いろんな所でこういう努力は始まっています。そういう所では、離職率は決して高くない。
しっかりとした事業経営プランを持てば、離職率は下げられるんです』」
▼長野アナ「先ほどおっしゃっていた専門性は、こういった活かされ方をするのかなぁと、見てて私なんか思いました」
▼高橋教授「『目標を立てて支援するという考え方。お世話ではありません。自立支援』。
そして、それに悩んだ時はサポートする専門職は揃っていますから、『自信を持って仕事ができる。それは“やりがい”に繋がるわけですよね』」
▼長野アナ「ですから、『介護職員の目標は利用者の目標でもある』わけですよね?
介護職員の目標はイコール、お年寄りの方がどう回復していくか、どういう暮らしをするかという所に繋がっていくと」
▼高橋教授「おっしゃる通りです。それが、介護事業の醍醐味だと思います」
6
●“やりがい”が定着のカギ…専門性を活かす
■「社会福祉法人・新生会」(岐阜県池田町)
離職率は6.5%。『設立されて30年間、深刻な人手不足に陥ったことはない』。
■この施設が力を入れているのが、《介護による利用者の機能の改善》。
寝たきりだった人が身体を起こせるようになったり、認知症などでコミュニケーションがとれなかった人がとれるようになったりするなど、
『介護によって(利用者の)状態が良くなることが、職員のやりがいになっている』。
◆「最前線で働く」看護職員を支援する仕組み
介護職員=利用者
↓作成
介護プラン
↑意見
医師・看護士・作業療法士・言語聴覚士など
■この施設では、利用者一人一人に対して、対応する介護職員を決め、機能改善に向けた責任者とする。
介護職員は先ず、担当する人の介護プランを作る。
さらに、その職員が中心になってミーティングを開き、専門の医師や看護士、作業療法士、言語聴覚士などに意見を求める。
『最前線で働く』看護職員を支援する仕組み。
介護によって利用者の機能が改善した事例は、担当の職員が年に一度の発表会で報告する。
「こうした成功事例を共有する」ことが、職員全体の意欲向上に結びついている。
5
◆好循環「介護職員の増員 →介護の質の向上 →利用者の増加 →収益アップ →介護職員の増員」
■悪循環を断ち切るために、あえて介護職員を増やした。
すると、利用者と向き合う時間が増え、介護の質が向上。施設の評判は高まり、利用者が増える。その結果、収益がアップし、さらに介護職員を増やした。
これを繰り返すことで、『当初25%もあった離職率は5%にまで低下』。
◆ロングバケーション制度
▽満2年以上勤務…14日間 ▽満2年未満勤務…10日間
■良い循環が生まれたことで、待遇面の改善も進んだ。
こうした施設では珍しい「連続休暇制度」や「資格取得支援制度」を作った。
◆「『収入に限りがある時に、待遇を良くする』。待遇は総合的なもの。
給料だけじゃなくて、研修であったり、休みであったり、社会的な評価だったり、色々な面があって処遇や待遇が決められる」
by 妹尾弘幸 (株)QOLサービス・社長
4
●“ゆとり”が生む好循環…ホワイトカラーを削減し、中核の仕事である介護職員を増やす
■『介護の職場にどうやって人材を定着させていくか』
成果をあげている施設を取材した。
「(株)QOLサービス(広島県福山市)」。『この施設は、「(事務職や管理職を減らし、その分)介護に当たる職員を増やし、ゆとりを生み出す」ことで離職率を低下させた』。
◆「利用者:介護職員=3:1 → 2:1」 これにより離職率は25%→ 5%に低下
■当初は、「3人の利用者に1人の介護職員」を配置していた。それを、「利用者2人につき1人」へと手厚くし、『その分、事務職や管理職を減らした』。
介護職員を増やした背景には、退職者が相次いだ過去の苦い経験がある。
施設を立ち上げた最初の1年間で22人を雇ったが、8人が辞めた。
3
(司会:「専門性が評価されない」とは?)
『この調査は資格を取られた方ですから、「資格を持っているのに、活かされないような職場じゃないのか」とお感じになる』。
どうも、「介護とは家族がやっておられたお世話の代わりだ」という、そんなイメージで、事業者も実は一部そんな考え方をしている。
(司会:一般的にもそう思ってらっしゃる方が多いかもしれない)
そうじゃなくて、(介護は)プロの仕事なんです、本来は。看護とか医療とかと同じようにプロの仕事であるべきなのに。それをきちんと社会的にも、実は給与面でも評価されていない。
(司会:家族の代わりにするのではなくて、『家族だから出来ない部分、プロだからこそやれる部分が相当数ある』ということを認識しないといけない?)
おっしゃる通りですね。
(司会:なるほど。ですから、労働条件の部分もあるんでしょうけど、やはり『精神的な部分にも影響を及ぼす』とこがありそうですね)
2
■なぜ解決しないのか人手不足…解決のヒントは辞める3大理由に
◆離職率…21.6% 産業平均…15.4%
◆介護の資格保有者を対象にした、辞めた理由[厚労省]
▽給与等の労働条件が悪い…32%
▽仕事の内容がキツイ…25%
▽専門性が評価されない…10%
◆介護福祉士養成学校・定員充足率[厚生労働省]
▽2006年度…71.8% ▽2007年度…64.0% ▽2008年度…45.8%
介護職場が抱える問題が浮かび上がる。この3大理由に解決のヒントがある。
◆ by 高橋紘士・立教大学・大学院教授 介護政策が専門
(司会:離職率が高く20%を超えている介護職ですけども、その理由が3つ出ていましたが、こうしてご覧になっていかがですか?)
『「給与の問題」と「仕事の内容のキツさ」は、実は同じこと』なんですよね。
『「仕事の内容に比べると、どうも給与がそれほどではない」とそういう感じをお持ちになったから』、こういう数字(辞める3大理由)が出たんだと思う。
やっぱし大事なのは、中核となって働く方の給与、これは生活をきちんと支えるだけの必要な額を保証しないといけません。ここはちょっと課題ですね。
1
★しっかりとした事業経営プランを持っている事業者では、離職率は低い
■参考 「人手不足からの脱出なるか~模索する介護現場~」[NHKナビゲーション 2009/06/05]
◆これから必要な介護職員[厚労省]
▽介護が必要な高齢者:2006年…440万人 → 2014年…640万人
▽介護職員:2006年…117万人 → 2014年…160万人
■求職者は増えたが…
社会福祉法人・太陽の里(三重県松阪市)の場合
不況の影響で08年11月以降、求職者は多くなった。これまでに70人の面接をした。今までは月に2・3人だったが、今はほぼ毎日面接をしている。
しかし、施設側の悩みは、『面接で仕事の内容(おむつ交換など腰を屈める作業、会話が成り立たない認知症利用者)を詳しく説明すると、辞退する人が多い』こと。
そのため、採用に至ったのは14人。「介護の仕事ならすぐに働ける(はず)」と安易な気持ちで来る人が多い。