 3月19日、公明党茨城県本部(代表:石井啓一衆院議員、幹事長:井手よしひろ県議)では、2月はじめから約40日間行った「農家の戸別所得補償制度に関するアンケート調査」の結果を、県庁内の県政記者クラブで記者会見し発表しました。
3月19日、公明党茨城県本部(代表:石井啓一衆院議員、幹事長:井手よしひろ県議)では、2月はじめから約40日間行った「農家の戸別所得補償制度に関するアンケート調査」の結果を、県庁内の県政記者クラブで記者会見し発表しました。
調査方法:公明党茨城県本部所属議員の面接による聞き取り調査
調査期間:2010年2月1日~3月6日
有効回答:540人(67.1%)
鳩山政権が進める農家の戸別補償制度は、2つの柱から成り立っています。一つは、コメの生産調整に協力した販売農家に対し、生産費と販売価格の差額を補てんする米戸別所得補償モデル事業(米のモデル事業)です。もう一つが、水田で大豆や麦、米粉・飼料用米を生産する販売農家を対象にした「水田利活用自給力向上事業」(自給率向上事業)です。
「戸別所得補償」という名称が、あたかも“一戸一戸の農家の所得を補償する”かのような誤解を与えています。しかし、その実体は「差額の戸別配り制度」に過ぎません。制度の概要は、生産数量目標に従って主食用のコメを作り、水稲共済に加入している販売農家などに対し、生産費と販売価格の差を全国一律の定額で直接支払います。価格が下がった場合は、上乗せ助成をします。定額部分は、10アール当たり1万5000円です。
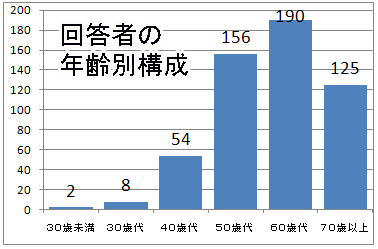 この金額は全国一律で、各地で生産条件などが違う現実を無視しています。2008年産米の10アール当たりの生産費は、一番低い北海道の11万2665円と、一番高い中国・四国の18万3686円では1.63倍の格差があります。それなのに全国一律にすると、不利な条件でコメを作る生産者の努力は報われません。
この金額は全国一律で、各地で生産条件などが違う現実を無視しています。2008年産米の10アール当たりの生産費は、一番低い北海道の11万2665円と、一番高い中国・四国の18万3686円では1.63倍の格差があります。それなのに全国一律にすると、不利な条件でコメを作る生産者の努力は報われません。
コメからの転作作物を助成する自給率向上事業にも疑問の声が上がっています。現行の産地確立交付金は、農地の団地化や担い手に対する経営支援に応じた地域独自の加算を行い、地方が主体的に転作を進めることができるようになっています。これを廃止し、品目ごとに全国一律の金額を助成する事業を実施しようとしています。米粉・飼料用などの新規需要米は、10アール当たり8万円を助成する一方で、麦や大豆は3万5000円、野菜や雑穀など「その他作物」は1万円と、かなり格差があります。新規需要米以外は、今の制度よりも大幅に助成が減ります。生産調整に真摯に応じ、経営努力を重ねてきた生産者や地方への配慮が欠けています。
そしてなによりも、農家への説明が遅れています。今年の営農計画も立てられないと、不安の声が出ています。
公明党茨城県本部は、農家の皆さまの声を真摯にお伺いして、日本の農業政策に具体的な提案をしていきたいとの思いから、アンケート調査を実施いたしました。
Q1:戸別所得補償制度の認知度は低い
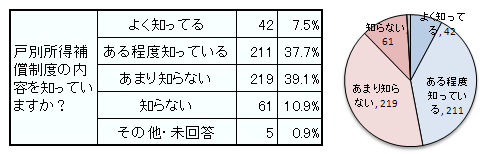
戸別所得補償制度について、「よく知っている」または「ある程度知っている」と回答した人は、253名で全体の46.9%に止まりました。反対に「知らない」「あまり知らない」と回答した人は、280名で、全体の51.9%と過半数に上りました。未だに制度自体の認知度が低く、政府の説明不足がその要因と推測されます。
Q2:戸別所得補償制度を導入しても農業経営は良くならない
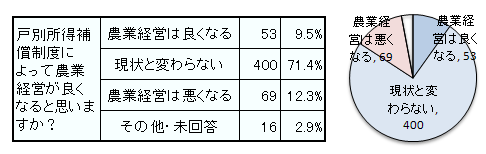
戸別所得補償制度を導入しても、全体の74.1%(400人)の人が、農業経営は「現状と変わらない」と考えていることが分かりました。農業経営が良くなると考えている人は、わずか53名(9.8%)しかいませんでした。茨城県の場合、そもそも農業経営が稲作に依存する割合が低いことが、戸別所得補償制度への評価が低い要因の一つと思われます。
Q3:「農業経営が悪くなる」と答えた理由(自由記述)
- 農地の集積が進まないから。
- 戸別所得補償制度は長続きしないと思う。
- 新規事業に対する助成が、現在転作中の作物より低くなるから。
- 説明不足で営農組合も計画が立てられないと思う。
- 地域間で不公平が発生してやる気を失わせる。
- 生産性の低い小規模農家が70%を占める現状では、ただ単に生産費と販売価格の差額を補償する制度では、農業全体の経営安定化には繋がらない。
- そもそも後継者がいないから。
- 戸別所得補償の対象になるための条件が複雑である。
- 転作の補償が無くなるから。
- 競争力が失われる。自分で努力しなくなる。大規模化が進まない。
- 小規模農家の切り捨て政策だと思います。後継者のいない小規模経営者はやがて、耕作放棄や大規模農家に吸収され、第二次大戦前の形態に逆戻りする。
- 野菜類にも所得補償がなければ、不公平で急激に農業が減少していく。
- 戸別所得補償を受けることでコメの価格が下落してしまう。
- 現在、農地を賃借りしていても正規の賃貸契約を結んでいない人が多い。このような人は戸別所得補償が受けられない。
- 大規模農家だけが恩恵を受け、農業の抜本改革にはほど遠い。
- 制度を悪用して真剣に農業に取り組まない農家が多くなるから。
Q4:定額部分1万5000円は安すぎる
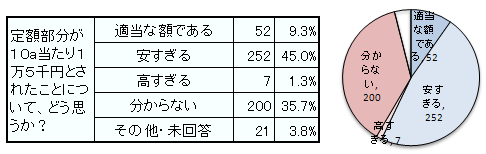
戸別所得補償制度の定額部分1万5000円/10aは、「安すぎる」と答えた人が、全体の46.7%に達しています。「分からない」と答えた人も、37.0%にのぼり、農家自らがコストを掌握できていない現状を物語っていると思われます。特に自らの人件費をどのように捉えるかで、判断に差が出ています。
Q5:定額部分が全国一律なのは見直すべき
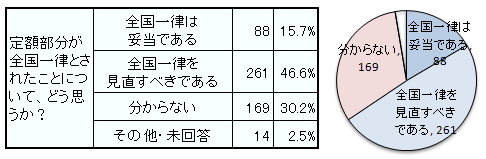
戸別所得補償制度の定額部分1万5000円/10aが、全国一律であることに対して、「妥当である」と答えた人は、88人(16.3%)に止まり、「見直すべき」と答えた人が261人(48.3%)に上りました。耕作条件が違う地域で、補償額が一定なのは不満感があるようです。
Q9:米以外に戸別所得補償がないのは不公平だ
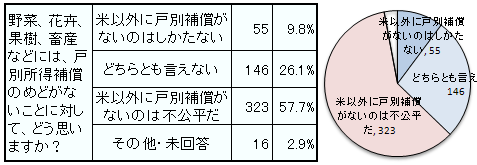
戸別所得補償制度が米以外にも適用されると勘違いしていた農家が多い。特に、茨城県では、野菜、果樹などの農家が多く、米以外に戸別所得補償がないことを不公平と考える農家が、全体の6割近くに達しました。
Q10:「水田利活用自給力向上事業」では米の転作が進まない
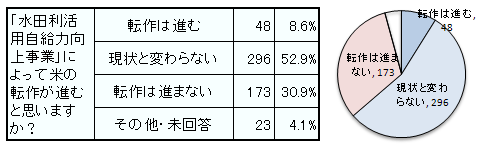
水田利活用自給力向上事業によって、「転作が進む」と考える農家はわずか8.9%に止まっています。「現状と変わらない」と「転作は進まない」を加えると86.9%に達しています。
Q11:戸別所得補償を導入しても後継者は増えない
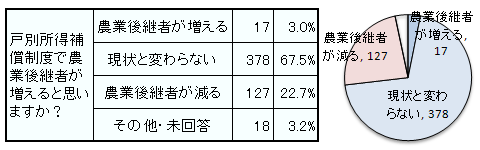
戸別所得補償制度が導入されても、「農業後継者が増える」と答えた農家は、わずか3.1%にすぎませんでした。「現状と変わらない」と「農業後継者が減る」と答えた農家は、93.5%にも達しました。
Q12:戸別所得補償を導入しても農地の集積は進まない
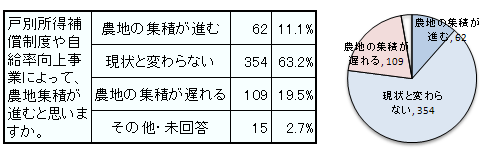
戸別所得補償制度で、「農地の集積が進む」と考える農家は、11.5%に止まり、「現状と変わらない」と「集積が遅れる」を加えると85.7%が否定的な考えを持っています。
Q13:戸別所得補償を実施してもFTAを進めるべきではない
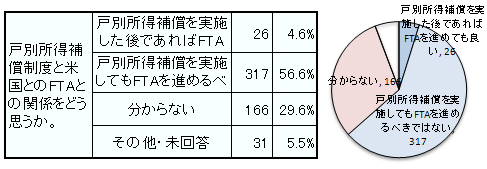
民主党は戸別所得補償と米国とのFTA締結を一体で行うと主張してきました。しかし、6割近くの農家が「FTAを進めるべきではない」と回答しました。
Q14:今後の農政に関する意見・要望(自由記述)
- 説明不足で所得補償制度の方向性が見えない
- 作った米は消費者に直接販売している。今までも、減反は一切行っていないし、これからも減反する意思はない。所得補償制度で国から金をもらおうとは思わない。国の農政に翻弄されるよりも、本当においしい米をじっくり作りたい。
- 全国の農家で同じ経営をしている農家は一戸もない。地方によって農家・農業は全く違う。政治家はもっと実状を知るべき。
- 農産物全体が安定した価格であって欲しい。
- 戸別所得補償制度というならば、10a当たり最低3万円程度は必要だと思う。
- 農家は大変手間が掛かり、その割りに収益が少ない。こうしたことから後継者がいないことが最大の問題。
- 担い手が育つ施策が大事であり、自給自足できる体制づくりが必要。
- バラマキ政策より担い手育成政策が大切。
- 専業農家の嫁不足が深刻である。
- 現在、稲作だけで生計を立てるのは困難。農家の総収入に占める米の割合の調査をしてはどうか。
- 農産物の価格安定化を図って欲しい。米だけでなく、野菜や果樹に最低価格を設定して欲しい。
- お金をばらまくだけではなく、もっと細かな指導をして欲しい。後継者を育成するための資金の貸し付けや技術指導、見習い期間の生活費支援などが効果的だと思う。
- どんなに大規模化しても、外国の安い人件費で作られる農産物にはかなわない。大規模化は異常気象や災害には対応できないし、作物の劣化も進む。視点を変えて中小規模の多くの農業者が夢を持てる未来を見られる農業を目指すべきだ。
- 戸別所得補償制度も民主党の打ち上げ花火に終わるような気がする。何年持つのか、いつまで続くのか不安。それが無くなった時に、生産調整はどのように行うのか心配になる。日本の主食である米を守るしっかりとした政策を望む。
- イノシシの被害が日々高まり、現状のまま放置すれば農業耕作をあきらめなくてはならないほどだ。国が害獣駆除の予算を縮小した理由が全く理解できない。
 参考:農家の戸別所得補償制度に関するアンケート調査結果報告PDF版
参考:農家の戸別所得補償制度に関するアンケート調査結果報告PDF版



