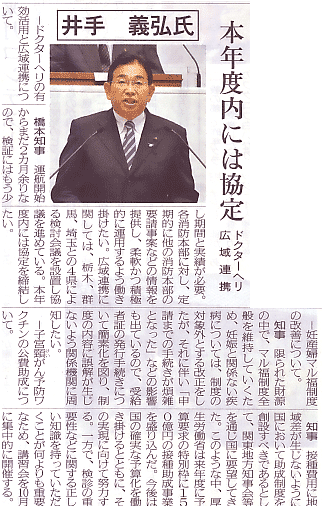9月7日に行われた井手よしひろ県議の代表質問は、新聞各社に紹介されました。その内容を以下のようにご紹介します。
本年度内には協定、ドクターヘリ広域連携
茨城新聞(2010/9/8)
ドクターヘリの有効活用と広域連携について
橋本知事:運航開始からまだ2カ月余りなので、検証にはもう少し期間と実績が必要。各消防本部に対し、定期的に他の消防本部の要請事案などの情報を提供し、柔軟かつ積極的に運用するよう働き掛けたい。広域連携に関しては、栃木、群馬、埼玉との4県による検討会議を設置し協議を進めている。本年度内には協定を締結したい。
妊産婦マル福制度の改善について
知事限られた財源の中で、マル福制度全般を維持していくため、妊娠と関係ない疾病については、制度の対象外とする改正をしたが、それに伴い「申請までの手続きが煩雑となった」などの影響も出ているので、受給者証の発行手続きについて簡素化を図り、制度の内容に誤解が生じないよう関係機関に周知したい。
子宮頸がん予防ワクチンの公費助成について
知事接種費用に地域差が生じないように国において助成制度を創設すべきであるとして、関東地方知事会等を通じ国に要望してきた。このような中、厚生労働省は来年度に予算要求の特別枠に⊥50億円の接種助成事業を盛り込んだ。今後は国の確実な予算化を働き掛けるとともに、その実現に向けて努力する。一方で、検診の重要性などに関する正しい知識を持っていただくことが何よりも重要なため、講習会を10月に集中的に開催する。
退職手当返上の考えなし住宅供給公社解散で知事「総合的に判断」
常陽新聞(2010/9/8)
橋本昌知事は7日の第3回定例県議会代表質問で、県住宅供給公社の解散処理をはじめ県保有土地問題で、県政の責任者として給与月額50%カット3カ月間とともに退職手当30%減額を実施することについて、「退職手当については責任の重さ、仕事の量など職務の内容を見ながら総合的に判断していく必要がある」として、退職手当を返上する考えはないことを示した。公明党の井手義弘氏の質問に答えた。
井手氏は「茨城県知事の退職手当はもともと高額。全国の知事の平均以下に下げたに過ぎないとの批判もある。非支給という選択肢はなかったのか」と報酬減額の内容についてただした。
知事の給与カットは2007年4月から実施している20%カットに30%を上乗せし、10月から3カ月間で実施。退職手当は1543万7000円を減額し、約3600万円の支給となる。住宅供給公社に関して橋本知事は06年に給与を3カ月50%カットし、4期目の退職金は20%返上した。
昨年の県開発公社などへの経営支援を行う際にも給料などを減額している。
知事の退職手当は4年の任期満了で、134万円の月額給料の48カ月分に支給乗率0・8を掛けて支給。
支給額は約5145万円となり、東京都知事などを上回り全国でも上位になるという。
非支給について橋本知事は「退職手当は全体的な処遇のあり方を考える中で検討していくべきものと考えている。他県の例なども踏まえてこのような判断をした」と述べた。
保有土地問題で退職金減額、知事「他県例踏まえ判断」
読売新聞(2010/9/8)
橋本知事は7日の県議会本会議で、県の保有土地問題で退職手当(退職金)を減額する方針について「非支給とする選択肢はなかったのかとの意見もいただいたが、全体的な処遇のあり方を考える中で検討すべきものと考えており、他県の例なども踏まえて判断した」と述べた。井手義弘氏(公明)の代表質問に答えた。
橋本知事と副知事2人は、県住宅供給公社の破産による解散など保有土地問題の対策方針を取りまとめたことを受け、給料と退職手当を減額する条例改正案を今定例会に提案している。橋本知事は今回の減額措置と併せて保有土地対策に伴い、給料は50%減額を9か月、退職手当は50%減額することになる。
ドクターヘリ広域連携 来春にも実施 関東4県
産経新聞(2010/9/8)
橋本昌茨城県知事は7日、茨城県が7月から運用を開始しているドクターヘリについて、「広域的な利用をさらに拡大するため、栃木、群馬、埼玉との4県による(広域連携の)協議を進めている」と明らかにした。開会中の県議会で、井手義弘氏(公明党)の代表質問に答えた。
橋本知事はドクターヘリの他県との連携について、現在、共同利用の協定を結んでいる千葉県との例に触れ「救急医療に効果を発揮している」と説明。そのうえで、「4県による検討会議を設置し、協議を進めている。今年度内に協定を締結し、広域的な活用を図りたい」と述べた。
県医療対策課や各県の担当者によると、今回の広域連携については、他県に出動した場合でも、ドクターヘリの運航にかかる経費については原則各県で負担するなど、新たな予算措置を必要としない方向で検討が進んでいるという。そのため、年度内に協定が締結された場合、早ければ来春にも広域連携が可能となる見込みだ。