12月12日投票の県議会議員選挙を目指して、多くの方にお会いする機会が増えています。
4年ごとの選挙で、その都度思いを強くすることは、地域社会の人と人との“つながり”が断絶しつつあることです。人や地域とのつながりを持てずに社会から孤立する「無縁社会」が、じわじわと広がっていると実感します。
にわかにクローズアップされた高齢者の所在不明問題は地域のつながり、人間関係の希薄化を浮かび上がらせのも記憶に新しいものがあります。
昨年、内閣府が60歳以上の高齢者を対象に行った調査によると、一人暮らし世帯では「2~3日に1回」以下しか会話をしない人が男性で約4割、女性でも約3割に上っています。一人暮らしの高齢者が家庭や地域とのつながりを持てず、社会的に孤立しやすい環境に置かれている実態があります。
最も多い日本の家族類型は単身世帯――とのデータも示されています。国立社会保障・人口問題研究所が推計した世帯の将来推計では、従来、家族のかたちとして最も多かった「夫婦と子」の世帯は、既に2006年には単身世帯にそのトップの座を譲っているとみられています。
単身世帯は、確実に今後も増え続けます。2030年には1824万世帯に達すると予測されています。この年には高齢男女や中高年男性の単身世帯が目立つようになり、50、60歳代男性の4人に1人は単身世帯との試算もあります。
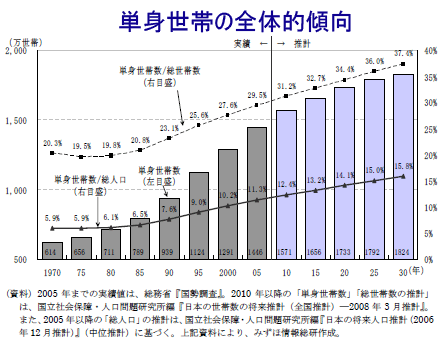
中高年男性の単身世帯増の背景には未婚化が挙げられている。こうした人たちが高齢世代になれば、配偶者がいないだけでなく、子どももいないわけで、いわゆる家族の支え合いを一層困難にします。単身世帯の6割は孤独死を身近に感じ、不安を覚えています。
今日一日で単身世帯のお年寄りから2つのご相談をいただきました。1件は生活保護で生活している方が、自分の葬儀はどのように行って貰えるのだろうかと、涙で訴えていました。もう1件は、現在は住んでいない千葉県内の自己所有のマンションを売却したいのだがどのようにすればよいのか、とのご相談でした。
無縁社会の進行を放置していいはずなどありません。単身世帯が急増していく日本社会で、支え合う仕組みの再構築が必要になっています。
その上で、従来の社会保障制度の枠組みでは想定できない新たなリスク(危険)に対応するため、公明党は「新しい福祉」の構築に全力を挙げています。もちろん、無縁社会への対応も例外ではありません。



