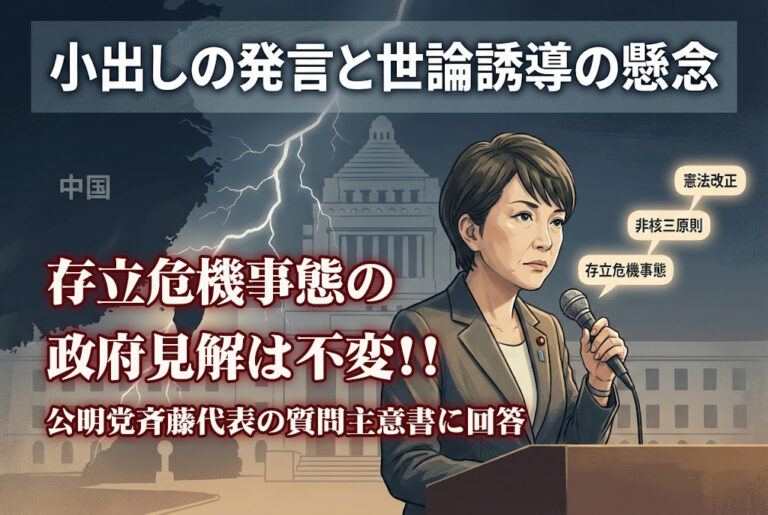今日(1月10日)は「成人の日」。茨城県のまとめによると、ことし県内で成人式を迎える新成人は、平成2年4月2日から平成3年4月1日までに生まれたあわせて3万1310人の皆さんです。
今日(1月10日)は「成人の日」。茨城県のまとめによると、ことし県内で成人式を迎える新成人は、平成2年4月2日から平成3年4月1日までに生まれたあわせて3万1310人の皆さんです。
成人の日に当たり、井手よしひろ県議は、市内2カ所で街頭演説を行いました。このブログでは、その内容から「学びを支援する奨学金」について語った内容をご紹介します。
公明党は、経済的な困難があっても安心して学べるよう、奨学金の拡充を一貫してリードしてきました。返済が不要な「給付型奨学金」の創設や、学生の「うつ病」をはじめとした心の悩みなどの相談体制の整備、学生の就職活動の支援政策を取りまとめ、昨年、政党として初めて学生のための政策集をつくりました。
こうした公明党の戦いによって、大学生らに奨学金を貸与している日本学生支援機構は、奨学金の返済が困難となった卒業生を対象に、今年1月から最長10年間、毎月の返済額を半額に軽減する「減額返還制度」を導入しました。
これまでも病気や失業などを理由に1年を限度(通算5年まで)として返済を猶予する制度はありましたが、今回、さらに奨学金が返済しやすくなりました。
対象は経済的な理由で返済が困難となった年収300万円以下の人。この制度の利用で返還期間の上限が20年から25年に延びますが、利子負担額は変わりません。
今回の制度導入の背景として、奨学金の返済に困る卒業生が増えていることが挙げられます。
大学生の就職内定率がここ数年大きく低下する中、就職が決まらずに派遣やアルバイトに就く卒業生が増加しています。その結果、奨学金の返済が大きな負担となっているのです。
2009年度末で奨学金を返済しなければならない卒業生は約263万人。このうち13%にも及ぶ、約34万人の返済が滞っています。
日本学生支援機構が昨年11月に発表した2009年度の延滞者の実態調査によれば、最も多い延滞理由は本人の低所得で49.1%にも上ります。延滞者の職業は正社員が28.5%に対し、派遣やアルバイトが36.9%と多数を占めており、年収300万円未満は87.5%にも達しています。
公明党は「一人一人に応じたきめ細かな奨学金制度等の構築」を掲げ、貸与要件の緩和や貸与枠の拡充などを実現、学生生活を支援してきました。
奨学金の返済についても、参院選マニフェストで急激な社会状況の変化や家計の急変に対応する所得に応じた返還制度創設を主張してきました。
公明党は、山口代表を先頭に、全国3000人を超える議員が、皆さまの悩みを一つひとつ伺う中で、政策を立案し、実現していく「行動する政策創造集団」であります。私たちは「戦う野党」として、国民の皆さまの生活向上のため全力で取り組んでいます。
これからの政治は、未来を担う青年に光を当て、夢と希望を持てる社会にしなければなりません。今の菅政権は、若者の課題に真剣に取り組んでいるとは到底思えません。私たち公明党は、これからも若い皆さまとともに青年政策の実現に全力で取り組んでまいります。
(写真は「土浦市成人式」の模様。八島功男県議撮影)