 6月9日付けの地元紙「茨城新聞」の一面。東日本大震災から3カ月の節目を前に、地域の防災体制を検証する連載記事が始まりました。
6月9日付けの地元紙「茨城新聞」の一面。東日本大震災から3カ月の節目を前に、地域の防災体制を検証する連載記事が始まりました。
その第一回は、震災当日7.2メートルの津波が襲い6名の死亡・行方不明者が出た北茨城市の状況を伝えていました。
津波襲来、繰り返し「逃げろ」 伝達手段途絶え叫ぶ:検証3・11第1部「その瞬間」(1)
茨城新聞(2011/6/9)
消防指令室は即座に非常用電源に切り替わる。津波襲来までの時間は短いと判断し、避難広報のため6台を出動させ、残りは高台で待機させた。
情報収集の“命綱”は消防無線。県の防災ヘリが「沖合に津波が見える」と伝えた。出動した消防職員は叫んだ。「津波が押し寄せている」
「午後3時10分ごろ津波が来る」。平潟地区を担当する消防団第15分団の伊藤良一団長(51)はラジオを聴き、平潟公民館に隣接する分団詰め所に急いだ。
信手段は途絶え、市から連絡は入らない。消防車で平潟漁港に向かい、逃げるよう叫び続けた。
壊滅的被害を受けた南側の住宅地は道路が液状化し到達できない。防災行政無線の屋外スピーカーは整備されておらず、やや離れた場所で消防車から繰り返し避難を呼び掛けるしかなかった。
同漁港北側にある平潟漁協の2階事務所で、鈴木一久事務長(45)は堤防の先を見詰めた。
港の南北両側から白い波が滝のように一気に流れ込んだ。乗用車が津波にのまれ、濁流の中を歩いて逃げる住民の姿が見えた。
北茨城市では、津波などの災害を市民の伝える方法として、緊急情報メール配信システムが整備されていました。しかし、このシステムにはわずか900人しか登録されておらず、その上、停電でサーバーが使えなくなり、津波警報の発令を登録者に送信できませんでした。
2005年、北茨城市では津波からの避難を呼び掛けるために『半鐘』を整備しました。前市長が「防災無線の設置より格安だ」として約1600万円かけて海沿いに24基を設置しました。津波警報が出た際は、消防団員1人と市職員2人の計3人が4メートルの高さにあるやぐらに上り、半鐘を鳴らして回るはず手はずでした。しかし、消防団員は地震の被災者の救援活動に忙殺され、職員は交通渋滞で半鐘にはたどり着けませんでした。結果、津波が来ると情報は、消防車やパトカーのスピーカーからの呼びかけだけでした。
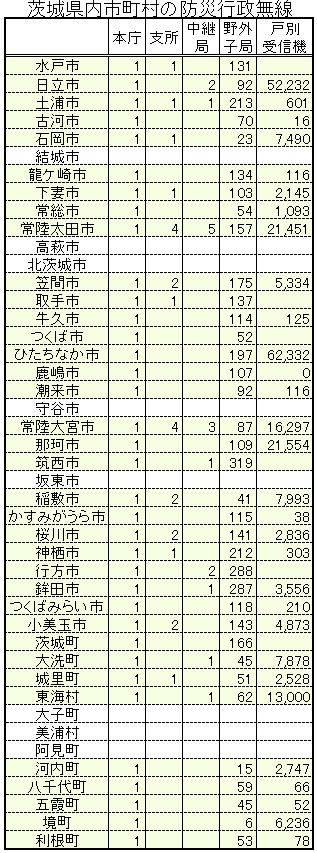 非常時の情報伝達体制の不備が、北茨城市の被災者を増やしたかどうかの検証には、今少し時間が掛かるかもしれません。でも、もし防災無線が整備されていればとの、声は市民の間から聞こえてきます。
非常時の情報伝達体制の不備が、北茨城市の被災者を増やしたかどうかの検証には、今少し時間が掛かるかもしれません。でも、もし防災無線が整備されていればとの、声は市民の間から聞こえてきます。
一方、日立市では地震直後から、市内92カ所の野外子局(鉄塔に大型のスピーカーが付いた装置)から「津波が来ます。避難して下さい」との声が、街中に響き渡りました。その上、市内の7割の家庭にはラジオ型の戸別受信機が配備されており、津波への注意喚起を繰り返し放送していました。日立市では、JCO事故の教訓から市内の南半分の地域(東海村の原子力施設から10キロ圏内)には、防災無線の戸別受信機が配置されていました。平成21年からは、残る北側の地域にも新型の戸別受信機の配備事業がスタートしています。(防災行政無線の戸別受信機の整備進む・日立市全域に防災無線戸別受信機を整備)
日立市の防災無線に効果については、以下のようなコメントが寄せられました。
実際、地震被害(津波)を受けてみて、この防災ラジオの効果を実感しました。確かに、よく聞こえなかったのですが、地震が来て、外に持ち出したら非常に良く聞こえました。緊急の時はこんな使い方になるのかと実感しました。日立で、津波の死傷者が出なかったのは、このラジオのおかげです。早く、十王の人にも配るべきです。(Posted by 床上被災者 at 2011年04月06日 12:34)
私も防災無線に助けられました。私は日立市の北部地域に在住しておりますが、震災時南部地域にある会社に勤務中でした。地震後沿岸地域にある私の会社の一部が津波にのみこまれました。しかし、防災無線のおかげで津波が到達することを知り高台に逃げたため私を含め社員は全員無事でした。幸い北部にある自宅は津波の被害はなかったのですが、在宅中に宮城県のような巨大津波がきていたら・・・テレビもつかない、ラジオもつかない、携帯電話も繋がらない情報がない状態で確実に避難できていたか、今も思うとぞっとします。色々な予算調整で日立市全地域に防災無線配備は難しいのかも知れませんが、海岸沿いの住民には最後の砦だと思います。北部地域にも早期の防災無線配布をお願いしたいと思います。(Posted by 日立市民 at 2011年04月27日 14:46)
東日本大震災という複合的な災害を被り、防災無線と戸別受信機の整備は、ぜひ必要だと実感しています。
右の一覧表は、井手よしひろ県議の要請で県消防防災課が取りまとめた、6月1日現在の県内市町村の防災行政無線の整備状況です。



