阪神・淡路大震災(1995年)の直後に兵庫県西宮市で開発された「被災者支援システム」が注目を集めています。東日本大震災の被災地でも導入が進み、円滑な“り災証明書”の発行などに役立てられています。
目的・きっかけ 「阪神」直後に開発
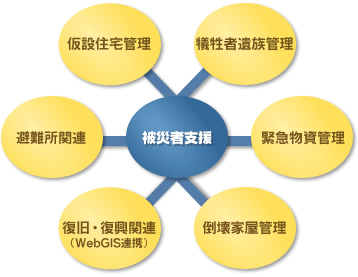 「被災者支援システム」は、阪神大震災で壊滅的な打撃を受けた西宮市が開発したものです。被災者の生活再建に向けて必要となる膨大な行政事務を効率的に行うため、市職員が試行錯誤を繰り返して震災から10日ほどで構築し、約1カ月後から稼働。実践の中で活用され、被災者支援や復旧・復興業務に大きな効果を発揮しました。
「被災者支援システム」は、阪神大震災で壊滅的な打撃を受けた西宮市が開発したものです。被災者の生活再建に向けて必要となる膨大な行政事務を効率的に行うため、市職員が試行錯誤を繰り返して震災から10日ほどで構築し、約1カ月後から稼働。実践の中で活用され、被災者支援や復旧・復興業務に大きな効果を発揮しました。
例えば、西宮市ではシステム導入により、当初、手作業で7時間ほどかかっていた罹災証明書の発行が1時間程度まで短縮できました。
支援システムは2006年から無料公開され、2009年に総務省がCD媒体でと全国の自治体へ配布しています。現在は、財団法人・地方自治情報センター(LASDEC)が普及業務を担っています。
 参考:被災者支援システムの概要(西宮市情報センター)
参考:被災者支援システムの概要(西宮市情報センター)
仕組み・効果 災害時の業務円滑化
支援システムは、災害発生時の住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳をつくり、(1)家屋の被害(2)避難先(3)犠牲者の有無(4)口座番号(5)罹災証明書の発行状況―などを一元的に管理。氏名などを端末に打ち込めば、被災関連情報をすぐに見つけ出すことができます。
例えば、被災者が義援金などを受け取るために必要となる罹災証明書の発行には、住民基本台帳、家屋台帳、被災状況という三つのデータベースを確認・照合する必要がありますが、従来型の仕組みでは、これらが別々に存在するため、発行に手間取り、窓口に長蛇の列ができることもしばしばです。
これに対し、支援システムではデータを一括して管理することで、その都度、確認・照合する手間が省け、スムーズな発行業務につなげられます。
低いコスト、職員が担えばゼロも
支援システムの導入には、「IT能力の高い職員が確保できず、難しい」「厳しい財政事情の中、導入経費を確保できない」といった声が聞かれます。しかし、もともと西宮市職員が災害の最中、必要に応じて立ち上げたもので、高いIT能力がなければできないものではありません。
また、職員がシステム稼働の業務を担うことで、導入コスト(費用)はゼロ。民間企業に委託しても委託費は数十万円程度で済みます。新たな設備の導入も特に必要なく、既存のパソコンがあれば十分に対応できる軽便なシステムです。
今回の震災後、改めて支援システム導入への機運が高まり、東北3県で30近くの自治体が、全国各地でも約140の自治体が既に導入、あるいは準備を進めています。
福島・須賀川市の事例から 「罹災証明書、義援金支給 迅速に」
福島県須賀川市も震災後に支援システムを導入した自治体の一つです。須賀川市は震災により本庁舎が被災。損傷が激しく、倒壊の恐れがあるため、現在は、分庁舎や市文化センターなどの公共施設で応急的に窓口業務を行っています。
須賀川市によると、罹災証明書の発行と義援金支給の担当課が別々の場所に分かれてしまいましたが、支援システムに接続した端末を各所に設置することで、場所が離れていても確認作業などに手間取ることなく、罹災証明書の発行とほぼ同時に、義援金が振り込めるようになりました。
須賀川市生活課の担当者は「複数の場所から情報を共有することができ、スムーズな業務の処理につなげられている」と語っています。
宮城県山元町も震災後に導入を決断しました。現在、罹災証明書をスムーズに発行しているほか、義援金などの交付や減免等で新たな申請を不要とするなどの効果を発揮しています。町の担当者は「行政にとっても住民にとっても助かる」と同システムを評しています。
公明、システム普及へ地方議会で論戦展開
公明党は5月26日に発表した「東日本大震災復旧復興ビジョン」に、支援システムの導入を盛り込むなど、国会論戦の中でも国に全国の自治体への普及を強く要請しています。
また、現在、全国各地で行われている6月の定例議会においても公明の地方議員が平時から支援システムを導入し、災害時に備える意義を訴えています。
茨城県議会でも、八島功男県議が総務企画委員会で、県内市町村にその普及をはかるよう提案しました。



