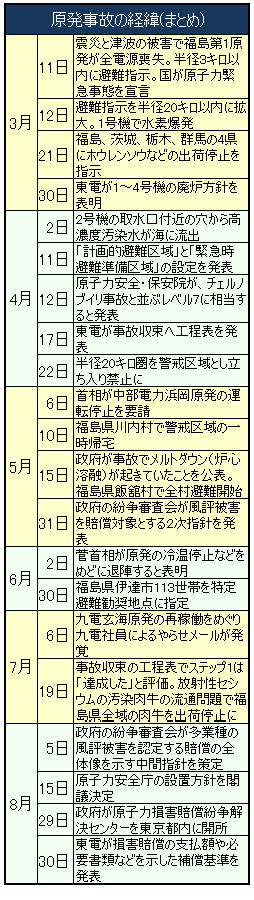 3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第1原子力発電所の事故から半年が経とうとしています。原子力安全・保安院は4月、事故を国際評価尺度で最悪の「レベル7」とし、また、福島第一原発1~3号機から放出された放射性セシウム137(半減期約30年)の量を、広島に投下された原爆の168倍に及ぶとの試算を8月に公表しました。放射性物質を取り除く除染作業が実施されている地域の住民は、今後も「放射能汚染との闘い」を強いられています。
3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第1原子力発電所の事故から半年が経とうとしています。原子力安全・保安院は4月、事故を国際評価尺度で最悪の「レベル7」とし、また、福島第一原発1~3号機から放出された放射性セシウム137(半減期約30年)の量を、広島に投下された原爆の168倍に及ぶとの試算を8月に公表しました。放射性物質を取り除く除染作業が実施されている地域の住民は、今後も「放射能汚染との闘い」を強いられています。
事故当初から、国民は政府の二転三転する説明や後手後手の対応に翻弄されました。政府は適切な情報公開を怠り、将来の安全規制の構築についても場当たり的対応を続けています。
【政府の情報隠し】
マグニチュード9という未曾有の大地震によって、原子炉は自動停止したものの、1~3号機の緊急炉心冷却装置と、停電時に除熱装置を動かす非常電源が全面的に喪失。原子炉は停止後も高温であり、外部電源を失った原発は最悪のメルトダウン(炉心溶融)に至りました。
しかし、政府がその事実を公表したのは2カ月後。また、事故で放出された放射性物質の拡散予測システムであるSPEEDIのデータも公表しようとせず(5月に公表方針決定)住民の避難を混乱させ、放射性物質による食品汚染を拡大させました。
【不安な安全規制構築】
現在、政府は原発の安全規制を強化するため、現在の原子力安全・保安院(経済産業省の外局)と原子力安全委員会(内閣府に設置)を再編した原子力安全庁を環境省に新設することを決め、準備を進めています。原発推進の経産省と安全規制の保安院が人事交流をしてきたことに対する反省です。
確かに、推進組織と安全規制組織の分離は国際標準の考え方です。しかし、政府には安全規制の専門家を育てる人事構想がありません。現状の保安員も電気事業者や原発県連の企業の技術者から人材が供給されている現実があります。こうした状況の中では、組織分離だけの安易な構想になりかねません。
被害の現状と損害賠償の問題
今回の原発事故では、大量の放射性物質が環境中に飛散し、農畜産物や土壌など、広範囲に甚大な汚染被害をもたらされています。人体への長期的な健康被害も危惧されています。
住民の間では内部被ばくの不安が高まり、農産物の買い控えも起こっています。また、原発から半径30キロ圏内で屋内退避などの指示が出た福島県内の市町村が、数千人単位の住民を独自判断で集団避難させるなど、住民生活にさまざまな影響が及んでいます。子どもを連れて、県外避難を決断する家庭も後を絶ちません。
福島県では放射線の影響を踏まえ、将来にわたって県民の健康管理を目的とした「県民健康管理調査」を実施するため、8月下旬から、問診票の発送を開始。3月11日から25日までの行動記録を中心に、被ばく線量の推計評価を行うことにしています。
農畜産物については、暫定規制値を上回る放射性物質が検出されたことを受け、国が3月21日に福島県産の原乳や、福島、茨城、栃木、群馬4県のホウレンソウなどの葉物野菜に出荷制限を指示。以降、さまざまな農畜産物が出荷制限を余儀なくされました。中には出荷制限を苦に自殺する生産者も出てています。
また、解除されたとしても風評被害は深刻で、安全性が確認された農産物でも、取引量減少や価格下落が続いています。
今後の課題は汚染地域の除染です。放射線量の低減へ現在、福島市が全市立小・中学校や幼稚園、児童センターなどを対象に建物除染や校庭などの表土除去を行ったほか、茨城県内でも教育施設などで除染措置が進んでいます。
しかし、国による費用負担や最終処分場の確保など、迅速な措置は不可欠です。自治体の取り組みを後押しする国の責任ある対応が急務です。
請求手続きが負担にならないよう配慮を
原発事故による被害者への損害賠償は今月からようやく動き出します。
原子力災害に関する現行法は、事故に伴う全ての賠償責任を事業者に課しています。しかし、今回のような大事故の損害賠償を全て一事業者に課すことには無理があります。
事実、東京電力がこれまでに行ったことは損害賠償の仮払いがやっと。しかも、あまりに少額で避難住民や仕事を失った被害者の生活再建を支えるには程遠いものがあります。
公明党は今回の損害賠償については国も責任を認め、国が前に出て対応するよう主張しましたが、政府は東電を前面にする姿勢を崩しませんでした。その間、避難住民や被害者は不安定な状況のまま放置されてきました。
その後、ようやく政府の責任を問う声が広がり、原子力損害賠償支援機構(今月スタート)と、損害賠償の国による仮払いを進める法制度が共に通常国会で成立。それを受け東電は8月30日、原発事故に伴う損害賠償の基準や手続きを発表しました。
ただ、東電への損害賠償請求には一定の書類が必要で、損害の額を自身で見積もって記入しなければなりません。避難住民にとってこれは大変な負担になることは明白です。また、賠償額について東電側と紛争が起こる可能性もあります。複雑な手続きが被害者を苦しめるようでは本末転倒です。政府は損害賠償制度が円滑に運営されるよう配慮すべきです。



