民主党の年金改革、「新制度創設」は棚上げ、釈明なく“現行制度の改善”へ転換
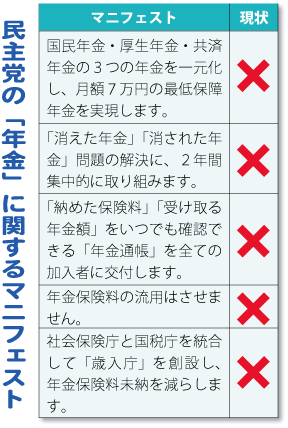 民主党が国民に約束した年金に関するマニフェストの実現度は、『総崩れ』に等しい現状です。
民主党が国民に約束した年金に関するマニフェストの実現度は、『総崩れ』に等しい現状です。
納めた保険料に応じて年金を受給できる「所得比例年金」と全額税による月7万円の「最低保障年金」を組み合わせた制度を創設し、全国民がこれに加入(公的年金制度の一元化)すれば、低年金や無年金も解消し、公平で信頼できる制度になると喧伝しましたが、政権交代から2年、年金一元を提唱して8年余が過ぎても、一向に具体案すら明示できないでいます。
仮に新制度が実現しても、既に年金を受給している高齢者世代は「新制度の影響を受けない」ため、現在の低年金・無年金者は救済されません。「公平で簡素で分かりやすい制度」に完全移行するまでには数十年もの時間が必要です。
また“国家プロジェクト”として2年間集中的に取り組んだ「年金記録問題」も、約5000万件の未統合記録のうち回復したのはわずか1584万件(今年6月現在)止まり。解決のめどは立っていません。費用対効果から「4年間で全件照合」の公約は断念する方向です。
「納めた保険料」「受け取る年金額」をいつでも確認できる「年金通帳」を全加入者に配布するとの公約も、提唱から4年経ちましたが、「国民の意向調査を実施予定」というのみで一歩も前進していません。
「年金保険料は断じて流用させない」と、流用禁止を法律で定めるとした公約は全く「未着手」です。野党時代の2007年末に〝年金保険料流用禁止法案″を参院に提出し通過させた民主党ですが、政権を握った途端、毎年約2000億円かかる社会保障関連事務費への流用には目をつぶり、だんまりを決め込んでいます。
「歳入庁を設置し、税と保険料を一体的に徴収し、年金保険料の未納をなくす」との公約も、歳入庁の創設は具体的検討段階にすらなく、未納者は増加の一途で有効な手だては、全く打たれていません。
「厚生」「共済」の年金一元化。野党で“反対”、与党で“推進”
政府は、年金の官民格差をなくすため、会社員の厚生年金と公務員の共済年金の保険料率を2018年度に統一して制度を一元化する方向で調整に入りました。この両年金の一元化は既に2007年、自公政権が「被用者年金一元化法案」をまとめ、提出していたものです。
この被用者年金一元化法案は、当時野党だった民主党は「自営業者などの国民年金も含めたすべての年金の一元化でないと、抜本改革の名に値しない」と猛反発、審議未了で廃案となった法案に他なりません。。
ところが与党になったら、その骨子をそのまま引き継ぐ法案を、来年の通常国会への提出に向けて議論を進めているのです。
かつて廃案となった被用者年金一元化法案には、その「被用者」の範囲について「労働時間30時間以上」の加入基準を「20時間以上」に拡大することにしています。“パート労働者への厚生年金適用拡大“も盛り込まれていました。
当時、成立していれば、少なくとも「働き方に中立で平等な年金」へ改革が動きだしていたことは、否定できない事実ですだ。結果的に民主党の理念無き政策と、その方針変換で年金改革の流れは5年近く滞ることになりました。
国民は認めてない!年金支給開始年齢引き上げへの議論
一方、民主党政権にあって、年金の支給開始年齢について、その引き上げを画策する不穏な動きが浮上しています。厚生労働省は、急速に進む少子高齢化に対応するには、年金の支給開始を将来的に68歳から70歳程度へ引き上げることを視野に検討を進める必要があるとして、今後、本格的な議論を始める方針を固めました。
年金の支給開始年齢を巡っては、厚生年金について、男性は2025年度、女性は2030年度までに段階的に65歳まで引き上げ、基礎年金と合わせることがすでに決まっています。これについて、厚生労働省は、急速に進む少子高齢化に対応するには、さらに68歳から70歳程度へ引き上げることを視野に検討を進める必要があるとして、社会保障審議会の部会で議論を開始します。具体的には、引き上げるスケジュールを3年に1歳ずつから2年に1歳ずつに早めて、65歳への引き上げ時期を前倒ししたうえで、基礎年金とともに、68歳から70歳程度へ引き上げる案などがすでに想定されています。
民主党マニフェストには、一言も触れられていない対象年齢の引き上げ。引き上げについて、すでに既定の事実であるような議論は絶対に許せません。



