10月20日のブログ「原子力事故防災範囲の見直し案まとまる」で紹介した原子力施設の防災重点範囲の見直しについて、国の原子力安全委員会の作業部会は、東京電力福島第一原発の事故を受けて、これまで原発の8キロから10キロ圏内としてきた防災対策を重点的に整備する範囲(EPZ)について、新たな区域を設けるWG案が示されていました。
11月1日の作業部会で、これまでの議論や、IAEA=国際原子力機関の基準などを踏まえた結果、新たに避難などの防護対策を整備する区域「UPZ=緊急時防護措置準備区域」をおおむね30キロに設定し、事故が起きた際に直ちに避難する「PAZ=予防的防護措置準備区域」を設けて、その範囲をおおむね5キロとする方針をまとめました。
このほか甲状腺の被ばくを避けるためにヨウ素剤の服用などの対策を準備する範囲について、50キロを目安に、国が被ばくを避けるための防護措置を実施する地域(PPA)としています。この範囲をWGは「PPZ」と圏(ZONE)と表現したものを、「PPA」地域(AREA)との表現に改めました。
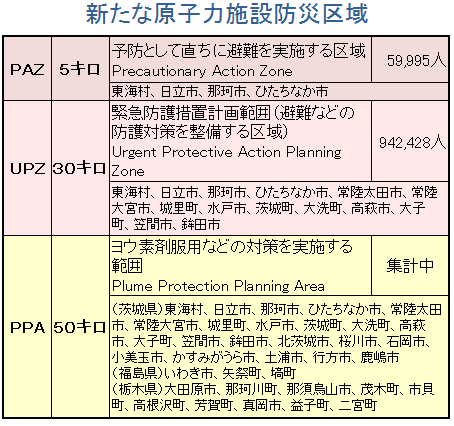
原発防災範囲を30キロに拡大した際の茨城県の影響
- 原子力防災範囲が拡大されると、茨城県においてはUPZ(緊急時防護措置準備区域)に、全国でも最も多い94万人余りが生活することになります。この住民をいかに避難させるか、その避難方法や道路の整備、などが大きな問題となります。
- UPZ(緊急時防護措置準備区域)内には茨城県庁や茨城県警本部、水戸市役所などの茨城県の中枢機能が全て位置しています。こうした施設の代替施設をどのように整備するかは最大の課題でもあります。
- 30キロ圏内には茨城県の工業生産の多くを占める日立製作所の主要工場が立地しています。この地域で生産機能がストップすれば、日本経済にも深刻な影響を与えます。
- 東海村を中心に、PAZ(予防的防護措置準備区域)には原子力の主要な研究施設が立地し、この施設が使用できなくなることで、日本全体の原子力防護体制が大きく弱体化します。
- PPAについては、茨城県のみならず栃木県と福島県にまたがるため、ヨウ素液の配布や飲料の指示をどのように行うかも、ポイントになります。
- 新たにUPZに加わった市町村は、当然、原子力安全協定を原子力事業者と結ぶことが求められます。地元自治体と原子力事業者との関係性を再度検討し直す必要があります。
原子力防災範囲の見直し案を機に、茨城県とそれぞれの自治体が防災計画を練り直すことになります。上記の諸課題を解決するためには、巨額の費用がかかります。その費用負担は当然、国が負担すべきです。
しかし、そのコストと東海原発の存続のメリットを天秤にかけて、冷静な判断を行う必要があります。そこには“東海原発の廃炉”という選択肢も十分に存在するはずです。
より大きな地図で 新たな原子力防災体制 を表示



