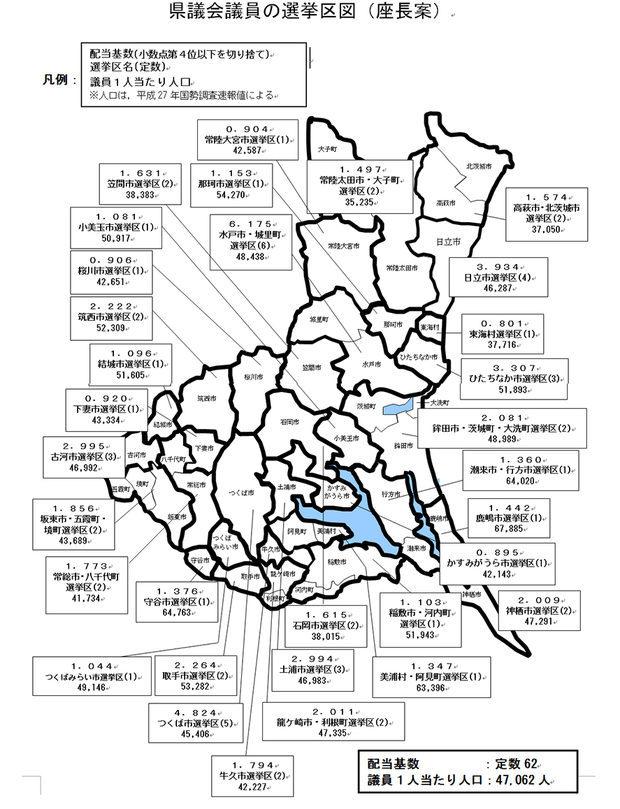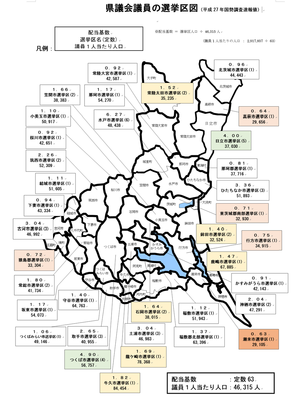県議会基本条例検討会を設置
 12月2日、茨城県議会議会運営委員会に、「県議会改革等調査検討会議」が取りまとめた県議会を活性化させるための具体案が示されました。
12月2日、茨城県議会議会運営委員会に、「県議会改革等調査検討会議」が取りまとめた県議会を活性化させるための具体案が示されました。
この日報告、提案されたのは、1.代表質問・一般質問に“分割質問方式”を導入するための具体案、2.議長の諮問機関として新たに「県議会基本条例検討委員会」の設置をすること、3.本会議での会派毎の採決態度をインターネットなどで公開する具体的な方法、4.予算特別委員会のインターネット中継を来年第1回定例議会から導入する件の報告、5.議会の費用弁償(議会への交通費並びに滞在費)を会期中も会議がない日は支給しない件の報告、6.県議会常任委員会の名称と所管を一部変更する条例案の提出、などです。
井手よしひろ県議ら公明党が昨年12月の県議選でマニフェストに掲げた議会改革が、当選後1年で具体的にスタートすることになりました。
県議会本会議質問に分割質問方式導入
この中でも注目されるのは、第1項目の質問方式の改善です。現状は、質問者が一括して質問事項を知事始め県執行部に行い、答弁は質問終了後、順次知事から各部長が行ってきました。この方式では、議論が通り一遍で余り深まらないため、井手県議らは一問一答方式や分割質問方式の導入を提案していました。
一問一答方式とは、国会の予算委員会のように通告した質問の一つひとつに知事や関係部長が答弁していくやり方です。分割質問方式は、質問を大きな項目毎に区切り、その項目毎に質問を行い、答弁はまとめて知事や執行部が行っていくやり方です。
井手県議らの提案に対して、議会改革検討会議では、「本会議の質問方式を現行の一括質問一括答弁方式に加え、分割質問方式を選択できる」との結論に至りました。2日示された具体的な運用案では、通告書の「質問の要旨」欄の大項目ごとに分割して質問し、答弁を受ける方式が提案されました。中項目、小項目単位での分割はできないとしています。また議事の円滑な進行を妨げないため、発言通告後の質問方式の変更は認めません。
まず質問者は議場の質問席で質問します。一つの大項目の質問を終えると自席には戻らず、議席中央の設置する質問者席で、答弁を聞くことになります。大項目毎に答弁に不満が残る場合は、2回目で再質問が出来ます。再質問は、登壇せず質問者席から行うことになります。
第2項目以降の質問は質問席から直接登壇します。これを繰り返し、持ち時間(代表質問は会派の持ち時間、一般質問は60分)内で質問を終えることとしています。持ち時間の5分前には、議長が鈴を鳴らすことにします。
質問者席は、議長席に向かって中央最前列の右端の席(現在の5番席)に設ける予定です。
この原案に対して井手県議は以下3点の提案を行う予定です。
- 質問者席の脇に補助者席を設ける(補助者は質問時間の調整や再質問の整理など、質問者の円滑な質問をサポートするために、同僚の県議から選ぶことが出来る。また、質問者・補助者の業務をサポートするためパソコンの電源、LANまたはWiFi端末を設置する)
- インターネットでの議会中継を充実させるため、質問席側を撮影できるカメラを増設する
- 代表質問に持ち時間内で質問者を複数立てることを認める(例えば、120分の持ち時間でA党が5つの大項目で質問を行う場合、A党所属のB議員は3項目、C議員が2項目の質問を行う)