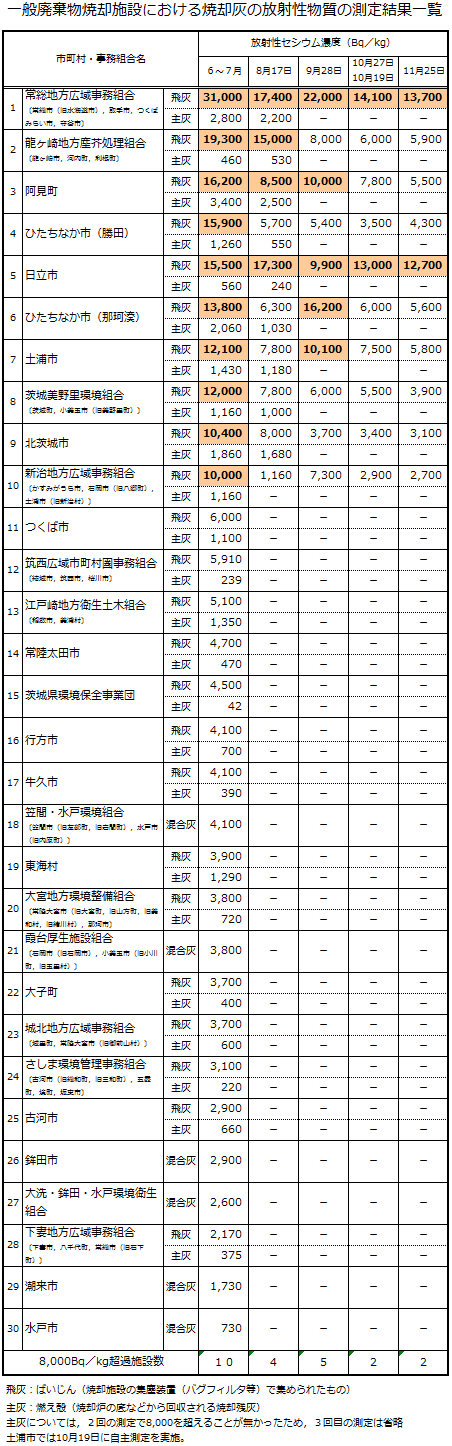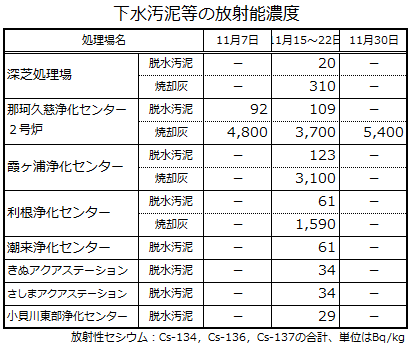東京電力福島第1発電所の原発事故により、県内のごみ焼却施設や下水処理場などの煤塵(ばいじん)から放射性物質が検出されています。国は、8000超~10万Bq/kg以下の焼却灰を埋め立て処分する場合、(1)セメントで固める、(2)耐久性のある容器に入れる、(3)隔離層を設けて水の浸入を防止、(4)施設に屋根を付ける、などの方法で放射性物質の流出を防ぐことを求めています。(10万ベクレルを超える焼却灰の処理方法については、未だに指針が示されていません)
東京電力福島第1発電所の原発事故により、県内のごみ焼却施設や下水処理場などの煤塵(ばいじん)から放射性物質が検出されています。国は、8000超~10万Bq/kg以下の焼却灰を埋め立て処分する場合、(1)セメントで固める、(2)耐久性のある容器に入れる、(3)隔離層を設けて水の浸入を防止、(4)施設に屋根を付ける、などの方法で放射性物質の流出を防ぐことを求めています。(10万ベクレルを超える焼却灰の処理方法については、未だに指針が示されていません)
茨城県内の10カ所の市町村や一部事務組合のごみ焼却施設では、この政府の暫定基準を超えた煤塵の処理場所が確保できず、現在までに1671トンの煤塵が施設内に保管されてています。
来年1月1日に施行される「放射性物質汚染対処特措法」では、一定基準以上の放射性物質に汚染された廃棄物は「国が処理する」とされており、各ごみ焼却施設の管理者は、国の動きを静観している状態です。
ただし、保管場所まで国が手配することは期待できず、結局、地方自治体が処分先を探さなくてはならない状況になる可能性があります。
この夏には、民間最大規模のごみ焼却灰処分場のある秋田県小坂町で、一旦は引き受けた首都圏からの焼却灰の一部が8000Bq/kgの暫定基準を超えたため、送り返されるという事態が発生しています。県内でも「江戸崎地方衛生土木組合」の焼却灰が、暫定値以下にもかかわらず返却されています。
ごみ焼却場の放射性物質問題は、まさに「トイレのない住宅」のような状況になりつつあります。
同じような問題は、県内の下水処理施設でも起きています。那珂久慈浄化センター(4800Bq/kg)、霞ヶ浦浄化センター(3100)、利根浄化センター(3100)などの県南地域の処理場では、暫定基準は下回っているものの、放射性セシウムが検出されています。
特に、土浦市湖北にある霞ヶ浦流域下水道事務所の霞ヶ浦浄化センターでは、保管されていた焼却灰から高い線量の放射性セシウムが測定されたことが、12月5日に判明しました。5月5日以前の保管分について、今回計測したところ、放射性セシウムが17,000Bq/kg検出されたということです。焼却灰の量は69.4tに及びます。古い時期の焼却灰が下(奥)の方に積まれていたために、測定ができなかったというのが理由です。焼却灰の放射能測定がいかに杜撰に行われてきたかを物語る内容です。