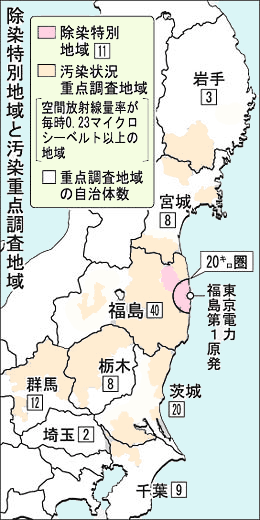 今年1月1日、東京電力福島第1原発事故に伴う放射性物質に汚染された廃棄物の処理や土壌などの除染を国の責任で行う「放射性物質汚染対処特別措置法」が完全施行されました。
今年1月1日、東京電力福島第1原発事故に伴う放射性物質に汚染された廃棄物の処理や土壌などの除染を国の責任で行う「放射性物質汚染対処特別措置法」が完全施行されました。
それに先立ち、環境省は12月28日、国の責任で除染を行う「除染特別地域」と、国が廃棄物の収集から運搬、保管、処分までを実施する「汚染廃棄物対策地域」について、福島県富岡町など原発から20キロ圏内の警戒区域や、放射線量が年間20ミリシーベルトを超える計画的避難区域の11市町村を正式に指定しました。
また、自然界からの被ばくを除く追加線量が年間1ミリシーベルト(毎時0.23マイクロシーベルト)以上の地域がある市町村が対象となる「汚染状況重点調査地域」に、8県102市町村を指定。県別では福島(40市町村)が最も多く、次いで茨城(20市町村)、群馬(12市町村)、千葉(9市)、宮城(8市町)、栃木(8市町)、岩手(3市町)、埼玉(2市)となりました。なお、茨城県の20市町村は、北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、東海村、ひたちなか市、土浦市、阿見町、稲敷市、美浦村、つくば市、つくばみらい市、牛久市、龍ヶ崎市、利根町、取手市、守谷市、常総市、鉾田市、鹿嶋市です。
「汚染状況重点調査地域」の指定を受けた市町村は、地域内の放射線量を調査して除染実施計画を策定し、国の財政支援の下で除染作業を行います。しかし、国から具体的なモデルが示されていないことや除去した汚染土の仮置き場の確保が難しいことなど、その課題は決して少なくありません。
 中でも一番の課題は、除去した土砂を処分する場所の問題です。日立市の除染の責任者は、「除去した物を最終的にどう処分するのか見えないため、仮置き場も確保した方がいいのかさえ分からない」と語っています。
中でも一番の課題は、除去した土砂を処分する場所の問題です。日立市の除染の責任者は、「除去した物を最終的にどう処分するのか見えないため、仮置き場も確保した方がいいのかさえ分からない」と語っています。
さらに、計画の策定区域は字や街区などの区域単位で平均値を算出して判断するため、広い範囲で平均すると、結果的に基準値を下回る地域が出てくる場合もあります。逆の言い方をすれば、局所的に放射線量が高い場所(マイクロ・ホットスポット)の除染には、国に枠組みが使えないと言うことになります。
実際に、除染作業を行う現場では新たな問題も起こっています。学校の校庭などの場合、表面から1~3センチ程度の汚染された表土を削ぎ取ることになりますが、その入札方法が従来の土木工事などと同じ積算基準で行われています。例えば、芝生などがない場合でも、3センチ撤去して線量が思うように下がらない場合、5センチ、7センチと深く表土を削っていきますが、落札された工事予算内で納まらないケースが発生しています。また、それを恐れて、除染作業の入札自体が不調に終わるケースが頻発しています。作業を速やかに進めるためには、除染作業に特化した積算基準を早期に示す必要があります。



