東海第2発電所の再稼動問題などを受けて注目されている東海村議会議員選挙が、来週1月17日告示、22日に投票日を迎えます。1月2日現在の有権者数は3万1人です。
昨年12月21日の定例記者会見で、東海村の村上達也村長は東海村議選について、「私が『脱原発』というアドバルーンをあげたのだから、各々の候補者は声を出してもらいたい」と発言。さらに、「立候補者は意見表明が必要だし、村民はそれについて判断する必要がある」と指摘しています。
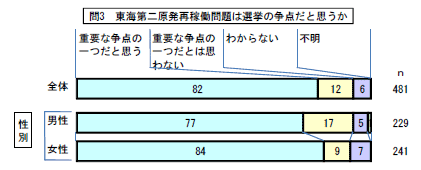
一方、茨城大学地域総合研究所は、東海第二原発の再稼働問題に焦点を絞って、東海村議選挙の政治的、政策的な争点として東海村の有権者が何を重視しているかアンケート調査を実施。その結果を12月に公表しています。それによると、「東海第二原発の再稼働問題が、村議選の重要な争点の一つになると思うか」との設問に、「重要な争点の一つだと思う」人81.5%、「重要な争点の一つだとは思わない人」12.3%という結果で、大多数の人が地元原発の再稼働問題を選挙の重要な争点と考えていることが明らかになっています。
こうした客観的な情勢や有権者の思いとは裏腹に、東海村村内を歩いてみると、村議選各陣営の東海原発再稼働に関する議論があまりに低調なのに驚かされます。街頭で原発問題に言及しているのは、公明党や共産党、一部の無所属議員のみで、村内には選挙ムードの高まりも感じられません。
住民の多くが原子力関連事業に関わっている土地柄であるがゆえに、簡単には原発の廃炉や再稼働について、意見を表明できないという背景がそこにはあります。
このような状況の中、毎日新聞水戸支局が「東海村議選候補者アンケート」を企画しました。予定候補者全員に5つの設問からなるアンケート調査票を送付し、1月15日までに回答を求めています。以下その設問を転載します。
①支持する ②支持しない ③その他
【設問2】村が進める「原子力センター構想」を支持しますか
①支持する ②支持しない ③その他
【設問3】今年8月に定期点検終了を迎える東海第2発電所は、その後どうすべきだと考えますか
①すぐに再稼動すべきだ ②耐震膨張策を徹底してから再稼動すべきだ ③いったん廃炉にし、新型炉を新たに建設すべきだ ④廃炉にすべきだ ⑤その他
【設問4】東海第2原発の再稼動について、村上村長は住民投票に言及していますが、住民投票は必要だと考えますか
①必要だ ②必要ない ③その他
【設問5】村は今後どのような方向性を目指して地域づくりを進めるべきと考えますか
①原子力エネルギーと最先端の原子力科学の促進で中心的な役割を果たす
②廃炉技術の研究や自然エネルギーの研究など脱原子力の方向で中心的な役割をはたす
③その他
この設問を一目見て、廃炉か再稼動かの二者選択の設問にはいささか面食らいました。真剣に東海原発の問題に取り組もうとすると、全ての設問が「その他」という回答になってしまいます。
井手よしひろ県議が、もしこのアンケートに回答するとすると以下のようになります。
「脱原発」「廃炉」という発言の方向性は評価します。しかし、その議論の過程は議会や住民との対話がさらに必要と考えます。
村上村長の提唱する「原子力センター構想」には全面的に賛成です。しかし、この構想は東海村一村で実現できる課題ではありません。県との連携を強化し、広域的な取り組みが必要です。
まず、国が再稼動をさせるかどうかの判断が定まっていないので、県や村が判断を出せる段階ではないと考えます。原発の寿命を40年とする法改正が通常国会には提出されると言われています。また、すでに東海第2と女川原発は、他の原発と違う枠組みで再稼動を検討する特には表明しており、何よりも国の動向を注視することが必要です。その上で、もし再稼動させるに当たっても、①福島第1原発の事故が完全に収束していること、②15メートル級の津波への対応が完了していること、③新たな原子力安全対策範囲への対応が完了していること、以上3点条件を満たす必要があると考えます。
通常、国や事業者が再稼動を前提にしている場合に、住民投票は行われます。国の方向性が示されていない中での、議論は時期尚早のように思えます。万が一、国が再稼動を認めるような状況の中では、住民の意見を集約するために住民投票やアンケート調査などは必要であると考えます。
二者選択では東海村は生き残れないと思います。原子力発電に依存する割合は早急に少なくする必要があります。しかし、村民の雇用や村の活力を維持することは村政の絶対条件です。原子力エネルギーと最先端の原子力科学の促進で中心的な役割を果たすことも、廃炉技術の研究や自然エネルギーの研究など、長期的な視点で脱原子力の方向で中心的な役割をはたすことも、必要であると考えます。
東海村議選17日に告示、「脱原発」ぼやける争点
読売新聞(2012/1/13)
日本原子力発電東海第二発電所が立地する東海村で、村議選の告示が17日に迫った。福島第一原発事故の発生や村上達也村長の「脱原発」表明を受け、同発電所の再稼働の是非が選挙戦の争点に浮上した。だが、今のところ立候補を予定しているのは定数より1増の21人にとどまり、村の将来を左右する原発問題の論戦は低調になりかねない。
今月8日、親子連れでにぎわう村内のスーパーマーケット前。新人の立候補予定者が、のぼりを手にした後援会メンバーと行き交う車に頭を下げていた。「原子力は欠かせないエネルギーの一つ」と原発推進を掲げ、告示後に有権者に配るチラシでも「原子力との共存共栄」を打ち出した。
後援会の中には「そこまで踏み込んで書くべきではない」との声もあり、意見は真っ二つに割れた。有権者から「原発推進派には票を入れたくない」とはっきり言われることもあり、「失う票があるのは覚悟しているが、誰かが必要性を訴えなければ議論はできない」と、選挙戦が盛り上がることを期待する。
◇
村議選は今回、5人が引退を決め、現職15人と新人6人が立候補の準備を進めている。
村上村長は昨年10月、細野原発相と面会した際、定期検査中の東海第二発電所の「廃炉」を提案した。12月の定例記者会見では「自分は脱原発のアドバルーンを上げた。候補者も意見を出してもらいたい」と、再稼働の是非が争点になることを望んだ。
しかし、村議会では「原子力を推進する議員有志の会」に15人が加盟し、原発推進派が大勢を占める。村上村長に共感する新人の出馬表明が相次ぐことも予想されたが、新人6人の中で「脱原発」を掲げるのは少数。村議会の勢力図に大きな変化を与えるような動きに発展しておらず、立候補予定者が少ないこともあり、原発問題を巡って活発な論議になるかは不透明だ。
村上村長は会見の場で「私は政党を作り、明確に同じ考えを持つ仲間と政治活動をしているわけではない。立候補者にはそれぞれの思いがあり、強引に多数派工作をしていくのは難しい」とも述べた。
◇
原発問題は選挙戦術にも影響を与えそうだ。推進派の現職は、前回はチラシに「推進」と書いたが、今回は「エネルギーとしての役割」とトーンを下げた。村長の脱原発表明後、支持者から雇用や経済への影響を心配する声が多く寄せられているといい、「村の未来に原発は必要」との思いは変わらない。しかし、「原発事故が収束しない中で推進とは書きにくい」と打ち明ける。
村長支持派の間でも対応は分かれる。現職の1人は「原子力の安全強化」を訴えることにした。「原発の危険性を感じる支持者は確実に増えた」と感じているが、「村内には原子力に携わっている人が大勢いるのも事実」と、脱原発を鮮明にすることには慎重な姿勢を見せる。別の現職は「国のエネルギー政策が決まっておらず、まだ廃炉にすべきかどうか決めかねている」と、村長とは一線を画す。
人口約3万7000人のうち、家族を含めて3分の1が原子力関連施設に関連していると言われる原子力発祥の村。共存共栄の歴史は長く、ある現職は「福島の現状を見れば原発は安全だとは言えない。しかし、この村には原子力に生涯をささげた人が多くいる。推進、反対を簡単に口にできるわけがない」と話す。



