井手よしひろ県議は、茨城県内の学校給食における放射性物質の検査体制について調査。その充実について、3月議会の代表質問で知事並びに教育長へ具体的な提案を行う予定です。
2月1日現在で県内の市町村毎に放射性物質の検査状況を見てみると、検査実施中(予定を含む)が3 8市町村、検討中が5市(鹿嶋市、潮来市、行方市、古河市、下妻市)、実施の予定なしが1町(五霞町)となっています。
主な市町村の実施状況を見てみると、水戸市では、学校給食共同調理場に簡易検査機器を配置し、共同調理場分は毎日2品目程度、
単独調理場分は1校あたり月1~2品目程度の検査を実施しています。併せて1食まるごとの検査も行っています。
笠間市では、市庁舎に簡易検査機器を配置し、各調理場の1食まるごと検査を週1回ずつ実施しています。
つくば市も、市庁舎に簡易検査機器を配置し、各調理場につき週2~3回(1回あたり3検体。うち1検体は1食まるごと、残り2検体は食材)の検査を実施しています。
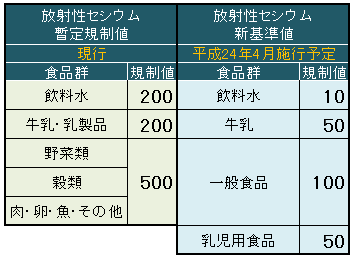 国は、食品の新たな基準値の設定について検討しています。現在の暫定規制値に適合している食品は、一般的に健康への影響はないものとされ、安全は確保されていると考えられていますが、より一層、食品の安全と安心を確保する観点から、厚生労働省において新たな基準値の設定が進められています。
国は、食品の新たな基準値の設定について検討しています。現在の暫定規制値に適合している食品は、一般的に健康への影響はないものとされ、安全は確保されていると考えられていますが、より一層、食品の安全と安心を確保する観点から、厚生労働省において新たな基準値の設定が進められています。
具体的な放射性物質の検査法は、厚生労働省の平成23年11月10日付け通知を準拠して行っています。
- 牛肉における放射性物質の問題を受け、多数の試料をより効率的に検査するために定められた検査手法
- 検体の放射性セシウムが暫定規制値よりも確実に低いことを判別するために規制値の10分の1(50Bq/kg)以下を測定下限値とする機器を用いて、規制値の2分1 (250Bq/kg) よりも低い値であることを確認する手法
- 現在は飲料水、乳及び乳製品を除く食品全般に適用されている
- 基準値の見直しに伴い、一般食材を対象に現在改正中であり、改正案では測定下限値を規制値の4分の1 (25Bq/kg) 以下としている
一方、文部科学省は、学校給食における安全と安心の確保に向け、安全・安心のための学校給食環境整備事業と学校給食モニタリング事業を行っています。
安全・安心のための学校給食環境整備事業では、茨城県を含む17都県を対象として、都県が検査機器を購入する際の費用を全額補助しています。茨城県では5台程度が認められています。
学校給食モニタリング事業は、47都道府県を対象として、実際に提供した学校給食のー食全体を検査機関に依頼して検査します。福島県は各市町村1校,それ以外は2市町村から各1校程度を選定して行います。
茨城県としては、県立学校の学校給食について放射性物質の検査を実施するほか、検査体制の整わない6市町の学校給食についても、要望に応じて検査が可能となるよう、国の補助事業を活用して検査機器を整備します。(5台)
新たな基準の策定などの国の動向について、各市町村に対して速やかに情報提供を行い、安全で安心な学校給食が実施されるよう努めることにしています。
こうした現状の上で、子どもたちの内部被ばくを出来るだけ少なくするために、井手県議は以下の提案をしています。
- 「1食丸ごと事前検査」を、除染重点調査市町村に指定された全ての学校で行える体制を確立する
- 学校給食衛生管理基準には、調理後2時間以内に給食を実施することが定められている。そのために、「1食丸ごと事前検査」を可能とするために、新たな検査装置の開発を県が先導して進める
- 新基準による検査を前倒しで実施する



