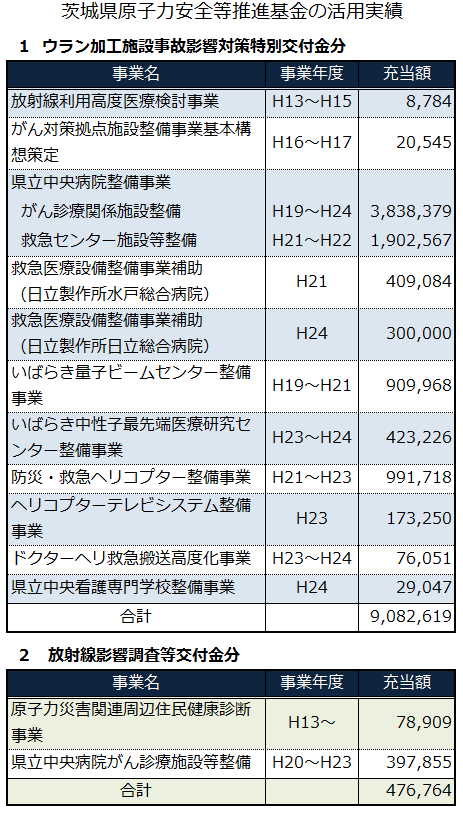9月議会に提案された平成24年度の補正予算には、「原子力安全等推進基金」を取り崩し、県立中央病院の陽電子放射断層撮影装置(PET)を更新する予算2億5400万円が盛り込まれました。この「原子力安全等推進基金」は、1999年9月30日に発生したJCO臨界事故に関連して国から交付された「ウラン加工施設事故影響対策特別交付金分」と「放射線影響調査等交付金分」を基に造成されました。JCO臨界事故の影響を受けた近隣住民の健康診断等を長期間にわたり行う事や東海村を中心とする放射線医療の充実に充てることが目的でした。
9月議会に提案された平成24年度の補正予算には、「原子力安全等推進基金」を取り崩し、県立中央病院の陽電子放射断層撮影装置(PET)を更新する予算2億5400万円が盛り込まれました。この「原子力安全等推進基金」は、1999年9月30日に発生したJCO臨界事故に関連して国から交付された「ウラン加工施設事故影響対策特別交付金分」と「放射線影響調査等交付金分」を基に造成されました。JCO臨界事故の影響を受けた近隣住民の健康診断等を長期間にわたり行う事や東海村を中心とする放射線医療の充実に充てることが目的でした。
県は当初、がん治療のための新型放射線治療装置(粒子線治療装置:FFAG)の開発を進める計画でしたが、開発費が高額になること等により断念。より現実的な、県立中央病院の整備や県北地域の放射線治療装置の整備、ドクターヘリの導入など、県民の利用環境の充実のために活用しました。
9月7日付けの地元紙・茨城新聞の一面には、こうした経緯を紹介する記事が掲載されました。その中で、この基金の活用についてその議論をリードしてきた井手よしひろ県議のコメントが紹介されました。井手県議は、「県民のがん対策や放射線医療の充実に貢献はしたが、本来の趣旨である臨界事故周辺住民の医療向上にもっと使ってほしかった」、「福島原発事故を受け、母親が不安がっている子どもの甲状腺検査の補助に使ってもよかったのではないか」と述べています。
臨界事故基金 総額92億円使い切る
茨城新聞(2012/9/7)
県中央病院整備に6割
1999年に起きた東海村臨界事故の後、県が国の交付金で創設した「原子力安全等推進基金」(92億円)が9月補正予算で全額使い切られることになった。最後の事業は、がんの早期発見に有効とされる県立中央病院(笠間市)の陽電子放射断層撮影装置(PET)の更新2億5400万円。創設から12年間で基金の6割以上が同病院の施設整備に充当され、ほかに防災・救急ヘリ購入や「いばらき量子ビーム研究センター」(東海村)の整備などに使われた。
同基金は、臨界事故でダメージを受けた地元対策として県が国に要望し、地元選出の故梶山静六元官房長官らも尽力して2000年に創設された。
当初は放射線を利用した高度がん治療施設を東海・ひたちなか地区に整備する財源に全額充当する構想だったが、施設の鍵を握る新型陽子加速器(FFAG)の実用化のめどが立たず、06年に断念。県は▽県立中央病院のがん診療施設整備▽大強度陽子加速器施設(J-PARC)の産業利用を促進する量子ビーム研究センター整備▽原子力防災や救急医療体制の充実-などに幅広く基金を活用する方針へかじを切った。
主な使途は、中央病院の施設整備(放射線治療、化学療法、人工透析、救急の各センター)に約57億円、量子ビーム研究センターと中性子医療研究センターの整備に約13億円、防災・救急ヘリやドクターヘリ事業に約11億円。ほかに日製日立総合病院と日製ひたちなか総合病院の救命救急センター整備に約7億円を補助した。
県議会で同基金について長年取り上げてきた井手義弘氏(公明、日立市選出)は「県民のがん対策や放射線医療の充実に貢献はしたが、本来の趣旨である臨界事故周辺住民の医療向上にもっと使ってほしかった」と指摘。「福島原発事故を受け、母親が不安がっている子どもの甲状腺検査の補助に使ってもよかったのではないか」とも述べた。
県によると、2000年から継続している臨界事故周辺住民の健康診断事業の財源として3億円は確保してあるという。今後の課題について「整備した施設や機材を更新するとき、別の財源を探さないと-」(財政課)としている。